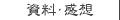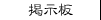「LOVER 【夢 幻 泡 影】 壱」 優サマ
大晦日、西国の筑前(ちくぜん)に聳え立つ城の主達が、宴を繰り広げていた。
ただの宴ではない。
この国一帯を支配する長兄弟の母なる者が、過去に厭魅(えんみ)に遭い、
命は取り留めたものの、代わりに死の病を患ってしまった。
それを払う為に、年に一度の大晦日に、この宴が施される。
家臣は管絃を奏で、厄払いの言を唱え、
侍女達は左手に小賀玉の木の枝を、右手に鈴を持ち、鈴を鳴らしながら踊る。
それを濡れ縁から長兄弟と葦が眺めていた。
間もなく、この一族の姫が額に白い鉢巻を締め、弓矢を持って奥から現れた。
清牙王と葦の一人娘の流麗だ。
姿は父方譲りで、輝く黄金の目に、頬には計四本の薄紫色の弧状の線が浮かぶ。
白銀色のさらりとした髪を頭頂部まで上げて紐で括り、そこから毛先は、膝まで至る。
天下に名高い大妖怪の血筋を継ぎ、
これまであらゆる妖怪と闘ってきたが、やはり流麗も人間と変わらぬ年頃の娘。
化粧や装飾に興味を持つのはもちろん、植物を愛で、優しい心を持つ動物達と心を交わす。
書をたしなみ、すらすらと歌を詠めば、詩も詠み、母から教わった笛をこよなく愛する。
まこと、その名のとおりの心優しい娘である。
流麗は長や両親を背に、弓を引いた。的は池の向こうにある鬼の顔を描いた絵。
ここからは十メートルある。
流麗はその鬼の絵を見つめ、狙いを定め、矢を放った。
流麗が狙う者は百発百中。放たれた矢は、見事、鬼の額を貫いた。
姫君の弓の技を見て、そこの者達は皆、「おう」と関心する。
それから流麗は、鬼の左目、右目、鼻、左耳、右耳、口と、次々と的を射抜いた。
それから世間は新年を迎えた。
新年早々雪が降り、あたり一面は一瞬にして銀世界である。
この日の早朝、闘牙王と清牙王は調べものがあるといって、
氷雪、冥加と、他の家来を連れて城を留守にしている。
城に残っているのは祖母と、祖母を看病する葦。
長兄弟に仕える家来の子供達と、そして流麗と、幼い殺生丸だ。
長と父より城の留守を任された流麗だが、
正午を回ると、己の牙で鍛えた剣を持ち、殺生丸と近場の広野へやって来た。
その剣を殺生丸に渡すと、流麗は言った。
「さあ殺生丸、私を相手に剣を振るってみよ。いいか、手加減なしに、本気だぞ」
厳しい男口調で言う流麗に、殺生丸は戸惑うような表情を見せた。
「万一の事を思ったら、それは……できません」
常に流麗を慕う殺生丸だ。
身を案じてくれるのは嬉しいが、もはやそう思ってはいけない。
「たとえ片やが剣を持って立ち会えば、敵同士。情けは無用!」
おのれより目上の、どんな命令にも殺生丸は逆らえない。
やがて殺生丸は剣の柄を握り、そして素早く剣を抜くと、流麗に刃を向けた。
“殺生丸に剣の技を教えよ”
長からそう命じられ、まだ半年しか経っていないのに、殺生丸の剣の技は見事なまでに上達している。
その広野では、時折、怒涛の如き殺生丸の声が響き渡った。
その後、剣は草叢の上に突き立てられ、流麗と殺生丸がとても楽しそうに戯れていた。
殺生丸が人間の子供と同じように楽しい、笑い声をあげている。
闘いもなく、とても平穏なこの時、流麗と遊ぶことが、この時の殺生丸は何よりの幸せだった。
ふと流麗が何か気配を感じ、背後の方を振り向いた。
流麗が見る方を、殺生丸も見る。
「――姉上、あれは……」
二人が目にしたものは、将軍を前に、何百という武士の数。
どの者も、長刀(なぎなた)を持っている。
「どこか地方の者達か……城の方へ向っているな」
広野からずっと武士達を通り過ぎるのを見る二人だが、その時、流麗の表情が一変した。
「殺気だ!奴ら、城を襲うつもりだぞ!」
「戻りましょう、姉上。お婆様の身が心配です!」
流麗は草叢に突き立つ剣を手にすると、殺生丸と急いで城へ戻った。
城の前には、長兄弟の仕いの子達が雪に戯れている。
案の定、武士達はそこにやって来た。
馬に跨る将軍は刀の刃を城の方へ向け、怒鳴り散らした。
「前は天下(てんが)を脅かす妖怪共だ!勇敢に闘いし者は、栄光の勝利をくれてやろうぞ!」
「おう!」
将軍に武士達は猛々しく答え、そして将軍は武士に命じた。
「ならば遠慮はいらぬ!殺してしまえ―――!!!」
そう将軍叫んだら、武士達は長刀を抜き、走り出した。
そこに流麗と殺生丸が戻ってきた。
目前の光景を見るや、武士が一族を容赦なく襲っている。
逃げ回る子達の前に、剣を抜いた流麗が立ち、武士と刃を交え、
殺生丸も爪から伸びる光るムチで武士を薙ぎ払う。
だがこの武士らは所詮は人間。無駄に殺すことは出来ない。
殺さずに相手にすることは、無駄に体力を使い、すぐに息が上がる。
せめて長と父達が戻ってくるまでは、この二人は必死だった。
暫くして、大半の武士は追い返しただろうか。偶然、流麗は城の方へ目をやった。
すると何と、あの将軍が武士を率い、流麗や殺生丸の目を盗んで城へ乗り込んでいる。
「お婆様!」
最早その場の武士は眼中になく、殺生丸も残したまま、流麗は疾(と)く城へ走った。
最上階にある祖母の部屋へ疾走する途中、母の叫び声が聞こえた。
それと同時に、濃い血の臭いも捉える。
遂に祖母の部屋に辿りつくと、そこには、肩から腕にかけて深い斬り傷を負った母と、
既に将軍の長刀によって殺された祖母の姿があった。
その光景を見ると言葉が出ず、だがその瞬間、流麗の形相が一変した。
あの透き通るような黒い瞳が青紫に、その周りが燃え盛る炎のような紅蓮の如く真赤に変色した。
頬に浮かぶ弧状の線が歪に変形し、また口から、上側の鋭い牙が剥き出しとなった。
利き手に持つ柄が、ミシミシとなく。
ついに怒りが頂点を達した。
「おのれ……貴様!!!」
速く武士の元へ駆けると、本性を露にした流麗は荒く剣を振り、武士を斬り殺していく。
流麗に対し、武士は反撃しようとするが、あまりの速い動きに逆に虐殺される。
粗方武士を殺すと、流麗が次に目をつけたのは、祖母を殺し、母に重傷を負わせた将軍。
「将軍!」
両手で剣を持ち、猛々しい大声をあげながら将軍の傍へ駆け、また剣を振るった。
だが流麗の剣の技を、将軍は長刀で一つ一つ確実に受け止め、素早くその刀を流麗に目掛け振るい落とした。
流麗は宙を返り、将軍から離れた。
将軍はギロリと流麗を見ると、言った。
「来い!醜い妖怪!!!」
流麗は剣を放り投げた。
爪で止めを刺すつもりだ。
「――流麗、いけません!」
荒れ狂う我が娘に、葦が声をあげたが、母の声は流麗の耳には聞こえていない。
変化の際に何十寸も鋭く伸びた爪を将軍に向け、大きく一歩を踏み出した。
「死ねえ―――!!!」
勢いをつけ、そして爪を振るった。
同時に将軍も刀の刃を真っ直ぐ突きのばす。
その時、流麗と将軍の間合いに清牙王が入り込んだ。
突然のことに、流麗の爪はそのまま清牙王の硬い鎧を砕き、身をも引き裂いてしまった。
「双方とも動くな!!!」
清牙王は将軍の喉元に剣の刃を突きつけ、声を上げる。
「一寸たりとも動くな。動けば、この喉に風穴があく」
前を将軍に、背後を流麗にして、清牙王は将軍に言う。
「人間風情がここまで来た事は褒めてやろう。
だが身に覚えのない怨みに、我が母を殺し、更には妻を傷つけるとは如何なる料簡か?」
「――――」
「戦を仕掛けるには、必ずや何かの訳があるはず。答えよ」
清牙王の言葉に、将軍が突如不気味な笑い声をあげた。
その不気味な嗤(わら)いをあげれば、口の中の黄色い歯が見える。
笑いを止め、だが顔をにやつかせ、将軍は清牙王に答えた。
「妖怪など、恐るるに足らぬ」
「――何……?」
「世を牛耳る妖を撲滅する為、我らは地方へ行っては、妖怪退治を施してきた。
だが今回、その女妖怪がこれほど強力とは不覚だったな」
「こやつは血肉を分け与えた我が娘だ。先祖代々、大妖怪の血を継いでいる。
これは全て貴様の企て。決して娘を怨むな」
「その目つき……如何にも我を殺したいような」
「――――」
「ならば望みを叶えてしんぜよう。さあ、その剣で我の喉を突いてみよ。
母や妻の仇に。憐れな愛娘の変わりに――」
一つも恐れ戦く様子もなく、清牙王に挑発する。
その原因で、次第に清牙王の妖気が部屋に充満する。
「あなた……己を保って」
憤る清牙王に、葦はせめて言葉で、清牙王の気を落ち着かせる。
清牙王の背後に立つ流麗は、漸く正気に戻った。
ふと己の着物や利き手など見ると、武士を殺した際に飛び散った血がべっとりと染み付き、
渾身の力で剣を放り投げ際に、銀(しろがね)の刃が深く壁に突き立っているが、その刃も柄も、真赤に汚れている。
それよりも父が羽織る真っ白な毛皮が、徐々に紅く染まっていく。
目前の光景がとてもおぞましく、遂に流麗は意識を失った。
倒れる娘に、清牙王は咄嗟に娘の細身を抱え、その時、将軍の喉に突きつける剣を引いてしまった。
剣を引いたと同時に、将軍や武士が一斉に動いた。
「動くな!殺すぞ!!!」
清牙王の長剣の刃が再び将軍に向けられる。
その場に漸く闘牙王と、氷雪と殺生丸がやって来た。
「お母様……」
夥しい血に汚れた部屋や、何よりとても信頼していた義母の無惨な姿に、氷雪は完全に言葉を失う。
闘牙王は清牙王の横に立った。
「清牙王、後は俺がしよう。早く、葦と流麗を連れ出せ」
清牙王は流麗を抱え、葦と部屋を出ようとした。
だが立ち上がった葦は闘牙王の背後に立ち、闘牙王に言った。
「お兄様、その者達は所詮は人間です。どうかお兄様の慈悲のお心で、お命だけは……」
闘牙王は答えない。
やがて清牙王に連れられ、部屋を後にした。
その後、氷雪は闘牙王と並び、当の闘牙王は背に下げる魔剣を抜いた。
これから将軍や、数えるほどの武士達に対し為す両親を、殺生丸は扉の横でじっと眺めていた。
二日後の朝、殺生丸が目を覚ますと、また流麗がいない。
一体、どこへ行ったのか。
城中を探してもいないし、家来達に訊ねても口を合わせて知らぬという。
終いには、大広間にいる両親や叔父夫婦に訊ねることにした。
「まあ、殺生丸。起きましたか」
「――姉上はどこです」
殺生丸が流麗の事を言うと、やはり皆は口を閉ざた。それでも殺生丸は、尚も迫る。
「あの日以来、姉上は上の空。一言も告げず、独りでどこか行って、戻っては来ない」
殺生丸が心の奥底から流麗を案じ、そんな殺生丸についに清牙王が言った。
「流麗は、東の広野へ、嵩明良といる」
そういえば嵩明良の姿も見えないと思っていたが、まさか流麗といるとは。
東の広野といえば、先日流麗と勝負し、遊んだ所。
そう聞くと、殺生丸は両親達に背を向けた。
「待て」
殺生丸が扉に手をかけ、開けようとした時、父の闘牙王が言った。
「旦那様……」
「殺生丸、流麗の所へは行くな」
「――なぜです」
「理由は訊くな。暫しの間は、流麗とは関ってはならん」
一方の流麗は、広野と嵩明良といた。
嵩明良は嘗ては出雲国を治める王の息子だった。
嘗て嵩明良には姉と兄がいたが、王なる父はあえて嵩明良に王座を委ねる為、ある一族の姫・如月と許婚とした。
時が流れ、近々如月姫と祝言を挙げ、王座を継ぐはずだったが、
ある敵との乱闘の末に一族と如月姫を失ってしまった。
死に物狂いで如月姫を守ろうとした証が、左の頬に残る刀傷の跡だ。
以後、嵩明良は一人で故郷を治めていたが、それからある長月の季節に、西国の流麗姫と出会った。
流麗と共にあらゆる苦難を乗り越え、今は故郷を治めつつ、流麗の一族と行動を共にしている。
半月程前から故郷の出雲に異変が起こり、ずっと帰省していたが、つい昨夜に戻った。
流麗は竜笛を、嵩明良は得意とする楽琵琶を布に包み、
背負(しょ)って、未だ雪が残っているこの広野にやって来た。
「お婆様の事は、とても残念だ」
嵩明良が言った。
数分の沈黙の後、流麗は漸く答えた。
「私の力か、お館様が天生牙を用いれば、お婆様は再び息を吹き返したのに……。
お館様と父様は、迷わずお婆様を葬られた」
まるで冷静な流麗に、嵩明良の目には流麗の背後しか見えない。
泣いているのか、怒りに満ちているのか、それとも、放心しているのか。
流麗が今どんな顔でこう言っているのか、予想は出来ない。
突如流麗が、嵩明良の胸に飛び込んだ。
泣いていた。
涙を溢し、嵩明良の着物を強く握る。その流麗に、嵩明良はそっと優しく流麗の体を包み込んだ。
「嵩明良……私は自分が怖い。目前の憎しみや哀しみに、簡単に心を狩られてしまう。
無駄に人を傷つけたり、殺したくないのに」
「――――」
“流麗姫はよく心に響く管を聴かせてくれる。まるで如月姫と同じ、善き優しき姫君よ”
この娘に対して、出雲国のある者が、嵩明良にそう言えば、
“流麗の男姫は、殺戮に度が過ぎる。関り持たぬ方が、そちの身の為ぞ”
と、言う者もいる。
確かに流麗が剣を持って敵と闘う姿は、言葉では言い難い。
だがそれは、敵から戦を仕掛け、流麗には守るべき者がある故に、その敵と闘い、倒す。
流麗自らが闘いを挑むことは全く無い。
嵩明良がこの娘に惚れたのは、闘う姿ではない。
生きとし生ける者、どんな者も心から愛する、その優しいその心に惚れたのだ。
「流麗は、何も間違ったことはしていない。もう泣くな」
「――――」
「ならば流麗、吾も是非、お婆様の為に弔いの楽を贈ろう。
弔いだけではないぞ、お前のその憎しみや哀しみも解き放ちたい。いつまでもそんな顔は、見たくはない」
「――――」
「流麗、楽を――」
やがて流麗は懐に挿す竜笛を手に持ち、嵩明良は布に包んで背負う楽琵琶を取り出し、雪の上に座した。
嫋(じょう)……
嫋(じょう)……
嵩明良が楽琵琶を奏でると、流麗はそれに合わせて笛を吹き始めた。
絶妙に合う楽琵琶と竜笛の管絃の音色は、陽が西に落ちるまでずっと続いた。
この時奏でた曲は、流麗が得意とする、夢幻泡影(むげんほうよう)という曲だった。
――九月十五日の未の刻。
流麗は寝息を立て、ぐっすりと眠っている。
だが数時間した頃にどこから大勢の笑い声が聞こえ、ふと目を覚ました。
起き上がり、寝衣のままその声のする所へ向った。
濡れ縁で、馴染みのある仲間達が酒を酌みあい、早い宴を楽しんでいる。
「おう、お目覚めか。女王陛下」
一人が流麗に気づくと、一斉に流麗の方を向く。
その宴の中には、あの豹猫族の冬嵐の姿もあった。
冬嵐とも長い付き合いだ。
子供の頃は殺し合う程の激闘は常だったが、
いつぞやか冬嵐姉弟と犬夜叉、殺生丸が起こした戦の末、冬嵐達はあの兄弟共に流麗への敵意は失った。
今では仲間と共に、ここに来ることが日課である。
「そなた達、いつ来られた?」
「つい先ほどよ」
「我らが来た頃はそちはもう夢の中。起こすのも哀れかと、勝手に上がらせてもらった」
「そう……。いや、構わぬ」
「流麗、いつまでもそんな姿せず、服を着替えて我々と酒(ささ)を頂こうぞ」
「待て、斉資(なりすけ)。一人では、難儀なところもあろう。冬嵐、流麗に手を貸してやれ」
斉資といえば、過去に折れた剣のつなぎにする為、流麗の牙を抜いたり、
銀竜との闘いに斬られた流麗の腹の傷を治療した薬師だ。
その薬師と同年の男が言い、流麗は冬嵐と部屋へ戻り、服を着替え、再び仲間の元へ戻って盃を手にした。
それぞれ瓶子(へいし)を持って、横と酒を酌み合い、
「では」
「うむ」
声を掛け合って、一斉に酒を喉の中に流し込んだ。
酒のアテも欠かせない。
仲間の一人が持ってきた鰯(いわし)と松茸を炭で焼き、平等に皿に盛り、それぞれ前に箸と置いた。
皿の縁(ふち)には、鰯と松茸と一緒に焼いた味噌も添えられている。
松茸につけて食べると、味は更に旨さを増す。
庭には大池や、敷石が敷かれ、秋の花が咲き誇っている。
その花の香りと、流麗の狩衣の垂領(たりくび)と、指貫袴に薫き込んでいる薫衣香(くのえこう)の香が混ざり、
その場は仄かな甘い匂いが漂っている。
「あのようなことが起こらねば、今頃はお館兄弟や、お前の夫(つま)と酒を頂いているとゆうに」
「今よりも過去が恋しいというのは、一体何の縁(えにし)かな」
しみじみと言う仲間に、流麗は七色に輝く酒をじっと眺め、仲間達に答えた。
「それも神が万人に平等に与えた運命の一つ。誰も永久(とわ)なる命は、人も妖も持ち合わせてあるまい」
「――――」
「過ぎたる過去は幻よ」
「ほお、幻とな……」
「先日文月の頃に、犬夜叉に逢いに行った時、犬夜叉はそう言った。
あの子はいち早く人の心を察する優しく、素直な子だ。が……一つ、そうにはゆかぬものがある」
「――唐の銀竜ことか」
仲間がそういうと流麗は頷いた。更に流麗が言う。
「闘いの始まりはお爺様の代からで、今年で五百年だ。この因縁だけは、何としても断ち切らねばならない」
そう言う流麗に皆は言葉を詰まらす。
決意の固い流麗に、一人の男が真剣な表情で言った。
「流麗よ。我らはそなたが赤子の頃から知っている。
一族の為に全てを賭する事は、やはり気が進まぬのだ。
数百年も年月が経っているのだ、もう仇討ちなど、よいではないか」
「この男の言うとおりぞ」
仲間は一斉に首を上下に振る。
だが当人だけは、首を左右に振り、そして答えた。
「あの男が唐へ戻ったは、私を倒す為に剣の研鑽を積んでいるからだ。銀竜との決着は必ず果す」
「――流麗は諦めの悪い、犬夜叉と殺生丸の従姉(あね)です」
冬嵐が言った。
「近々は天下泰平も成そうとしている。流麗はこれまで何一つ物事を諦めず、成し遂げたのです。
銀竜との決着も必ず流麗が勝つ。我々は今までどおり、流麗を心から見守りましょうぞ」
冬嵐の発言に、他者は黙り込んだが、悔やみながらも冬嵐の言葉に従った。
ただの宴ではない。
この国一帯を支配する長兄弟の母なる者が、過去に厭魅(えんみ)に遭い、
命は取り留めたものの、代わりに死の病を患ってしまった。
それを払う為に、年に一度の大晦日に、この宴が施される。
家臣は管絃を奏で、厄払いの言を唱え、
侍女達は左手に小賀玉の木の枝を、右手に鈴を持ち、鈴を鳴らしながら踊る。
それを濡れ縁から長兄弟と葦が眺めていた。
間もなく、この一族の姫が額に白い鉢巻を締め、弓矢を持って奥から現れた。
清牙王と葦の一人娘の流麗だ。
姿は父方譲りで、輝く黄金の目に、頬には計四本の薄紫色の弧状の線が浮かぶ。
白銀色のさらりとした髪を頭頂部まで上げて紐で括り、そこから毛先は、膝まで至る。
天下に名高い大妖怪の血筋を継ぎ、
これまであらゆる妖怪と闘ってきたが、やはり流麗も人間と変わらぬ年頃の娘。
化粧や装飾に興味を持つのはもちろん、植物を愛で、優しい心を持つ動物達と心を交わす。
書をたしなみ、すらすらと歌を詠めば、詩も詠み、母から教わった笛をこよなく愛する。
まこと、その名のとおりの心優しい娘である。
流麗は長や両親を背に、弓を引いた。的は池の向こうにある鬼の顔を描いた絵。
ここからは十メートルある。
流麗はその鬼の絵を見つめ、狙いを定め、矢を放った。
流麗が狙う者は百発百中。放たれた矢は、見事、鬼の額を貫いた。
姫君の弓の技を見て、そこの者達は皆、「おう」と関心する。
それから流麗は、鬼の左目、右目、鼻、左耳、右耳、口と、次々と的を射抜いた。
それから世間は新年を迎えた。
新年早々雪が降り、あたり一面は一瞬にして銀世界である。
この日の早朝、闘牙王と清牙王は調べものがあるといって、
氷雪、冥加と、他の家来を連れて城を留守にしている。
城に残っているのは祖母と、祖母を看病する葦。
長兄弟に仕える家来の子供達と、そして流麗と、幼い殺生丸だ。
長と父より城の留守を任された流麗だが、
正午を回ると、己の牙で鍛えた剣を持ち、殺生丸と近場の広野へやって来た。
その剣を殺生丸に渡すと、流麗は言った。
「さあ殺生丸、私を相手に剣を振るってみよ。いいか、手加減なしに、本気だぞ」
厳しい男口調で言う流麗に、殺生丸は戸惑うような表情を見せた。
「万一の事を思ったら、それは……できません」
常に流麗を慕う殺生丸だ。
身を案じてくれるのは嬉しいが、もはやそう思ってはいけない。
「たとえ片やが剣を持って立ち会えば、敵同士。情けは無用!」
おのれより目上の、どんな命令にも殺生丸は逆らえない。
やがて殺生丸は剣の柄を握り、そして素早く剣を抜くと、流麗に刃を向けた。
“殺生丸に剣の技を教えよ”
長からそう命じられ、まだ半年しか経っていないのに、殺生丸の剣の技は見事なまでに上達している。
その広野では、時折、怒涛の如き殺生丸の声が響き渡った。
その後、剣は草叢の上に突き立てられ、流麗と殺生丸がとても楽しそうに戯れていた。
殺生丸が人間の子供と同じように楽しい、笑い声をあげている。
闘いもなく、とても平穏なこの時、流麗と遊ぶことが、この時の殺生丸は何よりの幸せだった。
ふと流麗が何か気配を感じ、背後の方を振り向いた。
流麗が見る方を、殺生丸も見る。
「――姉上、あれは……」
二人が目にしたものは、将軍を前に、何百という武士の数。
どの者も、長刀(なぎなた)を持っている。
「どこか地方の者達か……城の方へ向っているな」
広野からずっと武士達を通り過ぎるのを見る二人だが、その時、流麗の表情が一変した。
「殺気だ!奴ら、城を襲うつもりだぞ!」
「戻りましょう、姉上。お婆様の身が心配です!」
流麗は草叢に突き立つ剣を手にすると、殺生丸と急いで城へ戻った。
城の前には、長兄弟の仕いの子達が雪に戯れている。
案の定、武士達はそこにやって来た。
馬に跨る将軍は刀の刃を城の方へ向け、怒鳴り散らした。
「前は天下(てんが)を脅かす妖怪共だ!勇敢に闘いし者は、栄光の勝利をくれてやろうぞ!」
「おう!」
将軍に武士達は猛々しく答え、そして将軍は武士に命じた。
「ならば遠慮はいらぬ!殺してしまえ―――!!!」
そう将軍叫んだら、武士達は長刀を抜き、走り出した。
そこに流麗と殺生丸が戻ってきた。
目前の光景を見るや、武士が一族を容赦なく襲っている。
逃げ回る子達の前に、剣を抜いた流麗が立ち、武士と刃を交え、
殺生丸も爪から伸びる光るムチで武士を薙ぎ払う。
だがこの武士らは所詮は人間。無駄に殺すことは出来ない。
殺さずに相手にすることは、無駄に体力を使い、すぐに息が上がる。
せめて長と父達が戻ってくるまでは、この二人は必死だった。
暫くして、大半の武士は追い返しただろうか。偶然、流麗は城の方へ目をやった。
すると何と、あの将軍が武士を率い、流麗や殺生丸の目を盗んで城へ乗り込んでいる。
「お婆様!」
最早その場の武士は眼中になく、殺生丸も残したまま、流麗は疾(と)く城へ走った。
最上階にある祖母の部屋へ疾走する途中、母の叫び声が聞こえた。
それと同時に、濃い血の臭いも捉える。
遂に祖母の部屋に辿りつくと、そこには、肩から腕にかけて深い斬り傷を負った母と、
既に将軍の長刀によって殺された祖母の姿があった。
その光景を見ると言葉が出ず、だがその瞬間、流麗の形相が一変した。
あの透き通るような黒い瞳が青紫に、その周りが燃え盛る炎のような紅蓮の如く真赤に変色した。
頬に浮かぶ弧状の線が歪に変形し、また口から、上側の鋭い牙が剥き出しとなった。
利き手に持つ柄が、ミシミシとなく。
ついに怒りが頂点を達した。
「おのれ……貴様!!!」
速く武士の元へ駆けると、本性を露にした流麗は荒く剣を振り、武士を斬り殺していく。
流麗に対し、武士は反撃しようとするが、あまりの速い動きに逆に虐殺される。
粗方武士を殺すと、流麗が次に目をつけたのは、祖母を殺し、母に重傷を負わせた将軍。
「将軍!」
両手で剣を持ち、猛々しい大声をあげながら将軍の傍へ駆け、また剣を振るった。
だが流麗の剣の技を、将軍は長刀で一つ一つ確実に受け止め、素早くその刀を流麗に目掛け振るい落とした。
流麗は宙を返り、将軍から離れた。
将軍はギロリと流麗を見ると、言った。
「来い!醜い妖怪!!!」
流麗は剣を放り投げた。
爪で止めを刺すつもりだ。
「――流麗、いけません!」
荒れ狂う我が娘に、葦が声をあげたが、母の声は流麗の耳には聞こえていない。
変化の際に何十寸も鋭く伸びた爪を将軍に向け、大きく一歩を踏み出した。
「死ねえ―――!!!」
勢いをつけ、そして爪を振るった。
同時に将軍も刀の刃を真っ直ぐ突きのばす。
その時、流麗と将軍の間合いに清牙王が入り込んだ。
突然のことに、流麗の爪はそのまま清牙王の硬い鎧を砕き、身をも引き裂いてしまった。
「双方とも動くな!!!」
清牙王は将軍の喉元に剣の刃を突きつけ、声を上げる。
「一寸たりとも動くな。動けば、この喉に風穴があく」
前を将軍に、背後を流麗にして、清牙王は将軍に言う。
「人間風情がここまで来た事は褒めてやろう。
だが身に覚えのない怨みに、我が母を殺し、更には妻を傷つけるとは如何なる料簡か?」
「――――」
「戦を仕掛けるには、必ずや何かの訳があるはず。答えよ」
清牙王の言葉に、将軍が突如不気味な笑い声をあげた。
その不気味な嗤(わら)いをあげれば、口の中の黄色い歯が見える。
笑いを止め、だが顔をにやつかせ、将軍は清牙王に答えた。
「妖怪など、恐るるに足らぬ」
「――何……?」
「世を牛耳る妖を撲滅する為、我らは地方へ行っては、妖怪退治を施してきた。
だが今回、その女妖怪がこれほど強力とは不覚だったな」
「こやつは血肉を分け与えた我が娘だ。先祖代々、大妖怪の血を継いでいる。
これは全て貴様の企て。決して娘を怨むな」
「その目つき……如何にも我を殺したいような」
「――――」
「ならば望みを叶えてしんぜよう。さあ、その剣で我の喉を突いてみよ。
母や妻の仇に。憐れな愛娘の変わりに――」
一つも恐れ戦く様子もなく、清牙王に挑発する。
その原因で、次第に清牙王の妖気が部屋に充満する。
「あなた……己を保って」
憤る清牙王に、葦はせめて言葉で、清牙王の気を落ち着かせる。
清牙王の背後に立つ流麗は、漸く正気に戻った。
ふと己の着物や利き手など見ると、武士を殺した際に飛び散った血がべっとりと染み付き、
渾身の力で剣を放り投げ際に、銀(しろがね)の刃が深く壁に突き立っているが、その刃も柄も、真赤に汚れている。
それよりも父が羽織る真っ白な毛皮が、徐々に紅く染まっていく。
目前の光景がとてもおぞましく、遂に流麗は意識を失った。
倒れる娘に、清牙王は咄嗟に娘の細身を抱え、その時、将軍の喉に突きつける剣を引いてしまった。
剣を引いたと同時に、将軍や武士が一斉に動いた。
「動くな!殺すぞ!!!」
清牙王の長剣の刃が再び将軍に向けられる。
その場に漸く闘牙王と、氷雪と殺生丸がやって来た。
「お母様……」
夥しい血に汚れた部屋や、何よりとても信頼していた義母の無惨な姿に、氷雪は完全に言葉を失う。
闘牙王は清牙王の横に立った。
「清牙王、後は俺がしよう。早く、葦と流麗を連れ出せ」
清牙王は流麗を抱え、葦と部屋を出ようとした。
だが立ち上がった葦は闘牙王の背後に立ち、闘牙王に言った。
「お兄様、その者達は所詮は人間です。どうかお兄様の慈悲のお心で、お命だけは……」
闘牙王は答えない。
やがて清牙王に連れられ、部屋を後にした。
その後、氷雪は闘牙王と並び、当の闘牙王は背に下げる魔剣を抜いた。
これから将軍や、数えるほどの武士達に対し為す両親を、殺生丸は扉の横でじっと眺めていた。
二日後の朝、殺生丸が目を覚ますと、また流麗がいない。
一体、どこへ行ったのか。
城中を探してもいないし、家来達に訊ねても口を合わせて知らぬという。
終いには、大広間にいる両親や叔父夫婦に訊ねることにした。
「まあ、殺生丸。起きましたか」
「――姉上はどこです」
殺生丸が流麗の事を言うと、やはり皆は口を閉ざた。それでも殺生丸は、尚も迫る。
「あの日以来、姉上は上の空。一言も告げず、独りでどこか行って、戻っては来ない」
殺生丸が心の奥底から流麗を案じ、そんな殺生丸についに清牙王が言った。
「流麗は、東の広野へ、嵩明良といる」
そういえば嵩明良の姿も見えないと思っていたが、まさか流麗といるとは。
東の広野といえば、先日流麗と勝負し、遊んだ所。
そう聞くと、殺生丸は両親達に背を向けた。
「待て」
殺生丸が扉に手をかけ、開けようとした時、父の闘牙王が言った。
「旦那様……」
「殺生丸、流麗の所へは行くな」
「――なぜです」
「理由は訊くな。暫しの間は、流麗とは関ってはならん」
一方の流麗は、広野と嵩明良といた。
嵩明良は嘗ては出雲国を治める王の息子だった。
嘗て嵩明良には姉と兄がいたが、王なる父はあえて嵩明良に王座を委ねる為、ある一族の姫・如月と許婚とした。
時が流れ、近々如月姫と祝言を挙げ、王座を継ぐはずだったが、
ある敵との乱闘の末に一族と如月姫を失ってしまった。
死に物狂いで如月姫を守ろうとした証が、左の頬に残る刀傷の跡だ。
以後、嵩明良は一人で故郷を治めていたが、それからある長月の季節に、西国の流麗姫と出会った。
流麗と共にあらゆる苦難を乗り越え、今は故郷を治めつつ、流麗の一族と行動を共にしている。
半月程前から故郷の出雲に異変が起こり、ずっと帰省していたが、つい昨夜に戻った。
流麗は竜笛を、嵩明良は得意とする楽琵琶を布に包み、
背負(しょ)って、未だ雪が残っているこの広野にやって来た。
「お婆様の事は、とても残念だ」
嵩明良が言った。
数分の沈黙の後、流麗は漸く答えた。
「私の力か、お館様が天生牙を用いれば、お婆様は再び息を吹き返したのに……。
お館様と父様は、迷わずお婆様を葬られた」
まるで冷静な流麗に、嵩明良の目には流麗の背後しか見えない。
泣いているのか、怒りに満ちているのか、それとも、放心しているのか。
流麗が今どんな顔でこう言っているのか、予想は出来ない。
突如流麗が、嵩明良の胸に飛び込んだ。
泣いていた。
涙を溢し、嵩明良の着物を強く握る。その流麗に、嵩明良はそっと優しく流麗の体を包み込んだ。
「嵩明良……私は自分が怖い。目前の憎しみや哀しみに、簡単に心を狩られてしまう。
無駄に人を傷つけたり、殺したくないのに」
「――――」
“流麗姫はよく心に響く管を聴かせてくれる。まるで如月姫と同じ、善き優しき姫君よ”
この娘に対して、出雲国のある者が、嵩明良にそう言えば、
“流麗の男姫は、殺戮に度が過ぎる。関り持たぬ方が、そちの身の為ぞ”
と、言う者もいる。
確かに流麗が剣を持って敵と闘う姿は、言葉では言い難い。
だがそれは、敵から戦を仕掛け、流麗には守るべき者がある故に、その敵と闘い、倒す。
流麗自らが闘いを挑むことは全く無い。
嵩明良がこの娘に惚れたのは、闘う姿ではない。
生きとし生ける者、どんな者も心から愛する、その優しいその心に惚れたのだ。
「流麗は、何も間違ったことはしていない。もう泣くな」
「――――」
「ならば流麗、吾も是非、お婆様の為に弔いの楽を贈ろう。
弔いだけではないぞ、お前のその憎しみや哀しみも解き放ちたい。いつまでもそんな顔は、見たくはない」
「――――」
「流麗、楽を――」
やがて流麗は懐に挿す竜笛を手に持ち、嵩明良は布に包んで背負う楽琵琶を取り出し、雪の上に座した。
嫋(じょう)……
嫋(じょう)……
嵩明良が楽琵琶を奏でると、流麗はそれに合わせて笛を吹き始めた。
絶妙に合う楽琵琶と竜笛の管絃の音色は、陽が西に落ちるまでずっと続いた。
この時奏でた曲は、流麗が得意とする、夢幻泡影(むげんほうよう)という曲だった。
――九月十五日の未の刻。
流麗は寝息を立て、ぐっすりと眠っている。
だが数時間した頃にどこから大勢の笑い声が聞こえ、ふと目を覚ました。
起き上がり、寝衣のままその声のする所へ向った。
濡れ縁で、馴染みのある仲間達が酒を酌みあい、早い宴を楽しんでいる。
「おう、お目覚めか。女王陛下」
一人が流麗に気づくと、一斉に流麗の方を向く。
その宴の中には、あの豹猫族の冬嵐の姿もあった。
冬嵐とも長い付き合いだ。
子供の頃は殺し合う程の激闘は常だったが、
いつぞやか冬嵐姉弟と犬夜叉、殺生丸が起こした戦の末、冬嵐達はあの兄弟共に流麗への敵意は失った。
今では仲間と共に、ここに来ることが日課である。
「そなた達、いつ来られた?」
「つい先ほどよ」
「我らが来た頃はそちはもう夢の中。起こすのも哀れかと、勝手に上がらせてもらった」
「そう……。いや、構わぬ」
「流麗、いつまでもそんな姿せず、服を着替えて我々と酒(ささ)を頂こうぞ」
「待て、斉資(なりすけ)。一人では、難儀なところもあろう。冬嵐、流麗に手を貸してやれ」
斉資といえば、過去に折れた剣のつなぎにする為、流麗の牙を抜いたり、
銀竜との闘いに斬られた流麗の腹の傷を治療した薬師だ。
その薬師と同年の男が言い、流麗は冬嵐と部屋へ戻り、服を着替え、再び仲間の元へ戻って盃を手にした。
それぞれ瓶子(へいし)を持って、横と酒を酌み合い、
「では」
「うむ」
声を掛け合って、一斉に酒を喉の中に流し込んだ。
酒のアテも欠かせない。
仲間の一人が持ってきた鰯(いわし)と松茸を炭で焼き、平等に皿に盛り、それぞれ前に箸と置いた。
皿の縁(ふち)には、鰯と松茸と一緒に焼いた味噌も添えられている。
松茸につけて食べると、味は更に旨さを増す。
庭には大池や、敷石が敷かれ、秋の花が咲き誇っている。
その花の香りと、流麗の狩衣の垂領(たりくび)と、指貫袴に薫き込んでいる薫衣香(くのえこう)の香が混ざり、
その場は仄かな甘い匂いが漂っている。
「あのようなことが起こらねば、今頃はお館兄弟や、お前の夫(つま)と酒を頂いているとゆうに」
「今よりも過去が恋しいというのは、一体何の縁(えにし)かな」
しみじみと言う仲間に、流麗は七色に輝く酒をじっと眺め、仲間達に答えた。
「それも神が万人に平等に与えた運命の一つ。誰も永久(とわ)なる命は、人も妖も持ち合わせてあるまい」
「――――」
「過ぎたる過去は幻よ」
「ほお、幻とな……」
「先日文月の頃に、犬夜叉に逢いに行った時、犬夜叉はそう言った。
あの子はいち早く人の心を察する優しく、素直な子だ。が……一つ、そうにはゆかぬものがある」
「――唐の銀竜ことか」
仲間がそういうと流麗は頷いた。更に流麗が言う。
「闘いの始まりはお爺様の代からで、今年で五百年だ。この因縁だけは、何としても断ち切らねばならない」
そう言う流麗に皆は言葉を詰まらす。
決意の固い流麗に、一人の男が真剣な表情で言った。
「流麗よ。我らはそなたが赤子の頃から知っている。
一族の為に全てを賭する事は、やはり気が進まぬのだ。
数百年も年月が経っているのだ、もう仇討ちなど、よいではないか」
「この男の言うとおりぞ」
仲間は一斉に首を上下に振る。
だが当人だけは、首を左右に振り、そして答えた。
「あの男が唐へ戻ったは、私を倒す為に剣の研鑽を積んでいるからだ。銀竜との決着は必ず果す」
「――流麗は諦めの悪い、犬夜叉と殺生丸の従姉(あね)です」
冬嵐が言った。
「近々は天下泰平も成そうとしている。流麗はこれまで何一つ物事を諦めず、成し遂げたのです。
銀竜との決着も必ず流麗が勝つ。我々は今までどおり、流麗を心から見守りましょうぞ」
冬嵐の発言に、他者は黙り込んだが、悔やみながらも冬嵐の言葉に従った。
「LOVER 【夢 幻 泡 影】 弐」 優サマ
今日は仲間達は夜遅くまでいるらしい。
いつも感じるあの淋しさは、今日は感じることはない。
「部屋へ戻る」
宴の最中、流麗は一族の為に弔いの笛を届けようと、笛を取りに部屋へ戻った。
障子を開け、痛んだ棚から木箱を取り出す。
更に木箱の蓋を取って竜笛を手にしたその瞬間、どこぞから凄まじき殺気を感じた。
そう思った時、外から途轍もなく強い力によって、分厚い壁が木端微塵に破壊した。
壁諸共、文机(ふづくえ)や、その他の戸棚も灰塵と化す。
間一髪、流麗はその被害を避け、大事な笛も傷一つ付かずに無事にすんだ。
濛濛と立ち込める塵や埃の中から、二人の人影が見えた。
やがて埃がおさまり、その者の姿をよく見ることが出来た。
他方は翡緑色の素朴な模様が飾る衣装を纏い、もう他方は無地で、紅蓮の如く紅い衣装を無造作に着ていた。
正しく、葉蘭と紫蘭だ。
「流麗、決着です」
葉蘭が言った。
「決着……?」
「主が唐よりお戻りになられたのです。あの時果たす事の出来なかった決着を、今度こそと」
「まさか、今ここでしようと……」
「早まるな」
葉蘭に代わって紫蘭が言った。
「旦那様は今、武蔵にいる。決着は、武蔵でするようだ」
「――――」
「武蔵へ来い、流麗。殺生丸、犬夜叉共に、五百年間の恨みを返してくれる」
「――流麗!」
心臓に響くような爆発音に、その場に仲間達が駆けてきた。
仲間達がやって来た頃には既に、葉蘭と紫蘭の姿はなく、流麗は立ちすくんでいた。
「流麗、今の音は何ぞ!?」
「一体何があったのです!?」
流麗は答えず、ついに鎧と三本の剣を身につけ、利き手に持つ竜笛を着物と鎧の間に挿した。
鹿皮の沓靴(かのくつ)を履くと、外へ出る扉へ向う。
何も分からぬ仲間達は、流麗の後につく。
「流麗、一体あれは何だ!?」
「どこへ行かれるというのです!」
「――――」
「黙っていては分からぬ!流麗、答えよ!」
斉資がついに声をあげた。
流麗は足を止め、漸く答えた。
「銀竜が日本に戻ったようだ」
「――何と、銀竜が!?」
「あの男は今は、武蔵にいると……」
「武蔵へ行くか、流麗」
「西国はどうなさるおつもり?」
流麗は冬嵐の顔を見た。
「私が戻るまで、お前に任そう」
冬嵐にそう頼むと、流麗はついに、外へ出て行った。
まだ、太陽が高い。
流麗は真の姿へ変化し、何里も響く大唸り声をあげると、武蔵へ走った。
同時刻の武蔵は、生憎の雨だった。
針より太く、絹より柔らかいこの雨の中では犬夜叉達も先には進めず、
偶然見つけた荒家(あばらや)で雨宿りをする。
雨がやむまでそこで体力を温存しようと、いっぱい寛いでいる。
カップラーメンや、甘味のお菓子をそれぞれ分け合って食べ、
いつものように犬夜叉が力ずくで七宝から食べ物を奪うと、七宝は泣く。
かごめが注意をした所で犬夜叉は無視をする。そこでかごめは犬夜叉に“おすわり”を数十発見舞った。
どさくさに紛れて、弥勒が珊瑚の尻を触った。
当然のように珊瑚は渾身の力で、弥勒の頬を叩く。
相変わらず賑やかなこの一行は、やがて仮眠をとることとなった。
かごめと珊瑚と七宝は横に、寄り添って眠り、犬夜叉や弥勒も壁に背を預け、軽く目を閉じる。
だが外からの絶妙な雨の音が深い眠りへと導く。
やがて仮眠のつもりが熟睡にしてしまった。
数時間した頃、犬夜叉の鼻は妙な匂いを捕らえた。
目が覚めた犬夜叉は鉄砕牙を腰に挿し、未だ眠る仲間を起こさず、そっと戸をあけて外に出た。
まだ雨が降っている。
鼻と耳を活かし、辺りの気配を探り、
やがてある一点を見つめると前方より人がこちらに向って歩いて来ている。
やがてその人は、犬夜叉と八歩の距離で立ち止まった。
男だ。それも華人のようである。よく見ると、妖怪とも分かった。
その風体が、如何にも不気味なのだ。左目の周囲だけ、妙な模様が描かれている。
藍や青の生地に、鮮やかな模様が飾った衣と袴をふうわりと身に纏い、利き手には長剣を持っていた。
「久方ぶりに見るその姿……変わらぬな、犬夜叉」
低い声で、男はそういった。
「――何故俺を知っている。てめぇ、一体何者だ」
そう言う犬夜叉に男が少々首を傾けた。
「この銀竜をお忘れか?」
「銀竜……?」
「あの炎の中で、流麗に命を救われた事や、母の死も……もうお忘れか」
――突如、犬夜叉の脳裏にあの事が鮮明に蘇った。
とても恐ろしいあの出来事に、犬夜叉の表情が憎悪へ変わり、その場に怒りを散らした。
「てめぇ、あの時の野郎か!」
怒りする犬夜叉を見て銀竜はにやりと笑みを浮かべる。
「何がおかしい!てめぇのせいで、どれだけお袋は苦しい思いをしたと思ってやがる!」
ついに腰に挿す鞘より、鉄砕牙を抜いた。
鋭く大きな鉄砕牙の刃は真っ直ぐ、銀竜に向けられる。
「お袋の仇、今ここで討ってやる!!!」
外の騒ぎにやがて、かごめ、七宝、弥勒、珊瑚が目を覚ました。
少し寝ぼけながら何事かと思い、戸をあけて外を眺めるや、犬夜叉が見知らぬ妖怪と激しく剣を交えている。
見るからに犬夜叉はこの男妖怪に苦戦している模様だ。
眠気は一気に覚め、犬夜叉に加勢しようと、それぞれ武器を持った。
「犬夜叉!」
かごめは弓矢を、弥勒は数枚の破魔札、珊瑚が飛来骨を振るい投げようとしたとき、
「手を出すな!」
犬夜叉が叫んだ。
かごめ達はぴたりと止まり、犬夜叉は仲間の方を向いた。
「こいつは俺に用があるんだ!関係ねぇお前らは手を出すんじゃねぇ!!!」
犬夜叉の視線は再び銀竜に向けられた。
「銀竜、ここじゃ闘えねぇ!俺に着いて来い!」
そう犬夜叉が言うと、そのまま竹林の中へと姿を消した。
また、にやりと笑みを浮かべると、銀竜は犬夜叉の後を追った。
――かごめ達は荒家の中で、ずっと犬夜叉の帰りを待つ。
あれから二時間は経ち、雨もすっかり止んだ。
だが犬夜叉が帰ってくる気配は、全くない。
「犬夜叉……大丈夫かのう」
「――――」
「やはりあの時、加勢してやればよかったのではないか」
七宝がとても犬夜叉を案じる。
時に、他の三人の脳裏に恐ろしい事が過る。
「犬夜叉よ。今までどんな敵も倒して、勝ってきたんだから。負けるなんてことないわ」
かごめが言った。
かごめのその言(こと)に、弥勒も珊瑚もそうだろうと強く確信した。
「かごめちゃんの言うとおりだよね。もうすぐ帰ってくるはずだよ」
「もう暫く、あの男の帰りを待ちましょう」
早くも西国から流麗がやって来た。
見知らぬ土地に、薄暗い竹林の中を歩くが、先程まで降っていた雨のせいで足場が悪い。
袴や左肩から垂らす白い毛皮は水を含んでずっしりと重く、また沓の中にも次第に泥水が染み込む。
足場の悪い道を歩き続けると、前方より倒れる人を見つめた。
生きているのか死んでいるのか、その傍に近づき、泥だらけの顔を覗き込んだら、何と犬夜叉だ。
所々破けた衣の隙間からは、生々しい斬り傷が見える。
その傷は、己の腹部に残る傷跡と瓜二つ。
一目で、この犬夜叉は銀竜と闘ったと分かった。
流麗は犬夜叉の口と鼻をそっと軽く押さえた。
まだ息がある。一刻も早く安全な所へ連れ、傷を治さねば。
そう思った時、どこぞからガサリという物音が聞こえた。
その音に、流麗に緊張が走った。腰から牙の剣を抜き、その身で犬夜叉の身を覆い隠して守る。
ある気配を感じ取り、流麗は背後を振り向き、刃を向けた。
目前の光景を見ると、三十人程の老若男女が、こちらを向き、立っていた。
体格から老若男女と分かる。
更に、いつの間にかそれ以上の集団に、周囲を囲まれている。
無造作に竹で編んだ笠を深く被り、少々俯いて、どの者も口元しか見えないが、どうやら純粋な人間らしい。
男も女も似たような衣装を纏い、武器に関しては、一人だけ銀槍を持ち、その他の男女は刀を持っている。
それに加えその銀槍を持った者を含め、全て、両腰に小刀を納める刀嚢(とうのう)を下げていた。
「誰だ」
流麗は訊ねるが、誰も答えない。
「そこの女」
集団の中に交えて、流麗は、長い銀槍を持った女に視線を送った。
「頭目か?」
「――そのように……」
「顔をみせよ」
「――刃を持っている時の頭目は、簡単に全貌を現さない」
流麗は剣を鞘に納めようとしない。
鋭い眼差しで見つめる流麗に対して、頭目の右に立つ男が、流麗に言った。
「我らが目的は、戦ではない。剣を納められよ」
この集団からは殺気は感じない。警戒心は鎮まる事はないが、流麗はやがて剣を鞘へ納めた。
頭目は荒網の笠の隙間から、流麗が柄から手を離すのを確かめると、言った。
「私の名は璋小竹(しょう・ささ)。我ら一同の生業は、悪人を捕らえ、処刑し、非力の人を救うこと」
「悪人とは、妖怪なども含められているのか」
「はい」
「――その目に映る我が姿は、見ての通りの妖怪。長年生きるこの身には、多くの罪も犯した。
さてはこれを機に我を捕らえ、殺す気か?」
そう言う流麗に、紅い紅をさした女の唇が上に吊上がった。
「地元や地方からの頼みにより、我々は悪人を捕獲する。それ以外は近場を巡回し、難儀する者を救う。
それが、妖であろうと。故にその手傷を負う者、我ら一同が介抱いたしましょう」
流麗や犬夜叉の背丈を遥かに上回る大柄の男が、未だ気を失う犬夜叉を軽々と負ぶさった。
そして頭目が歩き始めると、他者も大柄の男も皆、その後に続く。
流麗は少々眉間に皺を寄せつつも、一番最後から、その集団の後をついた。
暫く歩いた所で建物がみえた。
この集団達が勤務する詰め所だ。
新築されたばかりなのか、とても新しく、看板には、天楼館、と記されていた。
そのすぐ隣にも建物がある。見れば、胡蝶園、と書いている。
どうも遊女をかかえておいて客を遊興させる家らしい。
その証拠に楽器の音や、若い女(むすめ)達の甲高い笑い声が聞こえる。
――傷ついた妖怪がやって来たというのに、天楼館の者達は全く動じない。
一同は素早く部屋を確保し、地味な格好をした中年の女が布団や水桶、手拭など、その部屋に持ってきた。
「他に御必要な物はございませぬか」
「これだけで結構」
「恐れ入ります。また何か御用がありましたら、何なりとお申し付けくださいませ」
やがて女は深く頭を下げ、部屋を立ち去った。
人気がなくなった頃、剣と鎧を身より外し、そして犬夜叉の傷を、
生まれ持った摩訶不思議な力で癒そうと心を傾けた。
綺麗な笛の音が聴こえる。
覚えのある曲だ。
確か、魂之舞、という名曲だったか。
夢現、笛の調べを聴いていると、とても心が落ち着く。
間もなく犬夜叉は目を覚ました。
ぼうっと前の天上がぼやけ、犬夜叉はゆっくりと首を横に向け、濡れ縁の方を眺めた。
濡れ縁に、女(ひと)がいる。どうもその女が笛を吹いている。
人間でなく、妖怪だとすぐに分かった。
だが慣れぬ目で見ると、妖怪というのもまるで言い難い。
紐で括った白銀の長い髪が蒼い月光に反射し、まるで煌煌(キラキラ)と光を帯びる天女のように、犬夜叉は見えた。
庭の花の香りに混じって漂うこの香りは、薫衣香か――。
その天女が着る衣服から、何とも仄かに甘い香がする。
少しずつ、少しずつ目が慣れると、その女(ひと)の正体が把握できた。
「流麗……」
小さく名を呼ばれた流麗は、口から笛を外し、背後を向いた。
「犬夜叉。やっと気がついたのね」
流麗は立ち上がり、部屋の中へ入って犬夜叉の横に座り、犬夜叉もゆっくりと起き上がり、布団の上に座した。
「どうして、お前がここにいるんだ?」
「銀竜が武蔵にいると聞いて来たのよ。竹林を歩いていたら、お前が倒れているのを見つけたの」
「――――」
「傷の方も心配いらない。もう大丈夫よ、犬夜叉」
はと思い、犬夜叉は腕や、胸を見た。
銀竜と闘った際のあの傷は、膿んでいる様子も無く、むしろ跡もなく綺麗に消えている。
「流麗が、この傷を……?」
流麗は静かに頷く。
流麗が生まれ持った摩訶不思議な力は知っていたが、これほどの威力とは思わなかった。
よく身の回りを見ると、全く見知らぬものばかり。
辺りを眺めながら犬夜叉は居場所を訊ねた。
「ここはどこだ?」
「天楼館という、人間の詰め所。悪人や、魑魅魍魎を捕獲し処刑する所とか。
けれどそれは、ここよりもう少し離れた所で、この館(たち)は、主に人間達の各部屋があるらしい」
「――お話の最中、失礼申し上げます」
部屋の前に一人の若い男がやってきた。
開けっ放しにされた障子の向こうで、手と膝を床につけ頭を下げ、再びあげると二人に告げた。
「御膳の用意が出来ましたので、是非、お越しください」
犬夜叉は流麗と広間にやって来た。
大きな広間だ。
広間の隅々に、あらゆる秋の花が飾られ、花の香りが満ちている。
どうやら、男と女はそれぞれ分かれて座るらしい。
その間隔は、約十メートル。
何故大幅をあけて座るかは、後々分かる。
暫くすると女達が膳を運んできた。
誰も区別はなく、みんな同じものだ。箸が置かれたら、早速膳を頂く。
間もなく、その広間に楽士と踊り子達が入ってきた。
天楼館と並ぶ、胡蝶園の楽士と踊り子達だ。
笛や和琴。
鮮やかに模様が描かれた大小の鼓や、その他異国より伝来した楽器まで、そこに並べられた。
楽士、踊り子を合わせ、七割方が華人だ。
その幾人の華人の踊り子の内、一人の舞姫が、広間の中央に立った。
一同の視線が、その舞姫にむけられる。
この舞姫も華人。黒髪に似合わず、灰色の目をしている。
舞姫の身を包む衣は、如何にも派手で、色っぽい。
深い谷間が見え、袖や裾が床を這う。
濃い化粧を全面にして、首や耳には、今で言うネックレスや、ピアスをつけ、頭には王冠ものせている。
とても妖艶な舞姫だ。
それよりも流麗は、この華人を一目見ると、何か気になったことがあり、右側に座る若い女に訊ねた。
「あの華人は?」
「――璋小竹(チャン・シャオツュー)ですよ」
「チャン……?」
「日本読みで、“しょう・ささ”、とのそうで」
話が聞こえていたのか、流麗の左に座る女が言った。
「本業は天楼館の頭目ながら、遊び半分だったのか時折やって来る踊り子を真似、
以来、踊り子と踊りをするように。ですが幼少から舞踊の経験があったらしく、頭目の踊りは格別です」
「私の従弟(おとうと)が、あれに救われた。竹林の中対面した時、銀槍と腰に刀嚢を携えていたが、
さぞや剣術に優れているのだろうな」
「はい。何より頭目の必殺剣を習ってから、一同は、以前より更に力を上げました。全て、頭目のお蔭です」
小竹は、何と視線の先を流麗に向け、こう言った。
「お客人様。一つ、お願い事があります」
「――――」
「先ほど、わたくしの部屋に見事な竜笛の調べが聴こえて参りました。
もしや常に持ち歩く、あなたの笛でないかと思いつつ……」
「――――」
「もしもよろしければ、この場でその竜笛を奏でてはくれませんか」
部下や楽士や踊り子や前の犬夜叉も皆、流麗の方を眺める。
流麗は着物の間に挿す竜笛を取り出すと、微笑み、答えた。
「この笛は亡き母の形見。生前の頃は、これを用いて鬼神を泣かすほどの曲や、
死者を悼む曲を作り奏でていました。
わたくしは母に敵わぬ、まだ未熟者ですが、わたくしの笛でよければ、是非とも」
「――大いに感謝いたします」
片膝を床につけ、小竹は深く頭を下げた。
「ただその前に、あなたの楽舞を目にしてから――」
「それならば、とっておきの舞を一つ、お見せしましょう」
楽士は一回、二回、三回、四回鈴を鳴らし、続いて大鼓、琵琶、三味線、二胡、二十絃筝、笙、能管、尺八。
その他異国から伝来した様々な楽器を楽士は奏でた。
速く、あらゆる管絃、鼓が合い、小竹はその楽にのって如何にも激しい動きをみせる。
そして楽器が一斉にやむと、小竹もぴたりとその動きも止まった。
その度にその場の一同が、手を叩き、“見事”だの、“お上手”だのと叫ぶ。
流麗もその舞に感心した。
暫くその舞を見ると、流麗は楽士達の中に立ち、笛に息を吹き込んだ。
その笛に、他の楽器は止み、一人だけ琵琶楽士が合わした。
流麗が奏でるは得意の一曲・夢幻泡影。
笛と琵琶の音に、小竹は器用に乱舞から歌舞へ切り替えた。
――我的故郷是近遠的唐国
(私の故郷は近くて遠い唐の国)
故郷和一族戦斗都滅亡、天涯孤独的我家没有
(故郷も家族も戦に滅び、天涯孤独の私に家は無し)
一顧人背叛、再顧傾人国
(一目は人に裏切られ、二目は国も傾ける)
一辺感到人世虚幻、尽管如此我活下去
(一方で人の世の儚さを感じて、ひたすら生きていかねばならない)
戦、踊的事、我的命運
(戦い、踊る事が、私のさだめ)
小竹が何と歌っているか、一同には全く分からない。
だが聞き取れなくとも構わない。かえって、とてもいい眺めだ。
静かな曲故に、小竹の踊りはまるで足音も聞こえない。
宴は、遅くまで続いた。
いつも感じるあの淋しさは、今日は感じることはない。
「部屋へ戻る」
宴の最中、流麗は一族の為に弔いの笛を届けようと、笛を取りに部屋へ戻った。
障子を開け、痛んだ棚から木箱を取り出す。
更に木箱の蓋を取って竜笛を手にしたその瞬間、どこぞから凄まじき殺気を感じた。
そう思った時、外から途轍もなく強い力によって、分厚い壁が木端微塵に破壊した。
壁諸共、文机(ふづくえ)や、その他の戸棚も灰塵と化す。
間一髪、流麗はその被害を避け、大事な笛も傷一つ付かずに無事にすんだ。
濛濛と立ち込める塵や埃の中から、二人の人影が見えた。
やがて埃がおさまり、その者の姿をよく見ることが出来た。
他方は翡緑色の素朴な模様が飾る衣装を纏い、もう他方は無地で、紅蓮の如く紅い衣装を無造作に着ていた。
正しく、葉蘭と紫蘭だ。
「流麗、決着です」
葉蘭が言った。
「決着……?」
「主が唐よりお戻りになられたのです。あの時果たす事の出来なかった決着を、今度こそと」
「まさか、今ここでしようと……」
「早まるな」
葉蘭に代わって紫蘭が言った。
「旦那様は今、武蔵にいる。決着は、武蔵でするようだ」
「――――」
「武蔵へ来い、流麗。殺生丸、犬夜叉共に、五百年間の恨みを返してくれる」
「――流麗!」
心臓に響くような爆発音に、その場に仲間達が駆けてきた。
仲間達がやって来た頃には既に、葉蘭と紫蘭の姿はなく、流麗は立ちすくんでいた。
「流麗、今の音は何ぞ!?」
「一体何があったのです!?」
流麗は答えず、ついに鎧と三本の剣を身につけ、利き手に持つ竜笛を着物と鎧の間に挿した。
鹿皮の沓靴(かのくつ)を履くと、外へ出る扉へ向う。
何も分からぬ仲間達は、流麗の後につく。
「流麗、一体あれは何だ!?」
「どこへ行かれるというのです!」
「――――」
「黙っていては分からぬ!流麗、答えよ!」
斉資がついに声をあげた。
流麗は足を止め、漸く答えた。
「銀竜が日本に戻ったようだ」
「――何と、銀竜が!?」
「あの男は今は、武蔵にいると……」
「武蔵へ行くか、流麗」
「西国はどうなさるおつもり?」
流麗は冬嵐の顔を見た。
「私が戻るまで、お前に任そう」
冬嵐にそう頼むと、流麗はついに、外へ出て行った。
まだ、太陽が高い。
流麗は真の姿へ変化し、何里も響く大唸り声をあげると、武蔵へ走った。
同時刻の武蔵は、生憎の雨だった。
針より太く、絹より柔らかいこの雨の中では犬夜叉達も先には進めず、
偶然見つけた荒家(あばらや)で雨宿りをする。
雨がやむまでそこで体力を温存しようと、いっぱい寛いでいる。
カップラーメンや、甘味のお菓子をそれぞれ分け合って食べ、
いつものように犬夜叉が力ずくで七宝から食べ物を奪うと、七宝は泣く。
かごめが注意をした所で犬夜叉は無視をする。そこでかごめは犬夜叉に“おすわり”を数十発見舞った。
どさくさに紛れて、弥勒が珊瑚の尻を触った。
当然のように珊瑚は渾身の力で、弥勒の頬を叩く。
相変わらず賑やかなこの一行は、やがて仮眠をとることとなった。
かごめと珊瑚と七宝は横に、寄り添って眠り、犬夜叉や弥勒も壁に背を預け、軽く目を閉じる。
だが外からの絶妙な雨の音が深い眠りへと導く。
やがて仮眠のつもりが熟睡にしてしまった。
数時間した頃、犬夜叉の鼻は妙な匂いを捕らえた。
目が覚めた犬夜叉は鉄砕牙を腰に挿し、未だ眠る仲間を起こさず、そっと戸をあけて外に出た。
まだ雨が降っている。
鼻と耳を活かし、辺りの気配を探り、
やがてある一点を見つめると前方より人がこちらに向って歩いて来ている。
やがてその人は、犬夜叉と八歩の距離で立ち止まった。
男だ。それも華人のようである。よく見ると、妖怪とも分かった。
その風体が、如何にも不気味なのだ。左目の周囲だけ、妙な模様が描かれている。
藍や青の生地に、鮮やかな模様が飾った衣と袴をふうわりと身に纏い、利き手には長剣を持っていた。
「久方ぶりに見るその姿……変わらぬな、犬夜叉」
低い声で、男はそういった。
「――何故俺を知っている。てめぇ、一体何者だ」
そう言う犬夜叉に男が少々首を傾けた。
「この銀竜をお忘れか?」
「銀竜……?」
「あの炎の中で、流麗に命を救われた事や、母の死も……もうお忘れか」
――突如、犬夜叉の脳裏にあの事が鮮明に蘇った。
とても恐ろしいあの出来事に、犬夜叉の表情が憎悪へ変わり、その場に怒りを散らした。
「てめぇ、あの時の野郎か!」
怒りする犬夜叉を見て銀竜はにやりと笑みを浮かべる。
「何がおかしい!てめぇのせいで、どれだけお袋は苦しい思いをしたと思ってやがる!」
ついに腰に挿す鞘より、鉄砕牙を抜いた。
鋭く大きな鉄砕牙の刃は真っ直ぐ、銀竜に向けられる。
「お袋の仇、今ここで討ってやる!!!」
外の騒ぎにやがて、かごめ、七宝、弥勒、珊瑚が目を覚ました。
少し寝ぼけながら何事かと思い、戸をあけて外を眺めるや、犬夜叉が見知らぬ妖怪と激しく剣を交えている。
見るからに犬夜叉はこの男妖怪に苦戦している模様だ。
眠気は一気に覚め、犬夜叉に加勢しようと、それぞれ武器を持った。
「犬夜叉!」
かごめは弓矢を、弥勒は数枚の破魔札、珊瑚が飛来骨を振るい投げようとしたとき、
「手を出すな!」
犬夜叉が叫んだ。
かごめ達はぴたりと止まり、犬夜叉は仲間の方を向いた。
「こいつは俺に用があるんだ!関係ねぇお前らは手を出すんじゃねぇ!!!」
犬夜叉の視線は再び銀竜に向けられた。
「銀竜、ここじゃ闘えねぇ!俺に着いて来い!」
そう犬夜叉が言うと、そのまま竹林の中へと姿を消した。
また、にやりと笑みを浮かべると、銀竜は犬夜叉の後を追った。
――かごめ達は荒家の中で、ずっと犬夜叉の帰りを待つ。
あれから二時間は経ち、雨もすっかり止んだ。
だが犬夜叉が帰ってくる気配は、全くない。
「犬夜叉……大丈夫かのう」
「――――」
「やはりあの時、加勢してやればよかったのではないか」
七宝がとても犬夜叉を案じる。
時に、他の三人の脳裏に恐ろしい事が過る。
「犬夜叉よ。今までどんな敵も倒して、勝ってきたんだから。負けるなんてことないわ」
かごめが言った。
かごめのその言(こと)に、弥勒も珊瑚もそうだろうと強く確信した。
「かごめちゃんの言うとおりだよね。もうすぐ帰ってくるはずだよ」
「もう暫く、あの男の帰りを待ちましょう」
早くも西国から流麗がやって来た。
見知らぬ土地に、薄暗い竹林の中を歩くが、先程まで降っていた雨のせいで足場が悪い。
袴や左肩から垂らす白い毛皮は水を含んでずっしりと重く、また沓の中にも次第に泥水が染み込む。
足場の悪い道を歩き続けると、前方より倒れる人を見つめた。
生きているのか死んでいるのか、その傍に近づき、泥だらけの顔を覗き込んだら、何と犬夜叉だ。
所々破けた衣の隙間からは、生々しい斬り傷が見える。
その傷は、己の腹部に残る傷跡と瓜二つ。
一目で、この犬夜叉は銀竜と闘ったと分かった。
流麗は犬夜叉の口と鼻をそっと軽く押さえた。
まだ息がある。一刻も早く安全な所へ連れ、傷を治さねば。
そう思った時、どこぞからガサリという物音が聞こえた。
その音に、流麗に緊張が走った。腰から牙の剣を抜き、その身で犬夜叉の身を覆い隠して守る。
ある気配を感じ取り、流麗は背後を振り向き、刃を向けた。
目前の光景を見ると、三十人程の老若男女が、こちらを向き、立っていた。
体格から老若男女と分かる。
更に、いつの間にかそれ以上の集団に、周囲を囲まれている。
無造作に竹で編んだ笠を深く被り、少々俯いて、どの者も口元しか見えないが、どうやら純粋な人間らしい。
男も女も似たような衣装を纏い、武器に関しては、一人だけ銀槍を持ち、その他の男女は刀を持っている。
それに加えその銀槍を持った者を含め、全て、両腰に小刀を納める刀嚢(とうのう)を下げていた。
「誰だ」
流麗は訊ねるが、誰も答えない。
「そこの女」
集団の中に交えて、流麗は、長い銀槍を持った女に視線を送った。
「頭目か?」
「――そのように……」
「顔をみせよ」
「――刃を持っている時の頭目は、簡単に全貌を現さない」
流麗は剣を鞘に納めようとしない。
鋭い眼差しで見つめる流麗に対して、頭目の右に立つ男が、流麗に言った。
「我らが目的は、戦ではない。剣を納められよ」
この集団からは殺気は感じない。警戒心は鎮まる事はないが、流麗はやがて剣を鞘へ納めた。
頭目は荒網の笠の隙間から、流麗が柄から手を離すのを確かめると、言った。
「私の名は璋小竹(しょう・ささ)。我ら一同の生業は、悪人を捕らえ、処刑し、非力の人を救うこと」
「悪人とは、妖怪なども含められているのか」
「はい」
「――その目に映る我が姿は、見ての通りの妖怪。長年生きるこの身には、多くの罪も犯した。
さてはこれを機に我を捕らえ、殺す気か?」
そう言う流麗に、紅い紅をさした女の唇が上に吊上がった。
「地元や地方からの頼みにより、我々は悪人を捕獲する。それ以外は近場を巡回し、難儀する者を救う。
それが、妖であろうと。故にその手傷を負う者、我ら一同が介抱いたしましょう」
流麗や犬夜叉の背丈を遥かに上回る大柄の男が、未だ気を失う犬夜叉を軽々と負ぶさった。
そして頭目が歩き始めると、他者も大柄の男も皆、その後に続く。
流麗は少々眉間に皺を寄せつつも、一番最後から、その集団の後をついた。
暫く歩いた所で建物がみえた。
この集団達が勤務する詰め所だ。
新築されたばかりなのか、とても新しく、看板には、天楼館、と記されていた。
そのすぐ隣にも建物がある。見れば、胡蝶園、と書いている。
どうも遊女をかかえておいて客を遊興させる家らしい。
その証拠に楽器の音や、若い女(むすめ)達の甲高い笑い声が聞こえる。
――傷ついた妖怪がやって来たというのに、天楼館の者達は全く動じない。
一同は素早く部屋を確保し、地味な格好をした中年の女が布団や水桶、手拭など、その部屋に持ってきた。
「他に御必要な物はございませぬか」
「これだけで結構」
「恐れ入ります。また何か御用がありましたら、何なりとお申し付けくださいませ」
やがて女は深く頭を下げ、部屋を立ち去った。
人気がなくなった頃、剣と鎧を身より外し、そして犬夜叉の傷を、
生まれ持った摩訶不思議な力で癒そうと心を傾けた。
綺麗な笛の音が聴こえる。
覚えのある曲だ。
確か、魂之舞、という名曲だったか。
夢現、笛の調べを聴いていると、とても心が落ち着く。
間もなく犬夜叉は目を覚ました。
ぼうっと前の天上がぼやけ、犬夜叉はゆっくりと首を横に向け、濡れ縁の方を眺めた。
濡れ縁に、女(ひと)がいる。どうもその女が笛を吹いている。
人間でなく、妖怪だとすぐに分かった。
だが慣れぬ目で見ると、妖怪というのもまるで言い難い。
紐で括った白銀の長い髪が蒼い月光に反射し、まるで煌煌(キラキラ)と光を帯びる天女のように、犬夜叉は見えた。
庭の花の香りに混じって漂うこの香りは、薫衣香か――。
その天女が着る衣服から、何とも仄かに甘い香がする。
少しずつ、少しずつ目が慣れると、その女(ひと)の正体が把握できた。
「流麗……」
小さく名を呼ばれた流麗は、口から笛を外し、背後を向いた。
「犬夜叉。やっと気がついたのね」
流麗は立ち上がり、部屋の中へ入って犬夜叉の横に座り、犬夜叉もゆっくりと起き上がり、布団の上に座した。
「どうして、お前がここにいるんだ?」
「銀竜が武蔵にいると聞いて来たのよ。竹林を歩いていたら、お前が倒れているのを見つけたの」
「――――」
「傷の方も心配いらない。もう大丈夫よ、犬夜叉」
はと思い、犬夜叉は腕や、胸を見た。
銀竜と闘った際のあの傷は、膿んでいる様子も無く、むしろ跡もなく綺麗に消えている。
「流麗が、この傷を……?」
流麗は静かに頷く。
流麗が生まれ持った摩訶不思議な力は知っていたが、これほどの威力とは思わなかった。
よく身の回りを見ると、全く見知らぬものばかり。
辺りを眺めながら犬夜叉は居場所を訊ねた。
「ここはどこだ?」
「天楼館という、人間の詰め所。悪人や、魑魅魍魎を捕獲し処刑する所とか。
けれどそれは、ここよりもう少し離れた所で、この館(たち)は、主に人間達の各部屋があるらしい」
「――お話の最中、失礼申し上げます」
部屋の前に一人の若い男がやってきた。
開けっ放しにされた障子の向こうで、手と膝を床につけ頭を下げ、再びあげると二人に告げた。
「御膳の用意が出来ましたので、是非、お越しください」
犬夜叉は流麗と広間にやって来た。
大きな広間だ。
広間の隅々に、あらゆる秋の花が飾られ、花の香りが満ちている。
どうやら、男と女はそれぞれ分かれて座るらしい。
その間隔は、約十メートル。
何故大幅をあけて座るかは、後々分かる。
暫くすると女達が膳を運んできた。
誰も区別はなく、みんな同じものだ。箸が置かれたら、早速膳を頂く。
間もなく、その広間に楽士と踊り子達が入ってきた。
天楼館と並ぶ、胡蝶園の楽士と踊り子達だ。
笛や和琴。
鮮やかに模様が描かれた大小の鼓や、その他異国より伝来した楽器まで、そこに並べられた。
楽士、踊り子を合わせ、七割方が華人だ。
その幾人の華人の踊り子の内、一人の舞姫が、広間の中央に立った。
一同の視線が、その舞姫にむけられる。
この舞姫も華人。黒髪に似合わず、灰色の目をしている。
舞姫の身を包む衣は、如何にも派手で、色っぽい。
深い谷間が見え、袖や裾が床を這う。
濃い化粧を全面にして、首や耳には、今で言うネックレスや、ピアスをつけ、頭には王冠ものせている。
とても妖艶な舞姫だ。
それよりも流麗は、この華人を一目見ると、何か気になったことがあり、右側に座る若い女に訊ねた。
「あの華人は?」
「――璋小竹(チャン・シャオツュー)ですよ」
「チャン……?」
「日本読みで、“しょう・ささ”、とのそうで」
話が聞こえていたのか、流麗の左に座る女が言った。
「本業は天楼館の頭目ながら、遊び半分だったのか時折やって来る踊り子を真似、
以来、踊り子と踊りをするように。ですが幼少から舞踊の経験があったらしく、頭目の踊りは格別です」
「私の従弟(おとうと)が、あれに救われた。竹林の中対面した時、銀槍と腰に刀嚢を携えていたが、
さぞや剣術に優れているのだろうな」
「はい。何より頭目の必殺剣を習ってから、一同は、以前より更に力を上げました。全て、頭目のお蔭です」
小竹は、何と視線の先を流麗に向け、こう言った。
「お客人様。一つ、お願い事があります」
「――――」
「先ほど、わたくしの部屋に見事な竜笛の調べが聴こえて参りました。
もしや常に持ち歩く、あなたの笛でないかと思いつつ……」
「――――」
「もしもよろしければ、この場でその竜笛を奏でてはくれませんか」
部下や楽士や踊り子や前の犬夜叉も皆、流麗の方を眺める。
流麗は着物の間に挿す竜笛を取り出すと、微笑み、答えた。
「この笛は亡き母の形見。生前の頃は、これを用いて鬼神を泣かすほどの曲や、
死者を悼む曲を作り奏でていました。
わたくしは母に敵わぬ、まだ未熟者ですが、わたくしの笛でよければ、是非とも」
「――大いに感謝いたします」
片膝を床につけ、小竹は深く頭を下げた。
「ただその前に、あなたの楽舞を目にしてから――」
「それならば、とっておきの舞を一つ、お見せしましょう」
楽士は一回、二回、三回、四回鈴を鳴らし、続いて大鼓、琵琶、三味線、二胡、二十絃筝、笙、能管、尺八。
その他異国から伝来した様々な楽器を楽士は奏でた。
速く、あらゆる管絃、鼓が合い、小竹はその楽にのって如何にも激しい動きをみせる。
そして楽器が一斉にやむと、小竹もぴたりとその動きも止まった。
その度にその場の一同が、手を叩き、“見事”だの、“お上手”だのと叫ぶ。
流麗もその舞に感心した。
暫くその舞を見ると、流麗は楽士達の中に立ち、笛に息を吹き込んだ。
その笛に、他の楽器は止み、一人だけ琵琶楽士が合わした。
流麗が奏でるは得意の一曲・夢幻泡影。
笛と琵琶の音に、小竹は器用に乱舞から歌舞へ切り替えた。
――我的故郷是近遠的唐国
(私の故郷は近くて遠い唐の国)
故郷和一族戦斗都滅亡、天涯孤独的我家没有
(故郷も家族も戦に滅び、天涯孤独の私に家は無し)
一顧人背叛、再顧傾人国
(一目は人に裏切られ、二目は国も傾ける)
一辺感到人世虚幻、尽管如此我活下去
(一方で人の世の儚さを感じて、ひたすら生きていかねばならない)
戦、踊的事、我的命運
(戦い、踊る事が、私のさだめ)
小竹が何と歌っているか、一同には全く分からない。
だが聞き取れなくとも構わない。かえって、とてもいい眺めだ。
静かな曲故に、小竹の踊りはまるで足音も聞こえない。
宴は、遅くまで続いた。
「LOVER 【夢 幻 泡 影】 参」 優サマ
宴は終え、天楼の役人は各部屋に戻り、踊り子も楽士達も遊女屋へ帰った。
夜深更――流麗は部屋へ戻る途中に天楼館に勤める若い女とすれ違った。
その女を呼び止めると、流麗は酒とアテを持ってくるよう頼んだ。
部屋には、二人分の布団が敷かれていた。きっと、今すれ違った女が敷いたのだ。
だが、まだ寝るわけにはいかない。
布団を避け、隅に置かれる円座と脇息を持って流麗は縁に出た。
円座の上に座り、脇息にもたれ寛ぎながら、暫く夜空を眺めていると、
先程の女が瓶子と玉杯と、一品と、もみじの葉を数枚、盆にのせてやって来た。
その盆を流麗が座す右側に丁寧に並べ置いた。
間もなく女は、深く頭を下げると、早々と離れた。
流麗は瓶子を持ち、玉杯の中に酒を注ぐと、たちまち玉杯から清酒の香りが漏れ、夜気に溶けた。
同時に天(そら)からの蒼い月光に反射し、更なる輝きをみせる。
煌煌と光放つ清酒を飲むのは、とても惜しかった。
前の庭は、草に混じって芙蓉、桔梗、菊、紫苑などの秋の花が咲き誇り、
池の横には二本の立派な紅葉の樹がたっている。
どの草も花も、昼間の雨で未だ水滴が乾ききっていない。
みっしりと重さをおびて、闇の中を光っていた。
吾君の心(うら) 愛しき世(とき)は空の果て
我が死期こそは 長月のころ
季節を想っていたら、頭に愛(かな)し愛(かな)しの想い歌が浮かんだ。
想い歌に、流麗は軽い溜息を吐くと、漸く杯の中の酒を喉へと流し込んだ。
――と、重い床の板が軋む重い音が聴こえた。
横を見ると、犬夜叉がこちらに歩いてくる。
「どこにいたの?」
流麗が声をかけると、犬夜叉は立ち止まり、そして答えた。
「外に出て、空気を吸ってきた」
「もう亥の刻を過ぎている。早く休んではどう?」
「そういう姉貴こそ、今日西国から来たんだ。早く休めよ」
ふと流麗は空を見上げた。
「雨雲もなく、月は顔を露にしている。こんな夜を眺めぬとは、とてももったいない」
「――――」
「眠らぬなら、私と宴の続きをしよう」
流麗は立ち上がると、部屋からまた一つ円座を持ってきた。
遠慮なく犬夜叉は円座の上に、無造作に胡坐をかいて座った。
左肘を左膝の上に置き、左腕をたててその手の上に顎のせ、流麗とは何一つ会話を交わさず、前の光景を眺めた。
「なあ、おい……こんな戦ばっかりの世の中も、なかなか捨てたものじゃねぇな」
「この庭は、城の庭とまるで同じ。あそこに季節の花が並び、池の傍には大きな桜の樹がたっている。
土を掘り、石をつめて、川や池を作り、その中に鯉や、亀や蝦蟇を放つ」
「――――」
「闘いがなければ、今も仲間と一緒に月の宴を楽しんでいるはずなのに。だがお前との宴も、また一味違ってよい」
犬夜叉も流麗との宴は悪くはない。
この男が妖怪を慕うのは流麗だけだ。
先程、流麗が詠った歌が犬夜叉は気になる。何のためらいも無く犬夜叉は流麗に歌を訊ねた。
「今の歌は何だ?」
「夫を想う歌よ」
「夫?」
「夫の本名はヨソラ。父親から王座と、“嵩明良”という名跡を継ぎ、やがて出雲の王となった。
とても強くて優しくて、勇敢な男だったよ」
流麗は、更に言う。
「かつて嵩明良には、如月という高麗人の許婚がいたの。けれど敵の謀に王族共に如月を失ったとか。
如月のことは心の奥底にしまって、私と出会い祝言を挙げたけど、
すぐに、お前のお父様と一緒に竜骨精と闘って、若くして死んでしまった」
「――――」
「人と出会い、愛するほど哀しいものはない。出会えば必ず、その人の死に目に立ち会わねばならない」
「人生の中で一番かなしい運命(さだめ)かもしれねぇな」
「けど、人を愛さぬわけにはいかない。誰だって、愛こそは全てだもの」
「――――」
「私が地方へ行くのは闘いを施しに行くだけだった。
それに嵩明良と出会ってからは、よく夜中に私を連れて、あらゆる地方へ連れて行ってくれた。
その時にいつも、嵩明良は私にお前にとって為す事は何かと、よくたずねた」
遠い昔ほど、懐かしい思い出を浮かべると自然と微笑が浮かぶ。
またその時、嵩明良は流麗へ天の月を贈った。それを想うと、今でも感涙してしまう。
「それは、もう決めたのか?」
「あぁ。夫は出雲を治め、一族は代々から西国を治めていた。
なら私は、天下を泰平すること。私も闘って、最期は英雄に……」
犬夜叉は言葉を詰まらせてしまった。
天下泰平という、あまりに大きな夢に、まともな言葉が出なかったのだ。
犬夜叉は軽い息を鼻から吐き、そして流麗に言った。
「流麗は、今までたくさん敵と闘ってきた。その度に、死にかけたこともあるはずだ」
「何を言う?」
「お前と七日過ごした後、俺はずっと一人で生きた。
前に妖怪が現れて、刀や爪を振るう度に、いつもあの時のことを思い出す」
「あの時とは……」
「俺とお袋が、銀竜の手下に殺されそうになった時だ。炎からお前が現れて、俺とお袋を救った」
「――――」
「俺は、お前を頼りにしている。妖怪を相手にこんな思いをするのは、お前だけだ」
「――――」
「天下泰平なんて簡単にできるものじゃないぜ。きっと今まで以上に、多くの危機に陥る。
そんなことよりも、やっぱり今までどおり西国を治めて、平穏に暮らしていってほしい」
「――真の戦士なら、闘いなぞに我が命は惜しくはない。お前のお父様がよい例よ」
やがて玉杯を縁の上に置き、着物の間に挿す竜笛を取り出した。
口に近づけ、息を吹き込むと、得意の一曲、夢幻泡影を奏でた。
大気に溶け込んだ庭の花の香りと流麗が纏う着物からの薫衣香の香りを、
犬夜叉は空気と一緒に吸い込みながら、静かにその曲を聴いた。
更に夜は更ける。
天楼館の門前に二人の男が刀を持ち、左腰に刀嚢を携えて見張りをしていた。
風が吹く度に笹がざわざわと左右に揺れ、とても不気味。
前方から黒い人影が見えた。
「止まられよ」
男の言葉にその者はぴたりと立ち止まり、大松明の灯りでその者の顔をよく見た。
「なんと怪しい風体をする男ぞ」
「おい、名を申せ」
また見張りの男が声をかけると、その者は小さく低く答えた。
「我が名は――劉銀竜(リウ・インロン)。唐からきた」
「そんな者がいったい天楼館に何の用だ」
「ここに、頭目の璋小竹(チャン・シアオチュー)がいると耳にした」
「――確かにいるが、それが何か?」
「ならば即刻、璋小竹に逢わせよ」
「あいにく、どのような者であれ頭目と面会する事は禁じられている」
「華人、事は諦め、即刻立ち去れ」
見張りの男は銀竜を追い返そうとするが、銀竜は一歩も引き下がらない。
そして銀竜はぎろりと見張りを睨み、小さく言った。
「邪魔だては許さぬ」
その瞬間、目にも留まらぬ速さで剣を抜き、見張りを斬り殺した。
その時の見張りの叫び声で、天楼館から幾人の精鋭達が刀を持ってやってきたが、
銀竜はその者達も容赦なく手にかけた。
「――璋頭目!」
天楼館の役人は先の広間に集まっていた。
部下が叫んだ。一同がその方を見ると、未だ舞衣を纏う小竹が走って来た。
「なにごとです!」
「頭目、妖です!異国(とつくに)の妖が、一同を!」
動揺を隠せぬ部下に対して、小竹はあくまで冷静。その冷静を保って、部下に尋ねた。
「被害は?」
「駆けつけた精鋭部隊は殆ど……」
小竹は相変わらず冷静を保ち、そして別の集団を指揮する二人の男と女に命じた。
「高山隊長、流水隊長、この場を頼みます」
「璋頭目、まさか一人で行かれるのか?」
「さすがの頭目も、お一人では危のうございます!」
「部下と天楼館を守るのも私の役目です。よいですね、何があっても決して外へ出てはなりません」
小竹は現場へ向った。
同じ頃、叫び声で大量の血の臭いを流麗と犬夜叉は嗅ぎ取り、すぐさま門のほうへ走った。
そこへ来て見れば、大量の生臭い血の臭いが漂っている。
その血の海の中に一人、銀竜が立っていた。
「銀竜」
どれだけ銀竜の剣が速いのか。握る剣も衣服も、一点の返り血はない。
銀竜は目を細め、犬夜叉を見た。
「やはり生きていたな、犬夜叉」
「残念だな、銀竜。心優しい姉様に助けられて、この通りピンピンしてるぜ」
銀竜の視線が今度は流麗に向けられた。
「お前も他者を想う心は相変わらずのようだな、流麗」
「唯一の一族を救って何が悪いという。
銀竜、ここに来たのが貴様の運の尽き。今日こそ、一族の無念を晴らしてやる」
流麗は背に下げるあの神剣を抜くと、まっすぐ刃を銀竜に向けた。
同時に犬夜叉も鉄砕牙を抜き、流麗の横に並ぶ。
「銀竜大侠(インロンターシア)」
それと同時に、ついに小竹がやって来た。
舞衣の姿に、数本の短刀を納めた刀嚢を両腰に下げ、右手には弧状の刀を持っている。
銀竜が一目小竹の姿を見ると、少し表情が和らいだ。
何か銀竜と親密な小竹に、犬夜叉は小竹に訊ねた。
「お前、銀竜とどういう関係だ?」
犬夜叉の問いに、小竹は首を少しこちらに向け、そして口重そうに答えた。
「恋人です。唯一この私を愛してくれた方ですが、過去にこの方が犯した罪に、私はこの方の傍から……」
「――――」
「もう遠い昔の話だ」
銀竜が言った。
「過去は水に流し、小竹、お前もこの闘いに参戦せよ。私と共に、我が一族の仇(あだ)を果すのだ」
流麗と犬夜叉はじっと小竹を見る。
突如小竹の表情が変わった。
厳しい表情で、刀の刃先を銀竜に向け、小竹は言った。
「ここは重罪を犯した人を処刑する処」
「――――」
「ゆえに、今より貴様を処刑する!」
怒りを露にする小竹は、もはや冷静沈着な天楼の頭目ではなく、優雅な舞姫でもない。
最初に仕掛けたのは小竹だ。
それに続いて、流麗、犬夜叉もそれらの剣を用いて銀竜と刃を交えた。
銀竜と間合いがあけば、小竹は腰に携える刀嚢から刀を取り出し、そして放った。
飛翔刀(フェイシアンダオ)!
シャッと風を斬り、刀は素早く銀竜の方へ向うが、銀竜も稀ない武芸を持つ。
銀竜はその剣で、刀を全て払い捨てた。
一体、どれ程の時間を費やして闘ったのか。
時間の間隔など全く無い。
銀竜は三人と間を空けたが、懲りず犬夜叉は銀竜に目掛けて鉄砕牙を振るい落とした。
だが鉄砕牙よりひと回り小さい銀竜の剣は、難なく鉄砕牙の刃を止めた。
「犬夜叉、きっとこうしている間も葉蘭や紫蘭はお前の仲間と闘っているはずだ」
「何!?」
それを聞くと、犬夜叉の顔が憎に変わり、果てしない怒りをみせた。
目を尖らせ、牙を見せ、そして怒鳴り声をあげた。
「関係ない奴らまで巻き込みやがって……お前は一体どれだけ人を殺したら気がすむんだ!」
犬夜叉の怒りはもう最高潮に達した。
そんな犬夜叉に不敵な笑みを浮かべる銀竜は、また更に告げる。
「心の乱れは剣の乱れだぞ。一瞬たりとも心が乱れれば、命取りだ!」
銀竜の圧倒的な力で犬夜叉を押され、犬夜叉の胸を狙って銀竜は剣を突き伸ばした。
犬夜叉に止めを刺そうとしたその時、竹林の中から眩しい光が、銀竜の方へ突っ走って来た。
犬夜叉と銀竜は素早くそこを離れ、殺気ある光を避けた。
殺気に満ちた幽玄の竹林から、殺生丸が現れた。
あの光は、闘鬼神の奥義・蒼龍破。
「殺生丸。見ぬ内に随分ご立派になられた」
「――半妖如きに剣を汚そうとは。惜しいとは思わぬか」
「どのような者であれ、犬夜叉はそなた達と血が繋がる。剣が惜しいとは全く思わぬ」
やがて殺生丸は闘鬼神の先を銀竜に向け、低く言った。
「ここからは私が相手だ。尋常に勝負せよ」
間もなく、殺生丸と銀竜は激しく火花を散らし始めたが、すぐにその間に犬夜叉が入り込んだ。
殺生丸と犬夜叉が銀竜と一剣を交える。
今この瞬間、銀竜は流麗に対して、背を向けている。
ここで背後から銀竜を襲い、止めを刺せば、それで全てが終わる。
だが、何故かためらいを感じた。足が動かない。
暫くして、小竹が動いた。
駆けぬけ、強く地面を蹴り、激しく交える犬夜叉と銀竜の剣を己の刀で払い上げた。
一瞬乱れた剣の技に、素早く殺生丸が犬夜叉の前に立ち、再び蒼龍破を放った。
凄まじい青光りがはしり、あたり一面を飲み込み、激しく破壊していく。
やがて光りはきえ、荒れた一面を見ると、銀竜の姿は見えなかった。
きっとまた一瞬の隙で逃げたのだ。
またも決着がつけられぬまま闘いは終え、その後、犬夜叉は急いでかごめ達の元へ戻った。
竹林の中へ姿を消した犬夜叉を、誰も呼びとめも、追いかけもしない。
「璋頭目」
天楼館に押しとめていた部下が、騒ぎが静まったのを確かめ、その場にやって来た。
小竹は部下に、
「急用が出来ました。今すぐここを出ます」
刀と刀嚢を預け、早々と天楼館の中へ戻った。
その場に残されたのは、流麗と殺生丸。そして茂みの中から姿を現した邪見とりんだけ。
流麗はまっすぐ殺生丸を見つめるが、殺生丸は全く目を合わさず、目前の爪跡をじっと眺めていた。
夜深更――流麗は部屋へ戻る途中に天楼館に勤める若い女とすれ違った。
その女を呼び止めると、流麗は酒とアテを持ってくるよう頼んだ。
部屋には、二人分の布団が敷かれていた。きっと、今すれ違った女が敷いたのだ。
だが、まだ寝るわけにはいかない。
布団を避け、隅に置かれる円座と脇息を持って流麗は縁に出た。
円座の上に座り、脇息にもたれ寛ぎながら、暫く夜空を眺めていると、
先程の女が瓶子と玉杯と、一品と、もみじの葉を数枚、盆にのせてやって来た。
その盆を流麗が座す右側に丁寧に並べ置いた。
間もなく女は、深く頭を下げると、早々と離れた。
流麗は瓶子を持ち、玉杯の中に酒を注ぐと、たちまち玉杯から清酒の香りが漏れ、夜気に溶けた。
同時に天(そら)からの蒼い月光に反射し、更なる輝きをみせる。
煌煌と光放つ清酒を飲むのは、とても惜しかった。
前の庭は、草に混じって芙蓉、桔梗、菊、紫苑などの秋の花が咲き誇り、
池の横には二本の立派な紅葉の樹がたっている。
どの草も花も、昼間の雨で未だ水滴が乾ききっていない。
みっしりと重さをおびて、闇の中を光っていた。
吾君の心(うら) 愛しき世(とき)は空の果て
我が死期こそは 長月のころ
季節を想っていたら、頭に愛(かな)し愛(かな)しの想い歌が浮かんだ。
想い歌に、流麗は軽い溜息を吐くと、漸く杯の中の酒を喉へと流し込んだ。
――と、重い床の板が軋む重い音が聴こえた。
横を見ると、犬夜叉がこちらに歩いてくる。
「どこにいたの?」
流麗が声をかけると、犬夜叉は立ち止まり、そして答えた。
「外に出て、空気を吸ってきた」
「もう亥の刻を過ぎている。早く休んではどう?」
「そういう姉貴こそ、今日西国から来たんだ。早く休めよ」
ふと流麗は空を見上げた。
「雨雲もなく、月は顔を露にしている。こんな夜を眺めぬとは、とてももったいない」
「――――」
「眠らぬなら、私と宴の続きをしよう」
流麗は立ち上がると、部屋からまた一つ円座を持ってきた。
遠慮なく犬夜叉は円座の上に、無造作に胡坐をかいて座った。
左肘を左膝の上に置き、左腕をたててその手の上に顎のせ、流麗とは何一つ会話を交わさず、前の光景を眺めた。
「なあ、おい……こんな戦ばっかりの世の中も、なかなか捨てたものじゃねぇな」
「この庭は、城の庭とまるで同じ。あそこに季節の花が並び、池の傍には大きな桜の樹がたっている。
土を掘り、石をつめて、川や池を作り、その中に鯉や、亀や蝦蟇を放つ」
「――――」
「闘いがなければ、今も仲間と一緒に月の宴を楽しんでいるはずなのに。だがお前との宴も、また一味違ってよい」
犬夜叉も流麗との宴は悪くはない。
この男が妖怪を慕うのは流麗だけだ。
先程、流麗が詠った歌が犬夜叉は気になる。何のためらいも無く犬夜叉は流麗に歌を訊ねた。
「今の歌は何だ?」
「夫を想う歌よ」
「夫?」
「夫の本名はヨソラ。父親から王座と、“嵩明良”という名跡を継ぎ、やがて出雲の王となった。
とても強くて優しくて、勇敢な男だったよ」
流麗は、更に言う。
「かつて嵩明良には、如月という高麗人の許婚がいたの。けれど敵の謀に王族共に如月を失ったとか。
如月のことは心の奥底にしまって、私と出会い祝言を挙げたけど、
すぐに、お前のお父様と一緒に竜骨精と闘って、若くして死んでしまった」
「――――」
「人と出会い、愛するほど哀しいものはない。出会えば必ず、その人の死に目に立ち会わねばならない」
「人生の中で一番かなしい運命(さだめ)かもしれねぇな」
「けど、人を愛さぬわけにはいかない。誰だって、愛こそは全てだもの」
「――――」
「私が地方へ行くのは闘いを施しに行くだけだった。
それに嵩明良と出会ってからは、よく夜中に私を連れて、あらゆる地方へ連れて行ってくれた。
その時にいつも、嵩明良は私にお前にとって為す事は何かと、よくたずねた」
遠い昔ほど、懐かしい思い出を浮かべると自然と微笑が浮かぶ。
またその時、嵩明良は流麗へ天の月を贈った。それを想うと、今でも感涙してしまう。
「それは、もう決めたのか?」
「あぁ。夫は出雲を治め、一族は代々から西国を治めていた。
なら私は、天下を泰平すること。私も闘って、最期は英雄に……」
犬夜叉は言葉を詰まらせてしまった。
天下泰平という、あまりに大きな夢に、まともな言葉が出なかったのだ。
犬夜叉は軽い息を鼻から吐き、そして流麗に言った。
「流麗は、今までたくさん敵と闘ってきた。その度に、死にかけたこともあるはずだ」
「何を言う?」
「お前と七日過ごした後、俺はずっと一人で生きた。
前に妖怪が現れて、刀や爪を振るう度に、いつもあの時のことを思い出す」
「あの時とは……」
「俺とお袋が、銀竜の手下に殺されそうになった時だ。炎からお前が現れて、俺とお袋を救った」
「――――」
「俺は、お前を頼りにしている。妖怪を相手にこんな思いをするのは、お前だけだ」
「――――」
「天下泰平なんて簡単にできるものじゃないぜ。きっと今まで以上に、多くの危機に陥る。
そんなことよりも、やっぱり今までどおり西国を治めて、平穏に暮らしていってほしい」
「――真の戦士なら、闘いなぞに我が命は惜しくはない。お前のお父様がよい例よ」
やがて玉杯を縁の上に置き、着物の間に挿す竜笛を取り出した。
口に近づけ、息を吹き込むと、得意の一曲、夢幻泡影を奏でた。
大気に溶け込んだ庭の花の香りと流麗が纏う着物からの薫衣香の香りを、
犬夜叉は空気と一緒に吸い込みながら、静かにその曲を聴いた。
更に夜は更ける。
天楼館の門前に二人の男が刀を持ち、左腰に刀嚢を携えて見張りをしていた。
風が吹く度に笹がざわざわと左右に揺れ、とても不気味。
前方から黒い人影が見えた。
「止まられよ」
男の言葉にその者はぴたりと立ち止まり、大松明の灯りでその者の顔をよく見た。
「なんと怪しい風体をする男ぞ」
「おい、名を申せ」
また見張りの男が声をかけると、その者は小さく低く答えた。
「我が名は――劉銀竜(リウ・インロン)。唐からきた」
「そんな者がいったい天楼館に何の用だ」
「ここに、頭目の璋小竹(チャン・シアオチュー)がいると耳にした」
「――確かにいるが、それが何か?」
「ならば即刻、璋小竹に逢わせよ」
「あいにく、どのような者であれ頭目と面会する事は禁じられている」
「華人、事は諦め、即刻立ち去れ」
見張りの男は銀竜を追い返そうとするが、銀竜は一歩も引き下がらない。
そして銀竜はぎろりと見張りを睨み、小さく言った。
「邪魔だては許さぬ」
その瞬間、目にも留まらぬ速さで剣を抜き、見張りを斬り殺した。
その時の見張りの叫び声で、天楼館から幾人の精鋭達が刀を持ってやってきたが、
銀竜はその者達も容赦なく手にかけた。
「――璋頭目!」
天楼館の役人は先の広間に集まっていた。
部下が叫んだ。一同がその方を見ると、未だ舞衣を纏う小竹が走って来た。
「なにごとです!」
「頭目、妖です!異国(とつくに)の妖が、一同を!」
動揺を隠せぬ部下に対して、小竹はあくまで冷静。その冷静を保って、部下に尋ねた。
「被害は?」
「駆けつけた精鋭部隊は殆ど……」
小竹は相変わらず冷静を保ち、そして別の集団を指揮する二人の男と女に命じた。
「高山隊長、流水隊長、この場を頼みます」
「璋頭目、まさか一人で行かれるのか?」
「さすがの頭目も、お一人では危のうございます!」
「部下と天楼館を守るのも私の役目です。よいですね、何があっても決して外へ出てはなりません」
小竹は現場へ向った。
同じ頃、叫び声で大量の血の臭いを流麗と犬夜叉は嗅ぎ取り、すぐさま門のほうへ走った。
そこへ来て見れば、大量の生臭い血の臭いが漂っている。
その血の海の中に一人、銀竜が立っていた。
「銀竜」
どれだけ銀竜の剣が速いのか。握る剣も衣服も、一点の返り血はない。
銀竜は目を細め、犬夜叉を見た。
「やはり生きていたな、犬夜叉」
「残念だな、銀竜。心優しい姉様に助けられて、この通りピンピンしてるぜ」
銀竜の視線が今度は流麗に向けられた。
「お前も他者を想う心は相変わらずのようだな、流麗」
「唯一の一族を救って何が悪いという。
銀竜、ここに来たのが貴様の運の尽き。今日こそ、一族の無念を晴らしてやる」
流麗は背に下げるあの神剣を抜くと、まっすぐ刃を銀竜に向けた。
同時に犬夜叉も鉄砕牙を抜き、流麗の横に並ぶ。
「銀竜大侠(インロンターシア)」
それと同時に、ついに小竹がやって来た。
舞衣の姿に、数本の短刀を納めた刀嚢を両腰に下げ、右手には弧状の刀を持っている。
銀竜が一目小竹の姿を見ると、少し表情が和らいだ。
何か銀竜と親密な小竹に、犬夜叉は小竹に訊ねた。
「お前、銀竜とどういう関係だ?」
犬夜叉の問いに、小竹は首を少しこちらに向け、そして口重そうに答えた。
「恋人です。唯一この私を愛してくれた方ですが、過去にこの方が犯した罪に、私はこの方の傍から……」
「――――」
「もう遠い昔の話だ」
銀竜が言った。
「過去は水に流し、小竹、お前もこの闘いに参戦せよ。私と共に、我が一族の仇(あだ)を果すのだ」
流麗と犬夜叉はじっと小竹を見る。
突如小竹の表情が変わった。
厳しい表情で、刀の刃先を銀竜に向け、小竹は言った。
「ここは重罪を犯した人を処刑する処」
「――――」
「ゆえに、今より貴様を処刑する!」
怒りを露にする小竹は、もはや冷静沈着な天楼の頭目ではなく、優雅な舞姫でもない。
最初に仕掛けたのは小竹だ。
それに続いて、流麗、犬夜叉もそれらの剣を用いて銀竜と刃を交えた。
銀竜と間合いがあけば、小竹は腰に携える刀嚢から刀を取り出し、そして放った。
飛翔刀(フェイシアンダオ)!
シャッと風を斬り、刀は素早く銀竜の方へ向うが、銀竜も稀ない武芸を持つ。
銀竜はその剣で、刀を全て払い捨てた。
一体、どれ程の時間を費やして闘ったのか。
時間の間隔など全く無い。
銀竜は三人と間を空けたが、懲りず犬夜叉は銀竜に目掛けて鉄砕牙を振るい落とした。
だが鉄砕牙よりひと回り小さい銀竜の剣は、難なく鉄砕牙の刃を止めた。
「犬夜叉、きっとこうしている間も葉蘭や紫蘭はお前の仲間と闘っているはずだ」
「何!?」
それを聞くと、犬夜叉の顔が憎に変わり、果てしない怒りをみせた。
目を尖らせ、牙を見せ、そして怒鳴り声をあげた。
「関係ない奴らまで巻き込みやがって……お前は一体どれだけ人を殺したら気がすむんだ!」
犬夜叉の怒りはもう最高潮に達した。
そんな犬夜叉に不敵な笑みを浮かべる銀竜は、また更に告げる。
「心の乱れは剣の乱れだぞ。一瞬たりとも心が乱れれば、命取りだ!」
銀竜の圧倒的な力で犬夜叉を押され、犬夜叉の胸を狙って銀竜は剣を突き伸ばした。
犬夜叉に止めを刺そうとしたその時、竹林の中から眩しい光が、銀竜の方へ突っ走って来た。
犬夜叉と銀竜は素早くそこを離れ、殺気ある光を避けた。
殺気に満ちた幽玄の竹林から、殺生丸が現れた。
あの光は、闘鬼神の奥義・蒼龍破。
「殺生丸。見ぬ内に随分ご立派になられた」
「――半妖如きに剣を汚そうとは。惜しいとは思わぬか」
「どのような者であれ、犬夜叉はそなた達と血が繋がる。剣が惜しいとは全く思わぬ」
やがて殺生丸は闘鬼神の先を銀竜に向け、低く言った。
「ここからは私が相手だ。尋常に勝負せよ」
間もなく、殺生丸と銀竜は激しく火花を散らし始めたが、すぐにその間に犬夜叉が入り込んだ。
殺生丸と犬夜叉が銀竜と一剣を交える。
今この瞬間、銀竜は流麗に対して、背を向けている。
ここで背後から銀竜を襲い、止めを刺せば、それで全てが終わる。
だが、何故かためらいを感じた。足が動かない。
暫くして、小竹が動いた。
駆けぬけ、強く地面を蹴り、激しく交える犬夜叉と銀竜の剣を己の刀で払い上げた。
一瞬乱れた剣の技に、素早く殺生丸が犬夜叉の前に立ち、再び蒼龍破を放った。
凄まじい青光りがはしり、あたり一面を飲み込み、激しく破壊していく。
やがて光りはきえ、荒れた一面を見ると、銀竜の姿は見えなかった。
きっとまた一瞬の隙で逃げたのだ。
またも決着がつけられぬまま闘いは終え、その後、犬夜叉は急いでかごめ達の元へ戻った。
竹林の中へ姿を消した犬夜叉を、誰も呼びとめも、追いかけもしない。
「璋頭目」
天楼館に押しとめていた部下が、騒ぎが静まったのを確かめ、その場にやって来た。
小竹は部下に、
「急用が出来ました。今すぐここを出ます」
刀と刀嚢を預け、早々と天楼館の中へ戻った。
その場に残されたのは、流麗と殺生丸。そして茂みの中から姿を現した邪見とりんだけ。
流麗はまっすぐ殺生丸を見つめるが、殺生丸は全く目を合わさず、目前の爪跡をじっと眺めていた。