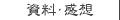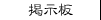「LOVER 【夢 幻 泡 影】 肆」 優サマ
「珊瑚、七宝、お前達は残って、かごめ様を守りなさい。私は、一人でゆく」
「待って、法師様!行かないで!」
「約束する。お前の為に、必ず戻ると……」
葉蘭は一口の剣、紫蘭は双方の扇を鋭い刃物と化かせ、弥勒を容赦なく襲う。
二人の攻撃を弥勒は錫杖で確実に受け止め、払う。
同じような攻撃で、時間ばかりが過ぎる。
額に浮かぶ脂汗を、紺色の衣の袖で拭う。
息が荒れる弥勒に対して葉蘭が言った。
「諦めなさい、若法師。所詮そなたは人なる身。わたくし達には敵わない」
冷酷な葉蘭に、弥勒は錫杖を地面に深く突き刺し、右腕に巻きつける数珠を掴んだ。
「あの女との約束を、破るわけにはいかない。貴様らに敗れるわけにはゆかぬのだ!」
ついに数珠を外し、葉蘭と紫蘭にその掌を見せた。
「風穴!」
封印が解かれた風穴は凄まじい力を露にし、周りのものを全て飲み込んでいく。
弥勒にこんな力があろうとは、流石の葉蘭も紫蘭も恐れ戦いた。
だが、それも本の一瞬だけ。
紫蘭は葉蘭の背にまわり、何と葉蘭は自らの左の掌に剣を深く突き刺した。
剣を引き抜くと忽ち赤い鮮血が迸り、だが、その手を強く握り締め口元に近づけ、呪を唱えた。
短い呪を唱えると、血まみれた手を握りながら左腕をまっすぐ伸ばし、握る手を広げた。
弥勒が目にした光景は、あの深い斬り傷の上から、弥勒と同じ風穴が穿たれている。
流石は魔術師なる葉蘭は、自ら風穴を穿つことも容易い。
力は互角。
巨大な渦が起こり、その渦の中にあらゆる塵が巻き込まれ、前方は見えない。
弥勒も葉蘭も絶えず風穴を開き続け、一方の紫蘭は双方の扇を広げると、葉蘭の傍から離れた。
風穴の渦を飛び越え、頭上から弥勒を襲い、止めを刺すつもりだ。
紫蘭が放った風の技を寸前になって弥勒は気づき、風穴を閉じて後ろへ下がり、技を避けた。
葉蘭はこの隙を逃さず、また意図も簡単に風穴の存在を消し、再び剣を持って弥勒の傍へ走った。
容赦のない葉蘭の剣の技に、弥勒はひたすら錫杖で払う。
葉蘭と激しく火花を散らし、紫蘭の気配をとる間がなく
――紫蘭がすぐ背後にいると分かった時は、既に遅かった。
漸く犬夜叉が、かごめ達の元へ戻ってきた。
すると、いち早く珊瑚は犬夜叉に叫んだ。
「犬夜叉、法師様が今もたった一人で闘っている!早く法師様の所へ!」
珊瑚がそこまで言うと、犬夜叉の鼻に濃い血の臭いが届いた。
紛れもない弥勒の血の臭い!
かごめと、珊瑚と、七宝を連れて、犬夜叉は臭いを辿って弥勒の元へ疾く向った。
やがてその場に辿りつくと、うつ伏せになって倒れる弥勒の姿があった。
犬夜叉は弥勒を抱き起こすと、大声で弥勒に呼びかけた。
「大丈夫か、弥勒!」
幾度呼びかけても、弥勒は目を覚まさない。
何とも痛ましく無惨な弥勒の姿に、珊瑚はまるで魂が抜けたようになっている。
――珊瑚。
風のような声で、弥勒はその口からそう言った。
珊瑚の目からは愛憎が混じった涙が、何粒も零れ落ちていた。
朝になった。
珊瑚はずっと弥勒を看病していたが、遂に決心し、
刀だけを持って眠る弥勒を残して、そこを飛び出した。
かごめと七宝が弥勒の為に薬草採りから戻ってくる時、珊瑚を見た。
とても厳しい表情でひたすら走る珊瑚に、かごめが、
「珊瑚ちゃん!」
声をかけたが、珊瑚はこちらを振り向かない。
「珊瑚ちゃん、どこへ行くの!」
またかごめが叫んだが、珊瑚は振り向くことも、立ち止まることもなく、やがて姿を消えてしまった。
「珊瑚のやつ……難しそうな顔をして、どこへ行くんじゃ?」
「――七宝ちゃん、戻って犬夜叉を呼ぼう。急ごう」
何か胸騒ぎするかごめは、七宝と急いで戻った。
珊瑚が向った場所は美しく色とりどりの花が咲く花畑。
薄い水色や黄色、紫、淡紅など花びらが風に乗って空気の中を踊る。
だがそこにはもの凄まじい殺気があった。
珊瑚の前には、背を向ける紫蘭が立っている。
紫蘭は後の珊瑚に小さく低く、冷酷に言った。
「お前とは闘わぬ……去ね」
紫蘭の背を見据える珊瑚の目は解き放たれた激しい怒りに燃えている。
悔しく哀しく、歯を食いしばりながら、刀を抜くと大きく叫び声をあげた。
「うるさい!貴様を殺して、法師様の仇を討ってやる!!!」
怒涛の如く勢いで珊瑚は紫蘭の元へ走った。
愛憎ゆえに、珊瑚は刀を振るい、その技を紫蘭はまるで花と一緒に踊るように避けた。
珊瑚に背を向けたまま花畑の中を走り、当の珊瑚は懲りず追いかけ、刃を振る。
やがて紫蘭に追いつき、刀を振ると、刃が紫蘭の頬を掠った。
紫蘭の雪のような白い肌から鮮血が飛び、紫蘭は珊瑚と二十歩以上の間隔をあけた。
だが珊瑚は尚も紫蘭を追う。
懲りぬ珊瑚に、紫蘭は低く小さく言った。
「さほどに死に急ぎたくば、死なせてやる」
あと数歩で紫蘭の身に刀が貫く時、ついに紫蘭は片方の扇を大きく広げて仰いだ。
その瞬間強く凄まじい大風が吹き、珊瑚の体がふわりと浮き、また紫蘭と大きく間があいた。
地面に足をつけると、珊瑚は素早く刃を紫蘭に定め、一方の背を向ける紫蘭はこちらを向いた。
風によって紫蘭の長い髪の毛は顔を覆い隠すが、その隙間から切れ長の目と、紅い唇が見える。
紫蘭は薄く冷笑を浮かべていた。
その顔が、珊瑚は気にいらない。
再び珊瑚は大声を出して走り出した。
狙いを定めて刃を突き伸ばし、だが紫蘭は刃を大きく飛び越え、
地面に足をつけると同時に扇を振った。
大風と共に無数の花びらが視界を遮るが、珊瑚は負けじと紫蘭に反撃する。
紫蘭は扇を銀(しろがね)の刃と化かし、
鋭い刃を珊瑚は刀を鞘で交わしてゆくが、やはり紫蘭の力に負け、倒されてしまう。
それでも珊瑚はすぐさまに立ち上がり、紫蘭と立ち向かった。
幾度も刃向かう珊瑚に対し、紫蘭はまた片やの色鮮やかな扇を振るった。
たちまち大風が吹き、珊瑚は風に捕らわれ、体が宙に浮いた。
渦が起こってそれに呑まれ、やがて渦がおさまると激しい勢いで珊瑚は花畑の上に倒される。
同じことばかりの繰り返し。だが珊瑚はまたも立ち上がり、紫蘭の方へ向った。
向って来る珊瑚に紫蘭はまた扇を振ると、再び大風が吹き、今度は大風と共に花びらが珊瑚を襲う。
完全に視界を遮られ、辺りの間隔を失ってしまった。
無数の花びらの中でもがく珊瑚に、紫蘭は銀の刃に化かす扇を、まっすぐ突き伸ばした。
まっすぐ向うその刃は、珊瑚の腹部を深く突き刺した。
かっと珊瑚は目を見開き、紫蘭はその珊瑚に上目で見つめた。
珊瑚は眉間に皺を寄せつつ、渾身の力で再び刀を振ったが、苦もなく紫蘭は刃を避け、数歩引き下がった。
珊瑚は己の身の現状をよく見た。
力ずくで刃を引き抜き、それを紫蘭に投げつけた。
刃はまっすぐ紫蘭に向って飛ぶが、当人はそれを容易く受け取り、
刃先に血がついているにも関らず懐中におさめた。
そして、また珊瑚に背を向ける。
珊瑚は片膝を突き、目前の紫蘭の背を見つめながら、突然クスクスと笑い声をあげた。
そして、背を向ける紫蘭に対して珊瑚は言った。
「なにを笑う?」
「――あんたも、全然大したことないね」
「――――」
「一発で仕留めないんだから……」
紫蘭は何も答えない。
やがて珊瑚は、立っている力も笑う気力も失せ、ついに花畑の中へと倒れた。
犬夜叉、かごめ、七宝は手分けして珊瑚を探している。
犬夜叉がいればすぐに珊瑚に追いつくと思っていたが、当の珊瑚は通った道に毒か薬をまいたのだろう。
犬夜叉の鼻はそういう臭いしか嗅ぎ取れず、珊瑚を見つけることは出来なかった。
三人の騒がしさに弥勒が目を覚ました。
事を察し、傷の痛みを堪えながら、雲母を連ね、一人で珊瑚の行方を追った。
手がかりは無い。ただ雲母の勘に任すしかない。
やがて花畑に来ると、雲母の足が止まった。
風が吹くたびに茎は左右に揺れ、花びらが空気の中を舞う。
茎が揺れるたびに、何か黒い物体が見えた。
それが人の姿にも見える。
「珊瑚!」
まさしく、珊瑚の姿だった。
もはや傷の痛みなど全く感じず、弥勒は無我夢中に珊瑚の傍に駆け寄り、その体を抱きかかえた。
珊瑚の姿を見るや、顔や体に幾箇所も斬り傷がある。
「珊瑚、なぜ行こうとしたんだ……」
弥勒の声を、珊瑚の耳は捉えた。
薄っすら目を開け、弥勒の顔を見つめ、力を絞って声を出した。
「法師様……どうして来たの?」
「決まっている。他の誰よりも、お前のことが一番心配だからだ」
珊瑚の目にまた涙が浮かんだ。
だが、目に涙を浮かべながらも精一杯の笑顔も浮かべている。
そんな苦痛に耐える笑顔で、珊瑚は弥勒にこうも話した。
「法師様、私、ずっと夢見てきたことがあるの……少しだけ、聞いてくれる?」
「何だ?」
「この件が終わって、いつか、きっと、旅も終えたらね……たとえ幻や泡みたいな儚い人生でも――」
「――――」
「法師様と、琥珀と、風向き次第の、風流な日々を送る……」
「――――」
「私も風のように生きて、花のように綺麗に散りたくて……」
「私が必ず、お前の夢を叶えてやる。私と琥珀と、一緒に行こう」
精一杯の笑顔を浮かべる珊瑚を、弥勒は強く、強く抱きしめた。
とても眺めのいい崖の麓に、犬夜叉は一人、夕焼けを眺めていた。
よい景色を眺めながら、いまだ少し残る夏の風に総身を任せる。
やがて背後から人の気配を感じた。
その方を向くと、あの天楼館の頭目であり、踊り子でもあった璋小竹が立っていた。
天楼館の制服ではなく、妖艶な舞衣でもなく、男物の武装姿だ。
右手には小さく“璋小竹”と名が彫られた銀槍を持ち、両腰には小刀を納める刀嚢を下げている。
「お前……」
「天楼館の璋小竹(しょう・ささ)です。昨日は大変、お世話になりました」
小竹は深く頭を下げた。
再び頭をあげ、犬夜叉と目を合わすと、小竹は尋ねた。
「お仲間が風術師の紫蘭の仕業で、重傷を負ったようですが、容態は如何ほどに?」
「――命に別状はない。ただ当分、動かすことが出来ない」
焦るようでもなく、怒りに溢れるでもなく、犬夜叉は冷静さを保っている。
小竹は犬夜叉にこれだけは言っておこうと、槍を地面に突き立て、数歩前に出て、そして語り始めた。
「犬夜叉様、個人的な事ですが言わせてください。
私はこの通り、劉銀竜(りゅう・ぎんりょう)と同じ唐国の生まれ。
あの頃もまた、絶えぬ戦ばかりでした。それゆえに、私の一族は敵に奪われ、
仇を果そうと決めたとき、時に大侠のお父様に救われました。ご察しください、大侠は慈悲があります。
本当は人を殺めることは、一切……」
「もう昔のことだぜ、小竹。信じていても、いつかは必ず裏切られる」
「――――」
「銀竜は裏切り者だ。お前を裏切って、今まで大勢の人間や妖怪を殺した。
お前が勤めてた館の仲間も、そうじゃねぇか」
突然、小竹がどこを見ているのか分からなくなった。
視線が合わない。
当の小竹は、銀竜と共に生きたあの頃の事を脳裏に浮かべた。
璋小竹――以前はそんな名前ではなかった。
三百年前の中国、
有名な武芸人・馮丹華(フェン・ダンフア)と、華麗な舞姫・煌(ホアン)の間に長女が生まれた。
両親はその子に麗玉(リーユィ)と名づけ、それがのちの璋小竹だ。
山岳地帯の村で村人と共に、麗玉は両親と妹の美琳(メイリン)となに不自由なく、平穏に暮らしていた。
丹華の手にはいつも刀があり、両腰には短刀を納める刀嚢を下げ、
得意とする技はただ一つ――必殺・飛翔刀(フェイシアンダオ)。
丹華は二人の娘達にその技と真意を告げ、他の誰にも、飛翔刀の真意を語ることはなかった。
だがまもなく、丹華ははやりの病にかかり、若くして亡くなってしまった。
嘆き悲しみに暮れる妻の煌は、二人の愛娘を連れて村を去り、一族の許へ戻った。
母方の一族は、哀れな母子を受け入れ、手厚に三人を敵から守った。
時に麗玉は美琳と、かつて生まれ育った村へ向って友人達にも逢っていた。
誰にも縛られず、麗玉と美琳はとても幸せな姉妹とよく言われていた。
だがまた悲劇がおとずれる。
突然にも県の捕吏が一族を襲ってきた。
武器を全て奪われた一族は為す術ないまま、その捕吏の手によって全滅してしまった。
幸いにも麗玉だけが生き残った。
一族の亡骸を前に麗玉は泣き叫び、やがてはその泪も枯れ果てた。
麗玉は決意した。
必ず一族の仇を討つ!
父の形見の刀嚢を両腰に携え、馮麗玉から璋小竹へ名を変えて、
正体を隠しながら捕吏を追い、その背後を襲った。
だが当時の麗玉の武芸の技量では、たとえ人間でも手が余る。
捕吏と苦戦する中、やがて麗玉の前に当時の竜舌蘭大魔王が現れた。
竜舌蘭は麗玉を救い、麗玉の素性を既に気づいていながら迷わず一門に招いた。
竜舌蘭一族と共にすることになった麗玉は、やがて心を一転にし、
一族とわずかに殺めてしまった捕吏達の魂を悼んだ。
血と泥に汚れた衣服を棄てて、化粧をし、色鮮やかな衣装や装飾品など身につけるその姿はとても美しく、
その姿を一目した銀竜は麗玉に近づき、やがて深く寵愛した。
その頃の麗玉も、これほど寵愛する銀竜をとても慕っていた。
だが、竜舌蘭やたとえ銀竜にも本名を明かすことはなく、“璋小竹”として通していた。
父や一族の死を忘れつつあったそんな時、突如銀竜は一振りの剣を携え、
竜舌蘭と配下と、あらゆる国へ向い、大戦を始めた。
そして、やがては日本の西国に降り立った。
元々因縁があったそこの一族と決着をつける為、
十年の歳月をかける激闘を施したが、むなしい結果となってしまった。
麗玉はこれ以上の戦はやめるようにと銀竜を説得し続けたが、それもやがては無駄に終わってしまった。
――小竹は銀槍を持ち、そして犬夜叉に告げた。
「劉銀竜は剣について数百年の研鑽を積み、同時に多くの刺客を唐より連れて参りました」
「――――」
「乱心は命取りです、犬夜叉様。闘われる際には、どうかそのお心を乱さぬように」
やがて小竹は犬夜叉の前から姿を消した。
犬夜叉がかごめ達の元へ戻ろうと思った頃は、既に夜になっていた。
暗い獣道を歩く途中、ふと足が止まった。
前方に七宝と流麗がいる。
「犬夜叉」
一番に犬夜叉の存在に気づいたのは七宝だった。つられて流麗が犬夜叉のほうを見た。
「どこにいた?」
「どこにも……すぐ近くにいた」
「ならば一言でも言い残せばいいものを……この現状に、どれ程七宝はお前を案じて探しまわっていたか」
「――ごめんな、七宝」
「犬夜叉に何も起こらねば、それでいい。それより弥勒と珊瑚は大丈夫じゃ。
流麗の“摩訶不思議な力”とやらで、傷は治った」
「本当か……?」
「おうっ。だから、いつまでもそんな顔するなよ!それでは、いつも犬夜叉ではないからなっ!」
犬夜叉は安心した顔で「おう」と、七宝に答えた。
「犬夜叉も戻ってきたことじゃ。かごめも心配しておろうし、早く戻ろう」
流麗と七宝は、もと来た道を歩き始めた。
犬夜叉は少し遅れて、その後につき、戻った。
「待って、法師様!行かないで!」
「約束する。お前の為に、必ず戻ると……」
葉蘭は一口の剣、紫蘭は双方の扇を鋭い刃物と化かせ、弥勒を容赦なく襲う。
二人の攻撃を弥勒は錫杖で確実に受け止め、払う。
同じような攻撃で、時間ばかりが過ぎる。
額に浮かぶ脂汗を、紺色の衣の袖で拭う。
息が荒れる弥勒に対して葉蘭が言った。
「諦めなさい、若法師。所詮そなたは人なる身。わたくし達には敵わない」
冷酷な葉蘭に、弥勒は錫杖を地面に深く突き刺し、右腕に巻きつける数珠を掴んだ。
「あの女との約束を、破るわけにはいかない。貴様らに敗れるわけにはゆかぬのだ!」
ついに数珠を外し、葉蘭と紫蘭にその掌を見せた。
「風穴!」
封印が解かれた風穴は凄まじい力を露にし、周りのものを全て飲み込んでいく。
弥勒にこんな力があろうとは、流石の葉蘭も紫蘭も恐れ戦いた。
だが、それも本の一瞬だけ。
紫蘭は葉蘭の背にまわり、何と葉蘭は自らの左の掌に剣を深く突き刺した。
剣を引き抜くと忽ち赤い鮮血が迸り、だが、その手を強く握り締め口元に近づけ、呪を唱えた。
短い呪を唱えると、血まみれた手を握りながら左腕をまっすぐ伸ばし、握る手を広げた。
弥勒が目にした光景は、あの深い斬り傷の上から、弥勒と同じ風穴が穿たれている。
流石は魔術師なる葉蘭は、自ら風穴を穿つことも容易い。
力は互角。
巨大な渦が起こり、その渦の中にあらゆる塵が巻き込まれ、前方は見えない。
弥勒も葉蘭も絶えず風穴を開き続け、一方の紫蘭は双方の扇を広げると、葉蘭の傍から離れた。
風穴の渦を飛び越え、頭上から弥勒を襲い、止めを刺すつもりだ。
紫蘭が放った風の技を寸前になって弥勒は気づき、風穴を閉じて後ろへ下がり、技を避けた。
葉蘭はこの隙を逃さず、また意図も簡単に風穴の存在を消し、再び剣を持って弥勒の傍へ走った。
容赦のない葉蘭の剣の技に、弥勒はひたすら錫杖で払う。
葉蘭と激しく火花を散らし、紫蘭の気配をとる間がなく
――紫蘭がすぐ背後にいると分かった時は、既に遅かった。
漸く犬夜叉が、かごめ達の元へ戻ってきた。
すると、いち早く珊瑚は犬夜叉に叫んだ。
「犬夜叉、法師様が今もたった一人で闘っている!早く法師様の所へ!」
珊瑚がそこまで言うと、犬夜叉の鼻に濃い血の臭いが届いた。
紛れもない弥勒の血の臭い!
かごめと、珊瑚と、七宝を連れて、犬夜叉は臭いを辿って弥勒の元へ疾く向った。
やがてその場に辿りつくと、うつ伏せになって倒れる弥勒の姿があった。
犬夜叉は弥勒を抱き起こすと、大声で弥勒に呼びかけた。
「大丈夫か、弥勒!」
幾度呼びかけても、弥勒は目を覚まさない。
何とも痛ましく無惨な弥勒の姿に、珊瑚はまるで魂が抜けたようになっている。
――珊瑚。
風のような声で、弥勒はその口からそう言った。
珊瑚の目からは愛憎が混じった涙が、何粒も零れ落ちていた。
朝になった。
珊瑚はずっと弥勒を看病していたが、遂に決心し、
刀だけを持って眠る弥勒を残して、そこを飛び出した。
かごめと七宝が弥勒の為に薬草採りから戻ってくる時、珊瑚を見た。
とても厳しい表情でひたすら走る珊瑚に、かごめが、
「珊瑚ちゃん!」
声をかけたが、珊瑚はこちらを振り向かない。
「珊瑚ちゃん、どこへ行くの!」
またかごめが叫んだが、珊瑚は振り向くことも、立ち止まることもなく、やがて姿を消えてしまった。
「珊瑚のやつ……難しそうな顔をして、どこへ行くんじゃ?」
「――七宝ちゃん、戻って犬夜叉を呼ぼう。急ごう」
何か胸騒ぎするかごめは、七宝と急いで戻った。
珊瑚が向った場所は美しく色とりどりの花が咲く花畑。
薄い水色や黄色、紫、淡紅など花びらが風に乗って空気の中を踊る。
だがそこにはもの凄まじい殺気があった。
珊瑚の前には、背を向ける紫蘭が立っている。
紫蘭は後の珊瑚に小さく低く、冷酷に言った。
「お前とは闘わぬ……去ね」
紫蘭の背を見据える珊瑚の目は解き放たれた激しい怒りに燃えている。
悔しく哀しく、歯を食いしばりながら、刀を抜くと大きく叫び声をあげた。
「うるさい!貴様を殺して、法師様の仇を討ってやる!!!」
怒涛の如く勢いで珊瑚は紫蘭の元へ走った。
愛憎ゆえに、珊瑚は刀を振るい、その技を紫蘭はまるで花と一緒に踊るように避けた。
珊瑚に背を向けたまま花畑の中を走り、当の珊瑚は懲りず追いかけ、刃を振る。
やがて紫蘭に追いつき、刀を振ると、刃が紫蘭の頬を掠った。
紫蘭の雪のような白い肌から鮮血が飛び、紫蘭は珊瑚と二十歩以上の間隔をあけた。
だが珊瑚は尚も紫蘭を追う。
懲りぬ珊瑚に、紫蘭は低く小さく言った。
「さほどに死に急ぎたくば、死なせてやる」
あと数歩で紫蘭の身に刀が貫く時、ついに紫蘭は片方の扇を大きく広げて仰いだ。
その瞬間強く凄まじい大風が吹き、珊瑚の体がふわりと浮き、また紫蘭と大きく間があいた。
地面に足をつけると、珊瑚は素早く刃を紫蘭に定め、一方の背を向ける紫蘭はこちらを向いた。
風によって紫蘭の長い髪の毛は顔を覆い隠すが、その隙間から切れ長の目と、紅い唇が見える。
紫蘭は薄く冷笑を浮かべていた。
その顔が、珊瑚は気にいらない。
再び珊瑚は大声を出して走り出した。
狙いを定めて刃を突き伸ばし、だが紫蘭は刃を大きく飛び越え、
地面に足をつけると同時に扇を振った。
大風と共に無数の花びらが視界を遮るが、珊瑚は負けじと紫蘭に反撃する。
紫蘭は扇を銀(しろがね)の刃と化かし、
鋭い刃を珊瑚は刀を鞘で交わしてゆくが、やはり紫蘭の力に負け、倒されてしまう。
それでも珊瑚はすぐさまに立ち上がり、紫蘭と立ち向かった。
幾度も刃向かう珊瑚に対し、紫蘭はまた片やの色鮮やかな扇を振るった。
たちまち大風が吹き、珊瑚は風に捕らわれ、体が宙に浮いた。
渦が起こってそれに呑まれ、やがて渦がおさまると激しい勢いで珊瑚は花畑の上に倒される。
同じことばかりの繰り返し。だが珊瑚はまたも立ち上がり、紫蘭の方へ向った。
向って来る珊瑚に紫蘭はまた扇を振ると、再び大風が吹き、今度は大風と共に花びらが珊瑚を襲う。
完全に視界を遮られ、辺りの間隔を失ってしまった。
無数の花びらの中でもがく珊瑚に、紫蘭は銀の刃に化かす扇を、まっすぐ突き伸ばした。
まっすぐ向うその刃は、珊瑚の腹部を深く突き刺した。
かっと珊瑚は目を見開き、紫蘭はその珊瑚に上目で見つめた。
珊瑚は眉間に皺を寄せつつ、渾身の力で再び刀を振ったが、苦もなく紫蘭は刃を避け、数歩引き下がった。
珊瑚は己の身の現状をよく見た。
力ずくで刃を引き抜き、それを紫蘭に投げつけた。
刃はまっすぐ紫蘭に向って飛ぶが、当人はそれを容易く受け取り、
刃先に血がついているにも関らず懐中におさめた。
そして、また珊瑚に背を向ける。
珊瑚は片膝を突き、目前の紫蘭の背を見つめながら、突然クスクスと笑い声をあげた。
そして、背を向ける紫蘭に対して珊瑚は言った。
「なにを笑う?」
「――あんたも、全然大したことないね」
「――――」
「一発で仕留めないんだから……」
紫蘭は何も答えない。
やがて珊瑚は、立っている力も笑う気力も失せ、ついに花畑の中へと倒れた。
犬夜叉、かごめ、七宝は手分けして珊瑚を探している。
犬夜叉がいればすぐに珊瑚に追いつくと思っていたが、当の珊瑚は通った道に毒か薬をまいたのだろう。
犬夜叉の鼻はそういう臭いしか嗅ぎ取れず、珊瑚を見つけることは出来なかった。
三人の騒がしさに弥勒が目を覚ました。
事を察し、傷の痛みを堪えながら、雲母を連ね、一人で珊瑚の行方を追った。
手がかりは無い。ただ雲母の勘に任すしかない。
やがて花畑に来ると、雲母の足が止まった。
風が吹くたびに茎は左右に揺れ、花びらが空気の中を舞う。
茎が揺れるたびに、何か黒い物体が見えた。
それが人の姿にも見える。
「珊瑚!」
まさしく、珊瑚の姿だった。
もはや傷の痛みなど全く感じず、弥勒は無我夢中に珊瑚の傍に駆け寄り、その体を抱きかかえた。
珊瑚の姿を見るや、顔や体に幾箇所も斬り傷がある。
「珊瑚、なぜ行こうとしたんだ……」
弥勒の声を、珊瑚の耳は捉えた。
薄っすら目を開け、弥勒の顔を見つめ、力を絞って声を出した。
「法師様……どうして来たの?」
「決まっている。他の誰よりも、お前のことが一番心配だからだ」
珊瑚の目にまた涙が浮かんだ。
だが、目に涙を浮かべながらも精一杯の笑顔も浮かべている。
そんな苦痛に耐える笑顔で、珊瑚は弥勒にこうも話した。
「法師様、私、ずっと夢見てきたことがあるの……少しだけ、聞いてくれる?」
「何だ?」
「この件が終わって、いつか、きっと、旅も終えたらね……たとえ幻や泡みたいな儚い人生でも――」
「――――」
「法師様と、琥珀と、風向き次第の、風流な日々を送る……」
「――――」
「私も風のように生きて、花のように綺麗に散りたくて……」
「私が必ず、お前の夢を叶えてやる。私と琥珀と、一緒に行こう」
精一杯の笑顔を浮かべる珊瑚を、弥勒は強く、強く抱きしめた。
とても眺めのいい崖の麓に、犬夜叉は一人、夕焼けを眺めていた。
よい景色を眺めながら、いまだ少し残る夏の風に総身を任せる。
やがて背後から人の気配を感じた。
その方を向くと、あの天楼館の頭目であり、踊り子でもあった璋小竹が立っていた。
天楼館の制服ではなく、妖艶な舞衣でもなく、男物の武装姿だ。
右手には小さく“璋小竹”と名が彫られた銀槍を持ち、両腰には小刀を納める刀嚢を下げている。
「お前……」
「天楼館の璋小竹(しょう・ささ)です。昨日は大変、お世話になりました」
小竹は深く頭を下げた。
再び頭をあげ、犬夜叉と目を合わすと、小竹は尋ねた。
「お仲間が風術師の紫蘭の仕業で、重傷を負ったようですが、容態は如何ほどに?」
「――命に別状はない。ただ当分、動かすことが出来ない」
焦るようでもなく、怒りに溢れるでもなく、犬夜叉は冷静さを保っている。
小竹は犬夜叉にこれだけは言っておこうと、槍を地面に突き立て、数歩前に出て、そして語り始めた。
「犬夜叉様、個人的な事ですが言わせてください。
私はこの通り、劉銀竜(りゅう・ぎんりょう)と同じ唐国の生まれ。
あの頃もまた、絶えぬ戦ばかりでした。それゆえに、私の一族は敵に奪われ、
仇を果そうと決めたとき、時に大侠のお父様に救われました。ご察しください、大侠は慈悲があります。
本当は人を殺めることは、一切……」
「もう昔のことだぜ、小竹。信じていても、いつかは必ず裏切られる」
「――――」
「銀竜は裏切り者だ。お前を裏切って、今まで大勢の人間や妖怪を殺した。
お前が勤めてた館の仲間も、そうじゃねぇか」
突然、小竹がどこを見ているのか分からなくなった。
視線が合わない。
当の小竹は、銀竜と共に生きたあの頃の事を脳裏に浮かべた。
璋小竹――以前はそんな名前ではなかった。
三百年前の中国、
有名な武芸人・馮丹華(フェン・ダンフア)と、華麗な舞姫・煌(ホアン)の間に長女が生まれた。
両親はその子に麗玉(リーユィ)と名づけ、それがのちの璋小竹だ。
山岳地帯の村で村人と共に、麗玉は両親と妹の美琳(メイリン)となに不自由なく、平穏に暮らしていた。
丹華の手にはいつも刀があり、両腰には短刀を納める刀嚢を下げ、
得意とする技はただ一つ――必殺・飛翔刀(フェイシアンダオ)。
丹華は二人の娘達にその技と真意を告げ、他の誰にも、飛翔刀の真意を語ることはなかった。
だがまもなく、丹華ははやりの病にかかり、若くして亡くなってしまった。
嘆き悲しみに暮れる妻の煌は、二人の愛娘を連れて村を去り、一族の許へ戻った。
母方の一族は、哀れな母子を受け入れ、手厚に三人を敵から守った。
時に麗玉は美琳と、かつて生まれ育った村へ向って友人達にも逢っていた。
誰にも縛られず、麗玉と美琳はとても幸せな姉妹とよく言われていた。
だがまた悲劇がおとずれる。
突然にも県の捕吏が一族を襲ってきた。
武器を全て奪われた一族は為す術ないまま、その捕吏の手によって全滅してしまった。
幸いにも麗玉だけが生き残った。
一族の亡骸を前に麗玉は泣き叫び、やがてはその泪も枯れ果てた。
麗玉は決意した。
必ず一族の仇を討つ!
父の形見の刀嚢を両腰に携え、馮麗玉から璋小竹へ名を変えて、
正体を隠しながら捕吏を追い、その背後を襲った。
だが当時の麗玉の武芸の技量では、たとえ人間でも手が余る。
捕吏と苦戦する中、やがて麗玉の前に当時の竜舌蘭大魔王が現れた。
竜舌蘭は麗玉を救い、麗玉の素性を既に気づいていながら迷わず一門に招いた。
竜舌蘭一族と共にすることになった麗玉は、やがて心を一転にし、
一族とわずかに殺めてしまった捕吏達の魂を悼んだ。
血と泥に汚れた衣服を棄てて、化粧をし、色鮮やかな衣装や装飾品など身につけるその姿はとても美しく、
その姿を一目した銀竜は麗玉に近づき、やがて深く寵愛した。
その頃の麗玉も、これほど寵愛する銀竜をとても慕っていた。
だが、竜舌蘭やたとえ銀竜にも本名を明かすことはなく、“璋小竹”として通していた。
父や一族の死を忘れつつあったそんな時、突如銀竜は一振りの剣を携え、
竜舌蘭と配下と、あらゆる国へ向い、大戦を始めた。
そして、やがては日本の西国に降り立った。
元々因縁があったそこの一族と決着をつける為、
十年の歳月をかける激闘を施したが、むなしい結果となってしまった。
麗玉はこれ以上の戦はやめるようにと銀竜を説得し続けたが、それもやがては無駄に終わってしまった。
――小竹は銀槍を持ち、そして犬夜叉に告げた。
「劉銀竜は剣について数百年の研鑽を積み、同時に多くの刺客を唐より連れて参りました」
「――――」
「乱心は命取りです、犬夜叉様。闘われる際には、どうかそのお心を乱さぬように」
やがて小竹は犬夜叉の前から姿を消した。
犬夜叉がかごめ達の元へ戻ろうと思った頃は、既に夜になっていた。
暗い獣道を歩く途中、ふと足が止まった。
前方に七宝と流麗がいる。
「犬夜叉」
一番に犬夜叉の存在に気づいたのは七宝だった。つられて流麗が犬夜叉のほうを見た。
「どこにいた?」
「どこにも……すぐ近くにいた」
「ならば一言でも言い残せばいいものを……この現状に、どれ程七宝はお前を案じて探しまわっていたか」
「――ごめんな、七宝」
「犬夜叉に何も起こらねば、それでいい。それより弥勒と珊瑚は大丈夫じゃ。
流麗の“摩訶不思議な力”とやらで、傷は治った」
「本当か……?」
「おうっ。だから、いつまでもそんな顔するなよ!それでは、いつも犬夜叉ではないからなっ!」
犬夜叉は安心した顔で「おう」と、七宝に答えた。
「犬夜叉も戻ってきたことじゃ。かごめも心配しておろうし、早く戻ろう」
流麗と七宝は、もと来た道を歩き始めた。
犬夜叉は少し遅れて、その後につき、戻った。
「LOVER 【夢 幻 泡 影】 伍」 優サマ
小竹はひたすら道を歩き続ける。だがふと、足が止まった。
前に葉蘭と紫蘭が立っている。
「小竹(シアオチュー)様」
「――――」
「旦那様があなたをお待ちでございます」
「是非とも旦那様にお逢いになってくださいませ」
葉蘭と紫蘭の案内で、小竹はある人間の城へやって来た。
物騒にも門は開けっ放しだ。
そこを潜るや、目に映った光景は、おぞましいものだった。
この城の人間達の死体が、あちこちに倒れている。
どこも血の海。まともな歩き場がない。
だが尚も葉蘭と紫蘭は歩み続け、小竹は更に奥へ進んだ。
やがて城の中の蔵書館にきた。
大量の書物や、子供の小指ほどの小さな筆から、大の男並の大きな筆が中央に立て並べられている。
その隅に銀竜がいた。小竹が蔵書館に入ると同時に、こちらを向く。
小竹の表情は硬い。
「大侠(ターシア)、まさかあなたがこの城の人間達を……?」
小竹の問いに、銀竜はすぐに答えた。
「私はただこの城が欲しかっただけだ。人間とは妖怪が前に現ると、すぐに剣を向ける」
小竹は右手の槍を強く握り締め、顔をゆがめた。
だがそんな小竹に、銀竜は更に言う。
「小竹、あの姉弟を倒す為に、私は二百年近くの歳月をかけて、剣について研鑽を積んだのは承知の上だろう」
「――――」
「この二百年、寝る間も惜しみ、あらゆる技をあみ出した。その中の一つに、最も有利な技がある」
「技とは?」
「快剣斬水(クァイジェンザンシュイ)」
「快剣斬水……?」
「快(はや)い剣は、たとえ水も斬ることはできない。相手と八歩以内の距離ならば、確実に敵の急所を突ける技だ」
「――では、始めに犬夜叉と闘った時もその技を?」
「使ったが、咄嗟にあの男は一歩引き下がった。元より犬夜叉と殺生丸を先に殺しても、
流麗が生まれ持った不可思議な力を使えば無意味だ」
銀竜は、余裕に満ちた微笑を浮かべている。
そんな銀竜に小竹が言った。
「天楼の役人を殺し、この城の人間も殺した。仇討ちの為だけに、これ以上の無駄な血は決して流させない」
「――――」
「私は命を賭して、大侠とあの者達との謀を止める覚悟です」
小竹がそう言うと、銀竜は嘲笑した。
「無駄な企てはよせ」
「――――」
「小竹、我が本懐は一門の仇を完全に果すことだ。仇に関わる者も、また戦を邪魔する者も皆、死あるのみ」
「大侠……」
銀竜は暫く小竹を見つめたが、やがて小竹に背を向けた。
背を向けたまま、また銀竜は言った。
「小竹、今日の日付は?」
「間もなく、長月の十七日です」
「私が倭に戻ったのが、先日の十五日だ。その日から四日をかけて、仲間共々あの三人を殺す」
「――法師と退治屋は、葉蘭(イエラン)と紫蘭(ツーラン)の仕業で深手を負っています。
どうか大侠、もとの慈悲の心で闘いをおやめに……人間達にお情けを!」
「闘いに情けは不要だ!」
銀竜が突如振り返り、大きく声を上げた。
小竹を見つめる銀竜の目が、とても鋭く、怖い。
その目に小竹の濡れた灰色の目が、一瞬にして恐怖に凍りついた。
背筋にも、妙な悪寒がはしる。
「もうこれ以上、私の手を阻むことはするな」
九月十七日。
傷は癒えても体力は戻っていない弥勒と珊瑚だが、敵が近くにいるということで、覚悟承知に再び行動に出た。
それよりも銀竜の一味と関れば、どこにも逃げ場はない。
命を懸けた闘い――。
一行の誰もが険しい表情を浮かべる。
やがて、深い林の中に迷い込んだ。
ひたすら前を歩み進めると、突如、林に殺気が満ちた。
目前に、葉蘭と紫蘭が率いる敵がいる。
その敵は皆、鎧兜に身を固め、左に盾、右に弧状の剣を持っていた。
「奴らはもしや、銀竜が放った刺客か!?」
「間違いないよ!みんな、あいつの手下だ!」
かごめに傷をつけさせまいと、犬夜叉は火鼠の衣をかごめの頭から被せた。
「かごめ、絶対俺の傍から離れるな!」
犬夜叉の叫びに、かごめは微かに頷いた。
犬夜叉は鉄砕牙の威力を発し、かごめは矢を射る。
一方の弥勒と珊瑚は、再び現れた葉蘭と紫蘭の因縁の対決を始めた。
弥勒が風穴を開けば葉蘭も風穴を開き、珊瑚は巧みに飛来骨と刀を使いこなして容赦なく紫蘭に攻撃する。
林の中の闘いは、鎮まることはない。
徐々に凄まじくなっていった。
それぞれ刺客と闘っている内に、仲間の姿が見えなくなった。
流麗はたった一人で幾人の刺客を倒していくが、全く数が減らない。
苦戦する流麗の背後から轟音と共に青光りがはしった。
その光は流麗と闘う刺客のみを巻き込み、そして光が治まると同時に妖怪の姿は後もなく消え失せた。
流麗がその方を向くと、そこには殺生丸が立っていた。
殺生丸の必殺・蒼龍破で刺客は消え失せたが、また新手が集まる。
それを目にしながら殺生丸は、冷静を装って流麗に訊ねた。
「姉上、なぜここにいる?」
「――――」
「銀竜は私が倒すと、姉上は西国へ帰ってくれと、あの詰め所で言ったはずだ」
剣を手に、流麗と殺生丸はそれぞれ背を預け、殺生丸は流麗にそう言った。
少しずつ、少しずつ、近づいてくる刺客から目を離さず、流麗は答えた。
「お前こそ……。私は、もう銀竜と闘う必要はないと、以前に言ったぞ」
「――これが最後だ、姉上。故郷へ帰れ」
「いや帰らぬ!」
「私はもう、一族の死を見たくはないのだ」
剣や槍を連ね、ついに敵が襲ってきた。
両手で剣の柄を握り、流麗は殺生丸に叫んだ。
「私がこの闘いで、こんな場所で死ぬものか!」
流麗と殺生丸は同時に、立ち向かってくる敵を一斉に斬り捨てた。
この林の中にいる敵を全て倒すまで、二人は激戦を繰り広げた。
茫茫の草叢の中に隠れ、りんと邪見は殺生丸の帰りを待つ。
何者にも劣らぬ殺生丸だが、刻一刻と時間が過ぎても戻ってこず、次第にりんが不安を見始めた。
「どうしよう、邪見様。殺生丸様、戻ってこないよ。まさか、何かあったんじゃ……」
「どあほう!縁起でもない事を言うなっ!天下の殺生丸様だぞ、負けるはずがなかろう!」
邪見は相変わらずりんをつっこむが、当の邪見も本当の所は殺生丸をとても案じている。
何せ敵は、偉大で優秀な殺生丸の一族を倒したやつら。
殺生丸や、流麗が勝つとは限らない。
邪見がぶんぶんと首を左右に振るった。
そんな事、思っては駄目だ。
せめて心配性のりんに、楽しい話をして気を紛らわせようと、邪見は少し頭を捻った。
一つ面白い話のネタが浮かび、それを口に出して言おうとした時、
頭上からキリキリと何かを引く音が聴こえた。
その瞬間、頭上から幾本もの矢が、邪見とりんを襲ってきた。
矢は着物を掠り、顔の横を間一髪通り過ぎ、地面に突き立った。
頭上を見上げると、二十は超える敵が、樹に剣を突き立て、その刃の上に総身を任し、次々と弓を放つ。
既に頭上を囲まれては逃げ切れない。
その時、わずかの刀が鋭い刃を向けて物陰から飛んできた。
刀は全て刺客の急所を突き、その一撃にあらかたの刺客はそのまま地面へ落下した。
「是誰!?」
邪見とりんの前に、その人が立った。
長い銀槍を持ち、両腰にその刀を納める刀嚢を下げている。
「那、是璋小竹!」
正しく小竹だ。
まさか小竹が敵を庇うという動作に、敵の表情は強張った。
やがてその手に槍や剣を持って地上におり、小竹を囲んだ。
「大姐、好快的飛翔刀!可是、為何把刀転向我們?」
小竹は邪見とりんを背後に回したまま、前の刺客に叫んだ。
「愚蠢的人們、狠狠地斬!!!」
小竹がそう叫ぶと同時に、怒濤の如く前の敵に目掛けて銀槍を大きく振るった。
身の丈以上にもある槍に関らず、見事な槍さばき。邪見もりんも驚かされる。
刺客も小竹に反撃するが、それも空しく、やがて小竹の手によって全て倒された。
雑木林の中は冷たい冷気に覆われ、吐く息は白い。
だが、小竹の額には幾粒も脂汗が浮かび、頬へつたっていた。
一度周囲を見渡した後、小竹は邪見とりんと見合わした。
だが、かすかな風を斬る音が聴こえた。
ある一点を見ると、無数の血のついた短刀が、こちらへ向って来る。
「飛翔刀!」
小竹は素早く槍を持ち直し、槍を用いてその刀を薙ぎ払った。
「――銀竜大侠!」
そこから二十歩離れた所で、銀竜が立っていた。
あの刀は正しく小竹が腰に携えているのと同じもの。
「もう私の手を阻むなと言ったのに……果たしてまた敵の方につくとは」
低く重く、銀竜が言い、小竹は答えた。
「命を賭して大侠達の謀を止めると申したはずです」
ふんと銀竜は鼻で笑い、小竹に告げた。
「どうもここは、お前を見逃すにはいれぬ」
「――――」
「だが小竹、本当にその方を案ずるのなら、すぐさま逃がせ。できるだけ遠くへ」
何と銀竜の口からそう言うとは、小竹はとても不思議に思えた。
だが迷っている暇はない。小竹はちらりと背後を向き、邪見とりんに言った。
「逃げなさい」
即座に邪見はりんの袖の引き、そこを離れようとした。
だが、その前にりんは、恐れ一つない、穏やか表情を浮かべて小竹に一つ言い残した。
「小竹さん、絶対に負けないでね!」
そう告げると、やがて邪見に手を引かれて、りんはその場を離れた。
「小竹(シアオチュー)」
「――――」
「もしもこれに私が勝てば、私の願いを叶えると約束をしてくれるか」
銀竜の願いなど知る由もないが、小竹は約束をすると、銀竜と激しく火花を散らした。
雑木林の闘いは終わらない。
息を殺し、犬夜叉とかごめは樹と樹の間をすり抜け、周囲を見渡す。
果たして、前方に十人足らずの刺客が立っている。
向こうも既にこちらの存在に気づいている。
犬夜叉は鉄砕牙を強く握り締め、横に立つかごめも矢壺から一本の矢を取り出し、狙いを定める。
するとその時、何か硬い物がかごめの背を強く押した。
あまりの勢いに、かごめは数歩前へ飛び出し、そして倒れた。
すぐに起き上がろうとしたが、幾人か敵は槍を用いて、かごめを右肩を強く押しつけ、
更に別の方からは槍と剣の刃を首元に突きつけた。
「かごめ!」
犬夜叉は素早く鉄砕牙を振るったが、敵は手持ちの剣で易々と鉄砕牙を弾いた。
その時の力があまりにも強く、鉄砕牙は犬夜叉の手から離れ、そして敵は一斉に犬夜叉を押さえつけた。
そして太い綱と鋭い鋼線と、黒く分厚い布を取り出した。
犬夜叉の両腕を後ろに回して綱で縛り、手首をその鋼線で何重も巻きつけ、
更に黒く分厚い布で犬夜叉の目を覆い隠した。
「野郎離せ……!離しやがれ!!!」
犬夜叉の力では到底破ることの出来ない凄まじい力。
この犬夜叉の叫びは、離れた流麗と殺生丸の耳に届いた。
目前の敵は、もはや眼中になく、流麗はその場を放ってその声の方へ走った。
その場に来ると、犬夜叉とかごめが敵に捕われている。
「犬夜叉!」
流麗はかごめが落とした弓と矢壺を手に取って矢壺から矢を取り出し、そして矢を放った。
幾度か矢を放った所、その矢は全て敵を射抜いた。
矢がある限り流麗は放つつもりにいたが、刺客が流麗に対して一斉に剣を投げた。
太い樹を切り倒し、目にも留まらぬ速さで剣は向ってくる。
自信の腰にある妖剣で、刃向かう全ての剣を弾くことはできない。
身軽な流麗は高く跳躍をしてそれを避けた。
その隙に、刺客は犬夜叉とかごめを連れたまま姿を消していた。
やがて林の闘いは終えた。
後に合流した弥勒、珊瑚、七宝に、流麗は犬夜叉とかごめの事を正直に話した。
もうすぐ太陽が西に沈む。
また痛んだ体をひとまず休ませようと、すぐ近くにあった村に宿を貸すよう弥勒は頼み込んだ。
弥勒や珊瑚や、その他、りんの様子を見て、村人達は拒むわけにはいかない。
貧しい村ながらも精一杯のおもてなしをしてくれた。
その村のはずれでは、流麗と殺生丸が何か話し合っていた。
「殺生丸、少しの間だけ留守を頼む」
「私にこの村に残れと……?一体どこへ行くか、姉上」
「――刀々斎の所だ」
「何のために?」
しつこく迫る殺生丸に、流麗はついに明かした。
「明日、犬夜叉とかごめを救い、銀竜と決着をつける」
「――――」
「せめて刀々斎に、その事を告げようと……」
「――――」
「安心せよ、帰りは遅くならない」
流麗の姿がやがて闇夜の中に溶け、消えた。
前に葉蘭と紫蘭が立っている。
「小竹(シアオチュー)様」
「――――」
「旦那様があなたをお待ちでございます」
「是非とも旦那様にお逢いになってくださいませ」
葉蘭と紫蘭の案内で、小竹はある人間の城へやって来た。
物騒にも門は開けっ放しだ。
そこを潜るや、目に映った光景は、おぞましいものだった。
この城の人間達の死体が、あちこちに倒れている。
どこも血の海。まともな歩き場がない。
だが尚も葉蘭と紫蘭は歩み続け、小竹は更に奥へ進んだ。
やがて城の中の蔵書館にきた。
大量の書物や、子供の小指ほどの小さな筆から、大の男並の大きな筆が中央に立て並べられている。
その隅に銀竜がいた。小竹が蔵書館に入ると同時に、こちらを向く。
小竹の表情は硬い。
「大侠(ターシア)、まさかあなたがこの城の人間達を……?」
小竹の問いに、銀竜はすぐに答えた。
「私はただこの城が欲しかっただけだ。人間とは妖怪が前に現ると、すぐに剣を向ける」
小竹は右手の槍を強く握り締め、顔をゆがめた。
だがそんな小竹に、銀竜は更に言う。
「小竹、あの姉弟を倒す為に、私は二百年近くの歳月をかけて、剣について研鑽を積んだのは承知の上だろう」
「――――」
「この二百年、寝る間も惜しみ、あらゆる技をあみ出した。その中の一つに、最も有利な技がある」
「技とは?」
「快剣斬水(クァイジェンザンシュイ)」
「快剣斬水……?」
「快(はや)い剣は、たとえ水も斬ることはできない。相手と八歩以内の距離ならば、確実に敵の急所を突ける技だ」
「――では、始めに犬夜叉と闘った時もその技を?」
「使ったが、咄嗟にあの男は一歩引き下がった。元より犬夜叉と殺生丸を先に殺しても、
流麗が生まれ持った不可思議な力を使えば無意味だ」
銀竜は、余裕に満ちた微笑を浮かべている。
そんな銀竜に小竹が言った。
「天楼の役人を殺し、この城の人間も殺した。仇討ちの為だけに、これ以上の無駄な血は決して流させない」
「――――」
「私は命を賭して、大侠とあの者達との謀を止める覚悟です」
小竹がそう言うと、銀竜は嘲笑した。
「無駄な企てはよせ」
「――――」
「小竹、我が本懐は一門の仇を完全に果すことだ。仇に関わる者も、また戦を邪魔する者も皆、死あるのみ」
「大侠……」
銀竜は暫く小竹を見つめたが、やがて小竹に背を向けた。
背を向けたまま、また銀竜は言った。
「小竹、今日の日付は?」
「間もなく、長月の十七日です」
「私が倭に戻ったのが、先日の十五日だ。その日から四日をかけて、仲間共々あの三人を殺す」
「――法師と退治屋は、葉蘭(イエラン)と紫蘭(ツーラン)の仕業で深手を負っています。
どうか大侠、もとの慈悲の心で闘いをおやめに……人間達にお情けを!」
「闘いに情けは不要だ!」
銀竜が突如振り返り、大きく声を上げた。
小竹を見つめる銀竜の目が、とても鋭く、怖い。
その目に小竹の濡れた灰色の目が、一瞬にして恐怖に凍りついた。
背筋にも、妙な悪寒がはしる。
「もうこれ以上、私の手を阻むことはするな」
九月十七日。
傷は癒えても体力は戻っていない弥勒と珊瑚だが、敵が近くにいるということで、覚悟承知に再び行動に出た。
それよりも銀竜の一味と関れば、どこにも逃げ場はない。
命を懸けた闘い――。
一行の誰もが険しい表情を浮かべる。
やがて、深い林の中に迷い込んだ。
ひたすら前を歩み進めると、突如、林に殺気が満ちた。
目前に、葉蘭と紫蘭が率いる敵がいる。
その敵は皆、鎧兜に身を固め、左に盾、右に弧状の剣を持っていた。
「奴らはもしや、銀竜が放った刺客か!?」
「間違いないよ!みんな、あいつの手下だ!」
かごめに傷をつけさせまいと、犬夜叉は火鼠の衣をかごめの頭から被せた。
「かごめ、絶対俺の傍から離れるな!」
犬夜叉の叫びに、かごめは微かに頷いた。
犬夜叉は鉄砕牙の威力を発し、かごめは矢を射る。
一方の弥勒と珊瑚は、再び現れた葉蘭と紫蘭の因縁の対決を始めた。
弥勒が風穴を開けば葉蘭も風穴を開き、珊瑚は巧みに飛来骨と刀を使いこなして容赦なく紫蘭に攻撃する。
林の中の闘いは、鎮まることはない。
徐々に凄まじくなっていった。
それぞれ刺客と闘っている内に、仲間の姿が見えなくなった。
流麗はたった一人で幾人の刺客を倒していくが、全く数が減らない。
苦戦する流麗の背後から轟音と共に青光りがはしった。
その光は流麗と闘う刺客のみを巻き込み、そして光が治まると同時に妖怪の姿は後もなく消え失せた。
流麗がその方を向くと、そこには殺生丸が立っていた。
殺生丸の必殺・蒼龍破で刺客は消え失せたが、また新手が集まる。
それを目にしながら殺生丸は、冷静を装って流麗に訊ねた。
「姉上、なぜここにいる?」
「――――」
「銀竜は私が倒すと、姉上は西国へ帰ってくれと、あの詰め所で言ったはずだ」
剣を手に、流麗と殺生丸はそれぞれ背を預け、殺生丸は流麗にそう言った。
少しずつ、少しずつ、近づいてくる刺客から目を離さず、流麗は答えた。
「お前こそ……。私は、もう銀竜と闘う必要はないと、以前に言ったぞ」
「――これが最後だ、姉上。故郷へ帰れ」
「いや帰らぬ!」
「私はもう、一族の死を見たくはないのだ」
剣や槍を連ね、ついに敵が襲ってきた。
両手で剣の柄を握り、流麗は殺生丸に叫んだ。
「私がこの闘いで、こんな場所で死ぬものか!」
流麗と殺生丸は同時に、立ち向かってくる敵を一斉に斬り捨てた。
この林の中にいる敵を全て倒すまで、二人は激戦を繰り広げた。
茫茫の草叢の中に隠れ、りんと邪見は殺生丸の帰りを待つ。
何者にも劣らぬ殺生丸だが、刻一刻と時間が過ぎても戻ってこず、次第にりんが不安を見始めた。
「どうしよう、邪見様。殺生丸様、戻ってこないよ。まさか、何かあったんじゃ……」
「どあほう!縁起でもない事を言うなっ!天下の殺生丸様だぞ、負けるはずがなかろう!」
邪見は相変わらずりんをつっこむが、当の邪見も本当の所は殺生丸をとても案じている。
何せ敵は、偉大で優秀な殺生丸の一族を倒したやつら。
殺生丸や、流麗が勝つとは限らない。
邪見がぶんぶんと首を左右に振るった。
そんな事、思っては駄目だ。
せめて心配性のりんに、楽しい話をして気を紛らわせようと、邪見は少し頭を捻った。
一つ面白い話のネタが浮かび、それを口に出して言おうとした時、
頭上からキリキリと何かを引く音が聴こえた。
その瞬間、頭上から幾本もの矢が、邪見とりんを襲ってきた。
矢は着物を掠り、顔の横を間一髪通り過ぎ、地面に突き立った。
頭上を見上げると、二十は超える敵が、樹に剣を突き立て、その刃の上に総身を任し、次々と弓を放つ。
既に頭上を囲まれては逃げ切れない。
その時、わずかの刀が鋭い刃を向けて物陰から飛んできた。
刀は全て刺客の急所を突き、その一撃にあらかたの刺客はそのまま地面へ落下した。
「是誰!?」
邪見とりんの前に、その人が立った。
長い銀槍を持ち、両腰にその刀を納める刀嚢を下げている。
「那、是璋小竹!」
正しく小竹だ。
まさか小竹が敵を庇うという動作に、敵の表情は強張った。
やがてその手に槍や剣を持って地上におり、小竹を囲んだ。
「大姐、好快的飛翔刀!可是、為何把刀転向我們?」
小竹は邪見とりんを背後に回したまま、前の刺客に叫んだ。
「愚蠢的人們、狠狠地斬!!!」
小竹がそう叫ぶと同時に、怒濤の如く前の敵に目掛けて銀槍を大きく振るった。
身の丈以上にもある槍に関らず、見事な槍さばき。邪見もりんも驚かされる。
刺客も小竹に反撃するが、それも空しく、やがて小竹の手によって全て倒された。
雑木林の中は冷たい冷気に覆われ、吐く息は白い。
だが、小竹の額には幾粒も脂汗が浮かび、頬へつたっていた。
一度周囲を見渡した後、小竹は邪見とりんと見合わした。
だが、かすかな風を斬る音が聴こえた。
ある一点を見ると、無数の血のついた短刀が、こちらへ向って来る。
「飛翔刀!」
小竹は素早く槍を持ち直し、槍を用いてその刀を薙ぎ払った。
「――銀竜大侠!」
そこから二十歩離れた所で、銀竜が立っていた。
あの刀は正しく小竹が腰に携えているのと同じもの。
「もう私の手を阻むなと言ったのに……果たしてまた敵の方につくとは」
低く重く、銀竜が言い、小竹は答えた。
「命を賭して大侠達の謀を止めると申したはずです」
ふんと銀竜は鼻で笑い、小竹に告げた。
「どうもここは、お前を見逃すにはいれぬ」
「――――」
「だが小竹、本当にその方を案ずるのなら、すぐさま逃がせ。できるだけ遠くへ」
何と銀竜の口からそう言うとは、小竹はとても不思議に思えた。
だが迷っている暇はない。小竹はちらりと背後を向き、邪見とりんに言った。
「逃げなさい」
即座に邪見はりんの袖の引き、そこを離れようとした。
だが、その前にりんは、恐れ一つない、穏やか表情を浮かべて小竹に一つ言い残した。
「小竹さん、絶対に負けないでね!」
そう告げると、やがて邪見に手を引かれて、りんはその場を離れた。
「小竹(シアオチュー)」
「――――」
「もしもこれに私が勝てば、私の願いを叶えると約束をしてくれるか」
銀竜の願いなど知る由もないが、小竹は約束をすると、銀竜と激しく火花を散らした。
雑木林の闘いは終わらない。
息を殺し、犬夜叉とかごめは樹と樹の間をすり抜け、周囲を見渡す。
果たして、前方に十人足らずの刺客が立っている。
向こうも既にこちらの存在に気づいている。
犬夜叉は鉄砕牙を強く握り締め、横に立つかごめも矢壺から一本の矢を取り出し、狙いを定める。
するとその時、何か硬い物がかごめの背を強く押した。
あまりの勢いに、かごめは数歩前へ飛び出し、そして倒れた。
すぐに起き上がろうとしたが、幾人か敵は槍を用いて、かごめを右肩を強く押しつけ、
更に別の方からは槍と剣の刃を首元に突きつけた。
「かごめ!」
犬夜叉は素早く鉄砕牙を振るったが、敵は手持ちの剣で易々と鉄砕牙を弾いた。
その時の力があまりにも強く、鉄砕牙は犬夜叉の手から離れ、そして敵は一斉に犬夜叉を押さえつけた。
そして太い綱と鋭い鋼線と、黒く分厚い布を取り出した。
犬夜叉の両腕を後ろに回して綱で縛り、手首をその鋼線で何重も巻きつけ、
更に黒く分厚い布で犬夜叉の目を覆い隠した。
「野郎離せ……!離しやがれ!!!」
犬夜叉の力では到底破ることの出来ない凄まじい力。
この犬夜叉の叫びは、離れた流麗と殺生丸の耳に届いた。
目前の敵は、もはや眼中になく、流麗はその場を放ってその声の方へ走った。
その場に来ると、犬夜叉とかごめが敵に捕われている。
「犬夜叉!」
流麗はかごめが落とした弓と矢壺を手に取って矢壺から矢を取り出し、そして矢を放った。
幾度か矢を放った所、その矢は全て敵を射抜いた。
矢がある限り流麗は放つつもりにいたが、刺客が流麗に対して一斉に剣を投げた。
太い樹を切り倒し、目にも留まらぬ速さで剣は向ってくる。
自信の腰にある妖剣で、刃向かう全ての剣を弾くことはできない。
身軽な流麗は高く跳躍をしてそれを避けた。
その隙に、刺客は犬夜叉とかごめを連れたまま姿を消していた。
やがて林の闘いは終えた。
後に合流した弥勒、珊瑚、七宝に、流麗は犬夜叉とかごめの事を正直に話した。
もうすぐ太陽が西に沈む。
また痛んだ体をひとまず休ませようと、すぐ近くにあった村に宿を貸すよう弥勒は頼み込んだ。
弥勒や珊瑚や、その他、りんの様子を見て、村人達は拒むわけにはいかない。
貧しい村ながらも精一杯のおもてなしをしてくれた。
その村のはずれでは、流麗と殺生丸が何か話し合っていた。
「殺生丸、少しの間だけ留守を頼む」
「私にこの村に残れと……?一体どこへ行くか、姉上」
「――刀々斎の所だ」
「何のために?」
しつこく迫る殺生丸に、流麗はついに明かした。
「明日、犬夜叉とかごめを救い、銀竜と決着をつける」
「――――」
「せめて刀々斎に、その事を告げようと……」
「――――」
「安心せよ、帰りは遅くならない」
流麗の姿がやがて闇夜の中に溶け、消えた。
「LOVER 【夢 幻 泡 影】 陸」 優サマ
亡(むな)しくて……
恋(くふ)しくて……
つい想ってしまう つい想い出してしまう
想うほどに哀しい 想うほどに愛おしい
やがて想う想いに暮れる心は闇に沈み
やがて想う想いに暮れる数多の涙の数
先日、夫の骨を故郷の出雲の土と一緒に、
妖怪の墓場とされる“この世とあの世の境”に葬った。
たとえ人間であっても、大親友という仲であった十六夜も、
生まれたばかりの息子を抱いて武蔵へ旅立った――。
夫にせよ家族にせよ、常に傍にいることが当たり前だった。
ゆえに、愛する人を失うということがこんなにも苦しいものとは知らなかった。
誰とも逢う気がない。
これまで欠かせなかった楽や書もできない。
夜、布団に入り、目を閉じり眠りにつくが、目に愛するひとが映って全く眠れない。
そんな日々が五年も続いた。
――ある冬の年、流麗は夫の故郷である出雲へ向かった。
胸に瑠璃の小刀を飾り、長い髪には、昔夫から貰ったつげ櫛を挿す。
細身の体に白くて分厚い毛皮を羽織るが、海から吹く風が強く冷たく、とても寒い。
冷たい空気を鼻で吸い、口から濃い白い息を吐きながら、流麗は大海原を見つめながら波打ち際を歩く。
ふと、絹のような柔らかい白銀の髪の毛を触った。
ない。
ここに挿していた櫛がない。
急に胸の鼓動が激しくなり、全身の血の気が失せ、顔を青ざめながら流麗は地を這って櫛を探した。
今まで歩いてきた道なき道を辿って砂をかき分けて探すが、やはり見つからない。
次第に冷たい風に体温は奪われ、手から徐々に、氷のように冷たくなっていく。
「おい、どうかしたか?」
地を這う流麗に、ある中年の男が向こうから呼びかけた。
やがて砂浜の上におり、流麗の前に立った。
「何をしている?」
「――櫛を……」
「櫛?」
「櫛を落としてしまったのです……夫から頂いた、大切なもの……」
流麗は砂浜から目を離さない。
「分かった、余も探そう。とにかく落ち着けよ。慌てると、何も見えなくなるぞ」
男は屈んで流麗にそう告げるが、それでも流麗は男と目を合わさない。
やがて男は砂浜の砂を丁寧にかき分け、櫛を探した。
だがやはり、櫛はない。
男は沓を履いたまま波打ち際に立ち、腰を屈め、わずかな波に打たれながら櫛を探した。
そしてまもなく――
「おう」
男が声を上げた。
手に持ち、着物で泥を拭うと、それを流麗に見せた。
正しく捜し求めていた櫛だ。
流麗は砂まみれの手で男から櫛を受け取った。
青ざめた表情が安堵に変わった。両手で櫛を握り、流麗は目に涙を浮かべる。
やがて、漸く流麗はその男の顔を見た。
「まあ、斉資様」
まさしく斉資だった。
斉資は流麗と目を合うと微かな笑みを浮かべ、そして横の大海原を眺めながら言った。
「ここはヨソラ貴公子の居場所じゃ。よく姉と来ては得意の琵琶を奏で、
不仲であった兄と高麗の姫を賭けた決闘をしていたのもここじゃ」
「美しい所ですね。私も以前、よく彼に手を引かれてここへ参りました。――斉資様」
流麗は言った。
「今日は久方ぶりに出雲へ参りましたが、あの頃を想う度に胸が強く締め付けられます」
「――――」
「このわずかに悟りました。私にはもう、全てをやり直すということは不可能のようです。
夫と一族の想いが捨てきれず、傍を離れられない」
美しい想い出に交えて、愛する人の死に対するこの苦しみを流麗は訴えた。
ほんの暫く海風に浴びて、そして斉資は答えた。
「それでもひとは、倒れたままにはいられない」
「――――」
「流麗、誰でもやり直せるのだ。ただそれに、多くの時間が必要なだけぞよ」
「――――」
「たとえ漆黒の闇が続いても、朝は必ず来る」
海からの冷たい風は止まない。
流麗は冷え切った手で櫛を握り、逆に優しい暖かい微笑みを浮かべて言った。
「斉資様、此度は斉資様のお蔭です。近々お礼物を……
今日はせめて、心からお礼に代えさせていただきます」
――蒼く眩しい月の光が、中まで射しこむ。
壁に幾本も立て並べた銀の刃が月光に反射し、その光が流麗の顔面を照らした。
あまりの眩しさに、漸く流麗は目を覚ました。
「起きたかよ、流麗様よ」
流麗の剣を研ぐ刀々斎が流麗の目覚めに気づき、声をかけた。
「久々に来たかと思ったら、急に死んだように寝るものな」
流麗は目を見開け、辺りの光景をよく見た。
ぼろ家に老人の刀鍛冶が、いつも通り仕事をしている。
先程目に映ったものが夢と分かると、流麗は大きく息を吐き、そしてその身を起こした。
「きっと闘いばかりで疲れているんだ。ここに来たからには、寛げよ」
夜空の下で、きまって流麗は一族の弔いに笛を吹く。曲は、魂之舞。
それを耳にしながら刀々斎は星を観る。
――と、ふと笛がやんだ。
刀々斎の視線は、流麗に向けられた。
「どうした?」
「恋しくて……」
「恋しい?」
「ヨソラの長い黒髪も、顔の傷も、私を抱きしめる腕の強さも一緒に楽を奏でたことも、
口を重ねたことも全て恋しいの」
「――――」
「彼は始めから出雲の公子でも王でもなかった。全て自らの一存で如月や私の為に闘い、尽くし、
全てに命を懸けたの。私はヨソラがいたからこそ、人を愛するという意味を知ったのよ。
その、ヨソラがいないだけで、こんなにも気持ちが苦しいなんて……不思議ね」
刀々斎は答えない。
暫く沈黙が続き――やがて流麗は手に持つ竜笛を着物と鎧の隙間に挿し、また体勢を整えた。
まだ刀々斎と話したい事が山のようにあるが、やはり時間がない。
流麗はついに本題に入った。
「今日、銀竜が放った刺客と闘った。当人も、すぐ近くにいたらしい」
「うむ」
「その刺客に、犬夜叉とかごめが捕らわれた」
「――――」
「剣よりも弓が有利と思って試みけれど、無駄に終わってしまった。
明朝、犬夜叉とかごめを助けて銀竜と決着をつける。
数は多い方がよいから――爺も、闘いに参戦せよ」
「流麗……」
「この後も会わねばならない者がいる。行かなければ……」
長年共にしてきた自らの牙で打った剣を腰に挿し、
絶大な力を持つ神剣を握り、流麗は立ち上がった。
「爺、夫(つま)の剣は、どうかあの場所へ捧げ、今のことは、冥加が戻ったら伝えて」
九月十八日。
ついに銀竜と決着をつけるこの日、とても奇怪なことが起きた。
夏から秋へ移り変わる頃なのに、牡丹雪が降っている。
気温もまるで低く、吐く息も白い。
だが幻想的な景色とは逆に、満ち溢れた殺気がそこにはある。
銀竜の居場所は人間の城と聞いた。
吹き荒れる雪とともに風にのって流れる匂いを頼りに、ついにその城に一行は辿りついた。
「一体何の厭魅か……雪が降るとは」
刀々斎の肩の上の冥加が言った。
「いかにも決闘にふさわしいじゃない」
冥加に、珊瑚がそう答えた。
前の景色を見つめながら意を決し、ついに、一行は動き出した。
城からは新手が群をなしてくる。
その中に葉蘭と紫蘭も混じり、弥勒と珊瑚の前に立ちはだかった。
手持ちの武器を握り弥勒と珊瑚は、葉蘭、紫蘭と再び激しく火花を散らした。
一方の犬夜叉は、ただ一人、牢獄にとじ込められている。
だがそれから間もなく、犬夜叉の耳はある足音は捉えた。
その音が牢の前で止んだ。戸を開け、その者は牢の中へ入ってきた。
そして犬夜叉の腕を強く掴んで乱暴にひき立たすと、犬夜叉を牢の外へ連れ出した。
逃がすのではない。
打ち首にするのだ。
その者は、犬夜叉の背後に立つと、乱暴に屈ませた。
「お前、小竹だろう」
ためらいもなく犬夜叉が言った。
「牢に来た時から分かっていた……俺の鼻は敏感だからな」
黒く分厚い布で目を覆い隠され、犬夜叉にも破れぬ綱で腕を縛られ、
手首も鋼線で何重にも巻きつけられている。
そのせいで、未だ手首から血が滴り落ちる。
だが、もう痛みすら感じない。
犬夜叉は抵抗する気もなく、ただ俯き、小竹に言う。
「小竹、俺を殺すのは構わねぇ。命なんて、全然惜しくもねぇからな」
「――――」
「俺とお前は敵同士だ。お前は、必然的に銀竜の肩を持つ。
敵同士なら、武器を持って闘い、どっちかが死ぬんだ」
「――そうね」
それまで黙っていた小竹が答えた。
「もしもこれが逆の立場なら、あなたも私を殺している。
きっとこんな風に、容赦はなく……」
遂に小竹は剣を抜き、刃先を犬夜叉の首筋に突きつけた。
だが、死ぬことに対して恐れぬ犬夜叉の背後を見て、ふと小竹は思いとどまった。
――生きていれば必ず死ぬ。忘れるんだ、いいな。
父親や、妹や、母方の一族を亡くして長い年が経つというのに、
あの時の光景と、銀竜の一言は忘れられない。
小竹は眉間に皺を寄せ、歯も食いしばりながら、ついに剣を振るった。
その瞬間、犬夜叉の体に自由が利いた。
小竹が断ち切ったのは、犬夜叉の腕を縛る綱と、手首を縛る鋼線。
小竹は剣を床に置き、犬夜叉の目を覆う布を解いた。
「やはりあなたを殺すことはできない」
「――銀竜を裏切るんじゃねぇのか?」
小竹はまっすぐ犬夜叉を見つめ、そっと頬を撫でた。
「私もあなたと同じ半妖……同じものを殺すことは、とてもできない」
「――――」
「どうか再びこれを。外では、皆が闘っています」
小竹は錆びた鉄砕牙を犬夜叉に渡した。
正しく、あの林で手放した鉄砕牙。
犬夜叉は、そっとその手で鉄砕牙を受け取った。
「共に、闘いましょう」
その後、無事にかごめと出会うことが出来た。
怪我などはなく、犬夜叉はかごめを連れ、小竹と刺客と闘った。
大勢の敵と一度に刃を交え、流麗は闘う。
だが刺客の圧倒的な力量に流麗が負けた。
素早く刺客が止めをさそうとした一瞬の時――ある女が突如、流麗の前に立った。
手持ちの氷の槍で刺客を倒し、集まる新手もその女の供の手によって倒された。
流麗がその者の姿を見ると、あっと驚いた。
前に立つのは、まぎれもない豹猫四天王の冬嵐姉弟だ。
「お前達……」
「あいつらから、女王陛下の援護をと俺達は頼まれた」
「みな、流麗様のお帰りをお待ちしています」
秋嵐と春嵐がそう言ったとき、再び刺客が集まった。
「お前達は、私の指示のとおりに」
冬嵐の命に、三人の妹弟は即座にそれぞれの所へ向った。
流麗は腰に下げる鞘から自らの牙の剣を抜き、冬嵐と背を預けた。
「流麗、彼奴らは私に任せなさい。あなたは早く、銀竜の許へ!」
冬嵐の命令に、右を向けば春嵐は敵の攻撃を交わし、反撃しながら殺生丸の方へ向い、
左を向けば、すでに夏嵐と秋嵐が弥勒と珊瑚の援護をする。
かつては敵同士だったのが、今では姉妹のようであり、
その冬嵐を一人にさせるわけにはいかなかった。
「一族を殺した敵に、人ながら友人までも殺された。同じ目を為してはならない!」
そう言ったと同時に、ついに刺客が群をなして襲ってきた。
鋭い刃を容赦なく振るい、その壮絶な攻撃を手に持つ武器を用いて受け止めながら、冬嵐は更に言った。
「私達などよりも、大切なのは自分です。今を無駄にしてはいけません!」
冬嵐の勢いに押され、流麗は悔やみながら冬嵐にその場を任せ、ついに銀竜の許へ走った。
やがて流麗は最上階の部屋に辿りつくと、果たして銀竜がいた。
強く剣を握り、流麗は、銀竜と向かい合う。
「やっと来たか、流麗」
銀竜はあることに気がついた。
「流麗、背の神剣はどうした?」
「――元の持ち主に返した。私を守る為に、
夫が天照神と闘って手にした神剣は、本来この世の者の持つべきものではない」
ふんと銀竜は嘲笑した。
剣を抜くと足を大きく一歩踏み出し、ついに流麗と決戦を始めた。
恋(くふ)しくて……
つい想ってしまう つい想い出してしまう
想うほどに哀しい 想うほどに愛おしい
やがて想う想いに暮れる心は闇に沈み
やがて想う想いに暮れる数多の涙の数
先日、夫の骨を故郷の出雲の土と一緒に、
妖怪の墓場とされる“この世とあの世の境”に葬った。
たとえ人間であっても、大親友という仲であった十六夜も、
生まれたばかりの息子を抱いて武蔵へ旅立った――。
夫にせよ家族にせよ、常に傍にいることが当たり前だった。
ゆえに、愛する人を失うということがこんなにも苦しいものとは知らなかった。
誰とも逢う気がない。
これまで欠かせなかった楽や書もできない。
夜、布団に入り、目を閉じり眠りにつくが、目に愛するひとが映って全く眠れない。
そんな日々が五年も続いた。
――ある冬の年、流麗は夫の故郷である出雲へ向かった。
胸に瑠璃の小刀を飾り、長い髪には、昔夫から貰ったつげ櫛を挿す。
細身の体に白くて分厚い毛皮を羽織るが、海から吹く風が強く冷たく、とても寒い。
冷たい空気を鼻で吸い、口から濃い白い息を吐きながら、流麗は大海原を見つめながら波打ち際を歩く。
ふと、絹のような柔らかい白銀の髪の毛を触った。
ない。
ここに挿していた櫛がない。
急に胸の鼓動が激しくなり、全身の血の気が失せ、顔を青ざめながら流麗は地を這って櫛を探した。
今まで歩いてきた道なき道を辿って砂をかき分けて探すが、やはり見つからない。
次第に冷たい風に体温は奪われ、手から徐々に、氷のように冷たくなっていく。
「おい、どうかしたか?」
地を這う流麗に、ある中年の男が向こうから呼びかけた。
やがて砂浜の上におり、流麗の前に立った。
「何をしている?」
「――櫛を……」
「櫛?」
「櫛を落としてしまったのです……夫から頂いた、大切なもの……」
流麗は砂浜から目を離さない。
「分かった、余も探そう。とにかく落ち着けよ。慌てると、何も見えなくなるぞ」
男は屈んで流麗にそう告げるが、それでも流麗は男と目を合わさない。
やがて男は砂浜の砂を丁寧にかき分け、櫛を探した。
だがやはり、櫛はない。
男は沓を履いたまま波打ち際に立ち、腰を屈め、わずかな波に打たれながら櫛を探した。
そしてまもなく――
「おう」
男が声を上げた。
手に持ち、着物で泥を拭うと、それを流麗に見せた。
正しく捜し求めていた櫛だ。
流麗は砂まみれの手で男から櫛を受け取った。
青ざめた表情が安堵に変わった。両手で櫛を握り、流麗は目に涙を浮かべる。
やがて、漸く流麗はその男の顔を見た。
「まあ、斉資様」
まさしく斉資だった。
斉資は流麗と目を合うと微かな笑みを浮かべ、そして横の大海原を眺めながら言った。
「ここはヨソラ貴公子の居場所じゃ。よく姉と来ては得意の琵琶を奏で、
不仲であった兄と高麗の姫を賭けた決闘をしていたのもここじゃ」
「美しい所ですね。私も以前、よく彼に手を引かれてここへ参りました。――斉資様」
流麗は言った。
「今日は久方ぶりに出雲へ参りましたが、あの頃を想う度に胸が強く締め付けられます」
「――――」
「このわずかに悟りました。私にはもう、全てをやり直すということは不可能のようです。
夫と一族の想いが捨てきれず、傍を離れられない」
美しい想い出に交えて、愛する人の死に対するこの苦しみを流麗は訴えた。
ほんの暫く海風に浴びて、そして斉資は答えた。
「それでもひとは、倒れたままにはいられない」
「――――」
「流麗、誰でもやり直せるのだ。ただそれに、多くの時間が必要なだけぞよ」
「――――」
「たとえ漆黒の闇が続いても、朝は必ず来る」
海からの冷たい風は止まない。
流麗は冷え切った手で櫛を握り、逆に優しい暖かい微笑みを浮かべて言った。
「斉資様、此度は斉資様のお蔭です。近々お礼物を……
今日はせめて、心からお礼に代えさせていただきます」
――蒼く眩しい月の光が、中まで射しこむ。
壁に幾本も立て並べた銀の刃が月光に反射し、その光が流麗の顔面を照らした。
あまりの眩しさに、漸く流麗は目を覚ました。
「起きたかよ、流麗様よ」
流麗の剣を研ぐ刀々斎が流麗の目覚めに気づき、声をかけた。
「久々に来たかと思ったら、急に死んだように寝るものな」
流麗は目を見開け、辺りの光景をよく見た。
ぼろ家に老人の刀鍛冶が、いつも通り仕事をしている。
先程目に映ったものが夢と分かると、流麗は大きく息を吐き、そしてその身を起こした。
「きっと闘いばかりで疲れているんだ。ここに来たからには、寛げよ」
夜空の下で、きまって流麗は一族の弔いに笛を吹く。曲は、魂之舞。
それを耳にしながら刀々斎は星を観る。
――と、ふと笛がやんだ。
刀々斎の視線は、流麗に向けられた。
「どうした?」
「恋しくて……」
「恋しい?」
「ヨソラの長い黒髪も、顔の傷も、私を抱きしめる腕の強さも一緒に楽を奏でたことも、
口を重ねたことも全て恋しいの」
「――――」
「彼は始めから出雲の公子でも王でもなかった。全て自らの一存で如月や私の為に闘い、尽くし、
全てに命を懸けたの。私はヨソラがいたからこそ、人を愛するという意味を知ったのよ。
その、ヨソラがいないだけで、こんなにも気持ちが苦しいなんて……不思議ね」
刀々斎は答えない。
暫く沈黙が続き――やがて流麗は手に持つ竜笛を着物と鎧の隙間に挿し、また体勢を整えた。
まだ刀々斎と話したい事が山のようにあるが、やはり時間がない。
流麗はついに本題に入った。
「今日、銀竜が放った刺客と闘った。当人も、すぐ近くにいたらしい」
「うむ」
「その刺客に、犬夜叉とかごめが捕らわれた」
「――――」
「剣よりも弓が有利と思って試みけれど、無駄に終わってしまった。
明朝、犬夜叉とかごめを助けて銀竜と決着をつける。
数は多い方がよいから――爺も、闘いに参戦せよ」
「流麗……」
「この後も会わねばならない者がいる。行かなければ……」
長年共にしてきた自らの牙で打った剣を腰に挿し、
絶大な力を持つ神剣を握り、流麗は立ち上がった。
「爺、夫(つま)の剣は、どうかあの場所へ捧げ、今のことは、冥加が戻ったら伝えて」
九月十八日。
ついに銀竜と決着をつけるこの日、とても奇怪なことが起きた。
夏から秋へ移り変わる頃なのに、牡丹雪が降っている。
気温もまるで低く、吐く息も白い。
だが幻想的な景色とは逆に、満ち溢れた殺気がそこにはある。
銀竜の居場所は人間の城と聞いた。
吹き荒れる雪とともに風にのって流れる匂いを頼りに、ついにその城に一行は辿りついた。
「一体何の厭魅か……雪が降るとは」
刀々斎の肩の上の冥加が言った。
「いかにも決闘にふさわしいじゃない」
冥加に、珊瑚がそう答えた。
前の景色を見つめながら意を決し、ついに、一行は動き出した。
城からは新手が群をなしてくる。
その中に葉蘭と紫蘭も混じり、弥勒と珊瑚の前に立ちはだかった。
手持ちの武器を握り弥勒と珊瑚は、葉蘭、紫蘭と再び激しく火花を散らした。
一方の犬夜叉は、ただ一人、牢獄にとじ込められている。
だがそれから間もなく、犬夜叉の耳はある足音は捉えた。
その音が牢の前で止んだ。戸を開け、その者は牢の中へ入ってきた。
そして犬夜叉の腕を強く掴んで乱暴にひき立たすと、犬夜叉を牢の外へ連れ出した。
逃がすのではない。
打ち首にするのだ。
その者は、犬夜叉の背後に立つと、乱暴に屈ませた。
「お前、小竹だろう」
ためらいもなく犬夜叉が言った。
「牢に来た時から分かっていた……俺の鼻は敏感だからな」
黒く分厚い布で目を覆い隠され、犬夜叉にも破れぬ綱で腕を縛られ、
手首も鋼線で何重にも巻きつけられている。
そのせいで、未だ手首から血が滴り落ちる。
だが、もう痛みすら感じない。
犬夜叉は抵抗する気もなく、ただ俯き、小竹に言う。
「小竹、俺を殺すのは構わねぇ。命なんて、全然惜しくもねぇからな」
「――――」
「俺とお前は敵同士だ。お前は、必然的に銀竜の肩を持つ。
敵同士なら、武器を持って闘い、どっちかが死ぬんだ」
「――そうね」
それまで黙っていた小竹が答えた。
「もしもこれが逆の立場なら、あなたも私を殺している。
きっとこんな風に、容赦はなく……」
遂に小竹は剣を抜き、刃先を犬夜叉の首筋に突きつけた。
だが、死ぬことに対して恐れぬ犬夜叉の背後を見て、ふと小竹は思いとどまった。
――生きていれば必ず死ぬ。忘れるんだ、いいな。
父親や、妹や、母方の一族を亡くして長い年が経つというのに、
あの時の光景と、銀竜の一言は忘れられない。
小竹は眉間に皺を寄せ、歯も食いしばりながら、ついに剣を振るった。
その瞬間、犬夜叉の体に自由が利いた。
小竹が断ち切ったのは、犬夜叉の腕を縛る綱と、手首を縛る鋼線。
小竹は剣を床に置き、犬夜叉の目を覆う布を解いた。
「やはりあなたを殺すことはできない」
「――銀竜を裏切るんじゃねぇのか?」
小竹はまっすぐ犬夜叉を見つめ、そっと頬を撫でた。
「私もあなたと同じ半妖……同じものを殺すことは、とてもできない」
「――――」
「どうか再びこれを。外では、皆が闘っています」
小竹は錆びた鉄砕牙を犬夜叉に渡した。
正しく、あの林で手放した鉄砕牙。
犬夜叉は、そっとその手で鉄砕牙を受け取った。
「共に、闘いましょう」
その後、無事にかごめと出会うことが出来た。
怪我などはなく、犬夜叉はかごめを連れ、小竹と刺客と闘った。
大勢の敵と一度に刃を交え、流麗は闘う。
だが刺客の圧倒的な力量に流麗が負けた。
素早く刺客が止めをさそうとした一瞬の時――ある女が突如、流麗の前に立った。
手持ちの氷の槍で刺客を倒し、集まる新手もその女の供の手によって倒された。
流麗がその者の姿を見ると、あっと驚いた。
前に立つのは、まぎれもない豹猫四天王の冬嵐姉弟だ。
「お前達……」
「あいつらから、女王陛下の援護をと俺達は頼まれた」
「みな、流麗様のお帰りをお待ちしています」
秋嵐と春嵐がそう言ったとき、再び刺客が集まった。
「お前達は、私の指示のとおりに」
冬嵐の命に、三人の妹弟は即座にそれぞれの所へ向った。
流麗は腰に下げる鞘から自らの牙の剣を抜き、冬嵐と背を預けた。
「流麗、彼奴らは私に任せなさい。あなたは早く、銀竜の許へ!」
冬嵐の命令に、右を向けば春嵐は敵の攻撃を交わし、反撃しながら殺生丸の方へ向い、
左を向けば、すでに夏嵐と秋嵐が弥勒と珊瑚の援護をする。
かつては敵同士だったのが、今では姉妹のようであり、
その冬嵐を一人にさせるわけにはいかなかった。
「一族を殺した敵に、人ながら友人までも殺された。同じ目を為してはならない!」
そう言ったと同時に、ついに刺客が群をなして襲ってきた。
鋭い刃を容赦なく振るい、その壮絶な攻撃を手に持つ武器を用いて受け止めながら、冬嵐は更に言った。
「私達などよりも、大切なのは自分です。今を無駄にしてはいけません!」
冬嵐の勢いに押され、流麗は悔やみながら冬嵐にその場を任せ、ついに銀竜の許へ走った。
やがて流麗は最上階の部屋に辿りつくと、果たして銀竜がいた。
強く剣を握り、流麗は、銀竜と向かい合う。
「やっと来たか、流麗」
銀竜はあることに気がついた。
「流麗、背の神剣はどうした?」
「――元の持ち主に返した。私を守る為に、
夫が天照神と闘って手にした神剣は、本来この世の者の持つべきものではない」
ふんと銀竜は嘲笑した。
剣を抜くと足を大きく一歩踏み出し、ついに流麗と決戦を始めた。
「LOVER 【夢 幻 泡 影】 漆」 優サマ
春嵐に告げられて、犬夜叉はかつて人の城であった楼上へやってきた。
辿りつくと、殺生丸がいてぼうっと俯いている。
殺生丸が見る先を犬夜叉は見ると、血だらけの流麗の姿があった。
「流麗……」
犬夜叉は流麗の近寄り、床に膝を付け、既に息絶える流麗の身を抱き起こした。
胸を一突きにされている。とても無惨なその姿に、犬夜叉は言葉を失くしてしまった。
殺生丸も同じだった。
童男のころから慕い続けた姉が、命を落としたのだ。
彼にとってこの現状は何より恐ろしいこと。
躊躇いはない。殺生丸が天生牙を掴んだ。
だが天生牙を抜こうとしたその時、
振るなかれ。
殺生丸の耳が、聞き覚えある低い声を捉えた。
空耳か?いやしかし、確かに聴こえた。
躊躇っているわけではない。なのに、天生牙を抜けない。
その時、流麗の体からまぶしい、虹色の光が放ち出した。
虹色の光とともに金粉が舞い上がり、そしてやがては、犬夜叉の腕から忽然とその姿が消えた。
唯一その場に残ったものは、瑠璃の小刀ただ一つだけ。
殺生丸は利き手から天生牙を離し、地面に膝をつけ、床の上の瑠璃の小刀を拾い上げた。
翡翠や瑪瑙や、水晶、真珠などの宝石などを飾り、永遠の輝きを放つ美しい瑠璃の小刀――
流麗と嵩明良が永久に離れはしない唯一の証だ。
まさか先の声は――。察した時、突如犬夜叉が背を向けた。
「犬夜叉」
殺生丸が言った。
「一人で行くつもりか?」
「――――」
「たった一人で銀竜に勝るとでも……?」
犬夜叉は微妙に顔をこちらに向け、陽気にも似た笑みを浮かべた。
「流麗は闘い命は惜しくないと言っていた。
俺も――闘いに悔いさえなければ、たとえ死んでも構わない」
犬夜叉がそう言った時、突如殺生丸は、瑠璃の小刀を犬夜叉の首にかけた。
「たとえ姉上はそう言っても、本当に思ったことは一度もない」
「――――」
「これを手放すな。姉上が必ず、お前を守ってくれる」
雪は止まず、ますます降り積る。
小竹は一人きりで、多くの刺客と闘っていた。
口からは霧のように白く濃い息を荒く吸い、吐きながら、
たった一本の刀を持ち、容赦ない激闘のさなか――
突如その間に銀竜が現れた。
「大侠……」
「小竹。やつをしとめ損ねたな。なぜだ?」
銀竜は冷ややかに、そして大きく声を上げた。
感情にひたる銀竜は、その手も体も、声も震える。
「二百年来、剣を用いて一門の為に偉業を為そうと研鑽を積んだ。
だがお前のことが毎日のように脳裏に過ぎる。会いたくてしようがなかった。
その感情を抑える為に、私は幾度も自分の剣で自分の身を斬り裂いた」
小竹は黙ったまま、何も答えなかった。
銀竜は一歩を踏み出した。
小竹の横を通り過ぎた時、小竹は驚いたようにハッとした。
今から銀竜がする事を俊敏に感じ、すぐさま銀竜の着物を掴んだ。
「行かせない!」
「私が何をするか、すでに分かっているのだな……」
銀竜は小竹の感情を痛いほどに感じた。
小竹は銀竜の気持ちを全て分かり知っている。
この男に、これほど深い理解をする女は世の中にはいない。
「最後に言う。お前はいまだ、私を愛しているか?」
銀竜がそう言った瞬間、小竹の声なき声があがった。
銀竜は手元の剣で小竹の胸を突き刺したのだ。
小竹は銀竜から手を離し、どさっと厚い雪の上に倒れた。
小竹は涙を流し、銀竜も涙を流していた。
銀竜の感情はもはや制御を失っている。
彼の狂ったような怒りと涙は激しい飛雪が拭って、やがて小竹を残してそこを離れた。
決意を固めて、犬夜叉と殺生丸は雪の中を駆けぬいた。
だが、突然に犬夜叉の足がとまった
ざっと犬夜叉は雪の上に膝をつき、
そして雪に埋もれる一人の女を掘りだし、その体を抱き上げた。
それが、まぎれもない、小竹なのだ。
流麗と同じ、胸に深い刺し傷があり、尚も鮮血が溢れていた。
既に小竹の顔色は蒼白であった。
最悪な自体を予感した時、殺生丸ともに犬夜叉は凄まじい殺気を感じ取った。
背後から銀竜の鋭い剣の刃が振り落とされ、
犬夜叉と殺生丸は素早く刃を避け、銀竜と間合いをとった。
犬夜叉と殺生丸は同時に、その腰から刀を抜き、身構えた。
血に汚れた銀竜を目にした犬夜叉は、とても険しい表情で言い放った。
「お前が流麗を殺したのか!」
「あぁ、そうとも!」
「まさか小竹も……?」
「私の仕業だ。心から小竹を愛している。貴様などと違って嘘ではない!」
「愛してるなら、どうして小竹を殺す!?」
静かに犬夜叉が訊ね、銀竜は叫びながら答えた。
「誰がそうしたと思っている。お前だろう!」
「俺だと?」
「私は流麗を仕留め、小竹はお前達を殺すと言った。必ずと……。
だが、お前が小竹を誘惑したせいで、小竹はお前を殺せなかったのだ」
「――あわれな女だ……」
殺生丸が呟き、銀竜は笑った。悲痛にも似た、冷ややかな笑い――。
向かい合う三人の男は凝固した。
飛雪に吹き付けられ、じっとにらみ合う。
やがて、その飛雪に逆らうように犬夜叉は言い放った。
「全てを仕組んだのはお前だ。流麗と小竹……そして仲間の為に、お前に容赦はない!」
そういう犬夜叉に、銀竜は剣を持ち上げて答えた。
「いいだろう。この一戦で、お前達との万古の憂いを解く!」
銀竜が放った刺客は全て倒した。
葉蘭や紫蘭も、やがては弥勒、珊瑚と、援護する夏嵐と秋嵐の手によって倒された。
長く闘い続けたせいで、ざっと腰を下ろすと再び立ち上がることができない。
前を見渡せば、すぐそこで犬夜叉、殺生丸と、銀竜が激しく刃を交わしている。
とても重い疲労に襲われ、仲間達は犬夜叉の援護にもあたることはできなかった。
ただそこで、犬夜叉の身を案じ、見守るしかない。
犬夜叉は殺生丸と手を組んで銀竜と血なまぐさく激しい闘いを続ける。
だが二百年も剣の研鑽を積んだ銀竜を相手にすれば、
犬夜叉や殺生丸までもまるで手に負えない。
また間をとった。
二十歩の間合い。
既に朦朧の犬夜叉に対して、銀竜は再び剣を向けた。
そして必殺・快剣斬水で、止めを心がけた。
劉(リウ)――立刀の劉。姓に刀があり。
それはすなわち、身中に刀を宿しているということ。
劉銀竜(リウ・インロン)という姓名も、
圧倒する必殺・快剣斬水も、元は銀竜本人の豪快さを表している。
前の兄弟と二十歩以上の距離が離れていても立刀の劉ならば快剣斬水は放てるし、
もし二人がともに剣の最大威力を撃とうとも、確実に弾き返せる。
勝利は銀竜の方にあった。
だが、その時――再び小竹が息を吹き返し、雪の中から立ち上がった。
「大侠……」
犬夜叉も銀竜も、誰もが小竹を見た。
小竹の胸からはいまだ鮮血が溢れ、複雑なまなざしで銀竜を見つめ、
飛雪にもみ消されそうな声で小竹は言った。
「大侠、その剣で兄弟を殺したら……私もあなたを殺す!」
小竹は刀嚢からあと一振りだけの飛翔刀を抜いた。
「小竹、飛翔刀をうつな!」
犬夜叉が叫んだ。
「刀を放ったら、傷が裂ける。血が溢れて死んでしまうぞ!」
その犬夜叉の声が響く。
だがまるで小竹は耳を傾けず、刀の柄を握り、さっと身構えた。
犬夜叉は小竹を見つめ、銀竜を見た。
そしてやがて意を決したように、一歩を踏み出した。
「この俺が、鉄砕牙で銀竜を討つ。お前は闘う必要はない……無駄に力を使うな」
足を引きずりながら犬夜叉は小竹に言い聞かせた。
犬夜叉を見つめる小竹の目から、涙が溢れる。
体を小刻みに震わせ、短刀を握り、構えたまま、銀竜と視線を合わし、銀竜を睨んだ。
一方の銀竜の視線は犬夜叉の方へ戻った。
剣先をまっすぐ犬夜叉のほうに向け、その体勢でじっと構えた。
ついに、その間が八歩まで迫った。
銀竜は大きく一歩を踏み出した。
「必殺・快剣斬水!」
瞬きする間もなく、銀竜の剣が犬夜叉の胸にさしかかった、
その時、三文字の言葉が怒濤のごとく、小竹の口をついて出た。
まさしく飛翔刀だった。
快剣斬水よりも速い飛翔刀が出現した時、空の色は、一瞬にして失った。
胸の傷は更に裂け、そこから溢れる、ぞっとするような夥しい鮮血が、純白の雪を汚した。
紛れもない、小竹の血。
複雑な眼差しで小竹は銀竜を見つめ、また銀竜も小竹を見つめていた。
「う……っ」
そっと視線を変えた。
唖然としてこちらを見る犬夜叉に、小竹はわずかな笑みを見せ――ついに力尽きた。
「小竹――――っ!!!」
犬夜叉は思わず鉄砕牙を手放し、無我夢中に小竹のそばに走ってその体を抱き上げた。
その姿を、銀竜はただ呆然と見つめる。
犬夜叉は小竹の名前を何度も呼んだ。
小竹は薄く目を開け、犬夜叉の目を見ると、風のような声で小竹は言った。
「私が間違っていた……あなたに刃を向けるべきではなかった……」
「――――」
「故郷へ帰って、昔のように、あなたは歌い、私は踊る。
刀を棄てて、風と花の日々送りたかった……銀竜大侠(インロンターシア)……」
小竹の目には、犬夜叉の姿は銀竜として映っていた。
銀竜は一度も小竹の傍には来ない。俯き、飛雪にふきつけられる。
小竹は答えを待っているように、じっと犬夜叉を見つめる。
そんな小竹に犬夜叉は強く抱きしめ、飛雪と同じくらいの微かな声で小竹に答えた。
「連れて行くよ。一緒に帰ろう」
蒼白の小竹の顔にまた笑顔が浮かんだ。
まもなく銀竜はその場を去った。
立ち止まることも振り返ることもなく、飛雪に吹きつられ、
時に分厚い雪に足をからめ倒れながら――。
壮絶な闘いが終わって直後、
見守り続けたかごめ達はその傷の痛みを堪えながら犬夜叉の傍へ疾く走った。
だが、絶望に暮れる犬夜叉の目の前は真っ暗になった。
体は氷のように冷たくなり、次第に力が失せ、ゆらゆらと雪の上に倒れた。
竜舌蘭一門は滅亡した。
それは確実に進行はしていたが、決定付けたのはあの飛雪の一戦だった。
一門だけにあらず二百年来ともにしてきた剣も、仕える精鋭も、
何より唯一の恋人を失った劉銀竜は、もはやその勢力を挽回することは不可能であった。
――昏睡から目を覚ました時、俺はいつの間にか武蔵野にある村に戻り、楓の家の中にいた。
長く眠り続けたらしい。まだ体がゆらゆらして、まともではなかった。
「犬夜叉様。ようやく、お目を覚まされましたか」
かすかに耳元で冥加がいった。
「流麗様は不幸でございましたが、このたびは見事なご功績です」
「――――」
「近々西国から、あなた様へ賞金が出されますぞ」
俺はうめいた。体を動かすことができない。
じっと天井を見つめて、何かしらの躊躇いを感じつつ、冥加に銀竜の事を訊ねた。
そのことに冥加は、
「劉銀竜は、死にました」
小さく、静かにそう言った。
更に冥加は、あの後の銀竜のことを詳しく語ってくれた。
俺は俺にとって最高の姉を亡くし、俺を守る為に小竹は命を擲った。
それらを追うように銀竜は自ら命を落としたと聞くと、俺はひとしきりの失望に沈んだ。
涙まで溢れ、あの闘いにとても後悔を感じた。
もう三年になる。
俺も仲間も、風ように自由気ままな毎日を送っている。
あの旅も、あの血なまぐさい四日間の日々も忘れかけていたとき、俺はある話を聞いた。
「璋小竹の妹が唐国で生きている」
それを聞いてすぐに、俺は唐へ向った。
話は本当だった。唐の山岳地帯に、小竹の妹の馮美琳(フェン・メイリン)はいた。
馮美琳もまた半妖であるが、全くそうとは思えなかった。
小竹と同じくどこにでもいる、ごく普通の女性だった。
美琳は母方の一族とともに捕吏に襲われ、殺されたと聞いている。
本題を話す前に、俺はその事について美琳に訊ねた。
すると美琳はすんなりと答えた。
璋小竹が見たものは、間違いではない。
三百年前あの日、姉妹と母方の一族は県の捕吏に襲われた。
美琳は致命傷を負って意識を失ったが一命はとりとめ、
再び目を覚ますと、一族は死に、姉の姿もなかった。
既に姉も最悪な事態に見舞われていると絶望していたが、
まさか天下一の大妖怪の恋人ということも、倭にいたということは知らなかった。
姉妹の微妙な食い違いに、美琳は苦笑していた。
そして、俺は三年前のあの四日の内を美琳に明かした。
片言の華語で美琳と話していくうち、俺は小竹の本名と身の上を知った。
璋小竹の本名は馮麗玉。
彼女の父親の馮丹華は混じりもない、人間の男。武芸人だった。
母親は妖怪で、踊り子であった。
昔、武芸人の馮丹華はたった一つの刀法・飛翔刀を武器に、
平気に人を強制し、騙し、殺しを続けていた。
自分の手を一切汚さず、人を殺していたのだ。
馮丹華は、人であって人ではない。
いつしかそんな丹華の力に魅了した武芸人が集まりはじめた。
やがて千の武芸人と刀が集まった時、
丹華を頭目に残忍な刀の一門――巨大な千刀隊(チェンダオドゥイ)を建てた。
丹華が千刀隊の頭目になった時、その姿は一切みせない。
集った仲間や娘達を使って人を殺し、
千刀隊の仲間が一度でも裏切りなどみせると、丹華は娘達に殺すよう命じた。
姉妹は丹華に逆らえない。
丹華が死ぬまで、麗玉と美琳は丹華の奴隷でしかなかった。
だが丹華は誰よりも二人の娘だけに飛翔刀の技を伝え、その真意を語った。
たとえ殺戮を命じても、丹華は、娘達を心から愛していたことには違いない。
若くして丹華が死の病を患った時、彼は漸くその飛翔刀の最高的奥義を悟った。
迫る死と共に悟った、飛翔刀の最高奥義とは――
飛翔刀を含めあらゆる刀剣は人を殺すだけや、人を守る為だけのものでもない。
結局、何も生まれはしないということ。
刀剣とは持つべきに非ず、ゆえに飛翔刀(フェイシアンダオ)すなわち、非翔刀(フェイシアンダオ)なのだ。
馮丹華は人を扱い、唆し、殺し、感情と弱点を巧妙に利用したことによって、
畢生の修練で編み出した飛翔刀の最高的奥義を悟ったと、美琳は言った。
俺は頷いた。それからも更に美琳は言う。
馮丹華の死後、千刀隊は滅亡し、麗玉と美琳は刀を棄てた。
だがそのまもなく、母方の一族は捕吏の手によって滅び、それがきっかけに麗玉は再び刀を持った。
以後、父親と同じ道を歩み、形見の飛翔刀を用いて、
敵や恋人の銀竜の命を狙い、そして最後は飛翔刀によって自分を殺した。
大妖怪であった劉銀竜は、半妖の麗玉だけを一途に愛した。
麗玉も銀竜が好きだった。
二人の愛と情は、とても純白なもの。
それを通り超えた為に、二人は互いに不殺にはいれず、闘い合った。
「ふん……」
思わず俺は苦笑した――まるで俺も、二人と同じだ。
対する美琳はしんと黙る。
仲のいい姉と過ごしたわずかな思い出と、三年にしてやっと姉の死を悟った美琳はとても複雑だった。
だがそれは一瞬なもので、彼女は冷静に言った。
――闘いに参戦したものは全て、互いに生死の契りを交わした。
心は、永久に離れることはない。
今はもう、俺の手に刀はない。たとえ五十年経っても二度と刀は持たないと、そう決めている。
五十年後――刀のない風流な毎日を送り、毎日きっと仲間と酒宴をしている。
その宴の時には必ず、五十年間の人生を語り合っているに違いない。
俺が語るなら奈落を追い求める旅よりも、あの四日間を語る。
出始めは、まず姓と名だ。
流麗から始まって、劉銀竜、馮麗玉と続き、
それぞれの身分と過去を語って――最後はあの四日を語る。
野の花に清らかな風が吹くように、実際に見て、聞いた真実を俺は長々と語るのだ。
きっと涙もろくなった仲間の衣の袖はぐっしょりと濡れて重くなり、
その泪を拭いながら仲間と口を合わせてこう言うはずだ。
「五十年来、なんて夢や幻、泡影のように儚い人生なのだろう」、と……。
そういえば、流麗はあの天楼館で同じ曲を二度も吹いていた。
夢幻泡影という、得意の一曲。
秘曲の魂之舞とならんで、まさに人生の儚さを感ずる曲だった。
誰かが言っていた。
流麗の笑顔は春の野にそそぐ暖かな光のようで、誰にでも、たとえ人間もその魅力に惹かれる。
多くの妖や人間達の交わりを好み、酒も好んだ。
一族の弔いに毎夜の管を奏で、歌や詩を詠い――まるで、太陽のような女性だと。
だが精鋭一族の姫君である流麗は、現れる敵と、闘わずにはいられない。
一族や夫と生き別れた後、確信的に自分の幸福な結末など有りはしないと感ずいていた。
きっと、何よりの全てだった夫と出会う以前から、有り余る力で天下泰平を為し、
末期は英雄になると心に決めていたのだ。
だがその二つの定義の結論を、流麗は最後の闘いのさなかにきっとこう悟った。
武器はなく、英雄がいない世界こそが、本当の平和だと!
星が空の海に浮かぶこの晩、その下で俺は一人いる。
あの日と同じ夜――
耳をすませば、あの笛の音が聴こえてきそうな、そんな感じの夜だ。
いつもとは違う、神秘的な夜空の下で、俺は歌を作った。
死を恐れず、勇敢に闘い続けた英雄たちを悼む歌だ。
あれから三年が過ぎて、ようやく贈ることができた。
歌とか詩とか楽には、全く興味はない。ただ感情さえ伝わればそれでいいと思っている。
流麗もきっとそう思って、毎晩に一族に弔いの笛を捧げていたはずだ。
感情というものは、瞬間的に生まれるもの。
その時その気持ちは、紛れもない真実なのだ。
――必ず届け。
そう願って、俺は夜空の下で勇敢に闘い続けた英雄達に歌を捧げた。
倭 と 唐 に 英 雄 あ り
両 者 英 雄 比 類 な き 絶 世 す
戦 士 と い う 宿 命 を 負 い な が ら
表 の 心 は 愛 の 為 に 生 き
裏 の 心 は 憎 に 囚 わ れ る
た と え憎 に 囚 わ れ 死 し て 灰 塵 と な っ て も
英 雄 本 当 の 愛 を 棄 つ に い ら れ な い
【完】
辿りつくと、殺生丸がいてぼうっと俯いている。
殺生丸が見る先を犬夜叉は見ると、血だらけの流麗の姿があった。
「流麗……」
犬夜叉は流麗の近寄り、床に膝を付け、既に息絶える流麗の身を抱き起こした。
胸を一突きにされている。とても無惨なその姿に、犬夜叉は言葉を失くしてしまった。
殺生丸も同じだった。
童男のころから慕い続けた姉が、命を落としたのだ。
彼にとってこの現状は何より恐ろしいこと。
躊躇いはない。殺生丸が天生牙を掴んだ。
だが天生牙を抜こうとしたその時、
振るなかれ。
殺生丸の耳が、聞き覚えある低い声を捉えた。
空耳か?いやしかし、確かに聴こえた。
躊躇っているわけではない。なのに、天生牙を抜けない。
その時、流麗の体からまぶしい、虹色の光が放ち出した。
虹色の光とともに金粉が舞い上がり、そしてやがては、犬夜叉の腕から忽然とその姿が消えた。
唯一その場に残ったものは、瑠璃の小刀ただ一つだけ。
殺生丸は利き手から天生牙を離し、地面に膝をつけ、床の上の瑠璃の小刀を拾い上げた。
翡翠や瑪瑙や、水晶、真珠などの宝石などを飾り、永遠の輝きを放つ美しい瑠璃の小刀――
流麗と嵩明良が永久に離れはしない唯一の証だ。
まさか先の声は――。察した時、突如犬夜叉が背を向けた。
「犬夜叉」
殺生丸が言った。
「一人で行くつもりか?」
「――――」
「たった一人で銀竜に勝るとでも……?」
犬夜叉は微妙に顔をこちらに向け、陽気にも似た笑みを浮かべた。
「流麗は闘い命は惜しくないと言っていた。
俺も――闘いに悔いさえなければ、たとえ死んでも構わない」
犬夜叉がそう言った時、突如殺生丸は、瑠璃の小刀を犬夜叉の首にかけた。
「たとえ姉上はそう言っても、本当に思ったことは一度もない」
「――――」
「これを手放すな。姉上が必ず、お前を守ってくれる」
雪は止まず、ますます降り積る。
小竹は一人きりで、多くの刺客と闘っていた。
口からは霧のように白く濃い息を荒く吸い、吐きながら、
たった一本の刀を持ち、容赦ない激闘のさなか――
突如その間に銀竜が現れた。
「大侠……」
「小竹。やつをしとめ損ねたな。なぜだ?」
銀竜は冷ややかに、そして大きく声を上げた。
感情にひたる銀竜は、その手も体も、声も震える。
「二百年来、剣を用いて一門の為に偉業を為そうと研鑽を積んだ。
だがお前のことが毎日のように脳裏に過ぎる。会いたくてしようがなかった。
その感情を抑える為に、私は幾度も自分の剣で自分の身を斬り裂いた」
小竹は黙ったまま、何も答えなかった。
銀竜は一歩を踏み出した。
小竹の横を通り過ぎた時、小竹は驚いたようにハッとした。
今から銀竜がする事を俊敏に感じ、すぐさま銀竜の着物を掴んだ。
「行かせない!」
「私が何をするか、すでに分かっているのだな……」
銀竜は小竹の感情を痛いほどに感じた。
小竹は銀竜の気持ちを全て分かり知っている。
この男に、これほど深い理解をする女は世の中にはいない。
「最後に言う。お前はいまだ、私を愛しているか?」
銀竜がそう言った瞬間、小竹の声なき声があがった。
銀竜は手元の剣で小竹の胸を突き刺したのだ。
小竹は銀竜から手を離し、どさっと厚い雪の上に倒れた。
小竹は涙を流し、銀竜も涙を流していた。
銀竜の感情はもはや制御を失っている。
彼の狂ったような怒りと涙は激しい飛雪が拭って、やがて小竹を残してそこを離れた。
決意を固めて、犬夜叉と殺生丸は雪の中を駆けぬいた。
だが、突然に犬夜叉の足がとまった
ざっと犬夜叉は雪の上に膝をつき、
そして雪に埋もれる一人の女を掘りだし、その体を抱き上げた。
それが、まぎれもない、小竹なのだ。
流麗と同じ、胸に深い刺し傷があり、尚も鮮血が溢れていた。
既に小竹の顔色は蒼白であった。
最悪な自体を予感した時、殺生丸ともに犬夜叉は凄まじい殺気を感じ取った。
背後から銀竜の鋭い剣の刃が振り落とされ、
犬夜叉と殺生丸は素早く刃を避け、銀竜と間合いをとった。
犬夜叉と殺生丸は同時に、その腰から刀を抜き、身構えた。
血に汚れた銀竜を目にした犬夜叉は、とても険しい表情で言い放った。
「お前が流麗を殺したのか!」
「あぁ、そうとも!」
「まさか小竹も……?」
「私の仕業だ。心から小竹を愛している。貴様などと違って嘘ではない!」
「愛してるなら、どうして小竹を殺す!?」
静かに犬夜叉が訊ね、銀竜は叫びながら答えた。
「誰がそうしたと思っている。お前だろう!」
「俺だと?」
「私は流麗を仕留め、小竹はお前達を殺すと言った。必ずと……。
だが、お前が小竹を誘惑したせいで、小竹はお前を殺せなかったのだ」
「――あわれな女だ……」
殺生丸が呟き、銀竜は笑った。悲痛にも似た、冷ややかな笑い――。
向かい合う三人の男は凝固した。
飛雪に吹き付けられ、じっとにらみ合う。
やがて、その飛雪に逆らうように犬夜叉は言い放った。
「全てを仕組んだのはお前だ。流麗と小竹……そして仲間の為に、お前に容赦はない!」
そういう犬夜叉に、銀竜は剣を持ち上げて答えた。
「いいだろう。この一戦で、お前達との万古の憂いを解く!」
銀竜が放った刺客は全て倒した。
葉蘭や紫蘭も、やがては弥勒、珊瑚と、援護する夏嵐と秋嵐の手によって倒された。
長く闘い続けたせいで、ざっと腰を下ろすと再び立ち上がることができない。
前を見渡せば、すぐそこで犬夜叉、殺生丸と、銀竜が激しく刃を交わしている。
とても重い疲労に襲われ、仲間達は犬夜叉の援護にもあたることはできなかった。
ただそこで、犬夜叉の身を案じ、見守るしかない。
犬夜叉は殺生丸と手を組んで銀竜と血なまぐさく激しい闘いを続ける。
だが二百年も剣の研鑽を積んだ銀竜を相手にすれば、
犬夜叉や殺生丸までもまるで手に負えない。
また間をとった。
二十歩の間合い。
既に朦朧の犬夜叉に対して、銀竜は再び剣を向けた。
そして必殺・快剣斬水で、止めを心がけた。
劉(リウ)――立刀の劉。姓に刀があり。
それはすなわち、身中に刀を宿しているということ。
劉銀竜(リウ・インロン)という姓名も、
圧倒する必殺・快剣斬水も、元は銀竜本人の豪快さを表している。
前の兄弟と二十歩以上の距離が離れていても立刀の劉ならば快剣斬水は放てるし、
もし二人がともに剣の最大威力を撃とうとも、確実に弾き返せる。
勝利は銀竜の方にあった。
だが、その時――再び小竹が息を吹き返し、雪の中から立ち上がった。
「大侠……」
犬夜叉も銀竜も、誰もが小竹を見た。
小竹の胸からはいまだ鮮血が溢れ、複雑なまなざしで銀竜を見つめ、
飛雪にもみ消されそうな声で小竹は言った。
「大侠、その剣で兄弟を殺したら……私もあなたを殺す!」
小竹は刀嚢からあと一振りだけの飛翔刀を抜いた。
「小竹、飛翔刀をうつな!」
犬夜叉が叫んだ。
「刀を放ったら、傷が裂ける。血が溢れて死んでしまうぞ!」
その犬夜叉の声が響く。
だがまるで小竹は耳を傾けず、刀の柄を握り、さっと身構えた。
犬夜叉は小竹を見つめ、銀竜を見た。
そしてやがて意を決したように、一歩を踏み出した。
「この俺が、鉄砕牙で銀竜を討つ。お前は闘う必要はない……無駄に力を使うな」
足を引きずりながら犬夜叉は小竹に言い聞かせた。
犬夜叉を見つめる小竹の目から、涙が溢れる。
体を小刻みに震わせ、短刀を握り、構えたまま、銀竜と視線を合わし、銀竜を睨んだ。
一方の銀竜の視線は犬夜叉の方へ戻った。
剣先をまっすぐ犬夜叉のほうに向け、その体勢でじっと構えた。
ついに、その間が八歩まで迫った。
銀竜は大きく一歩を踏み出した。
「必殺・快剣斬水!」
瞬きする間もなく、銀竜の剣が犬夜叉の胸にさしかかった、
その時、三文字の言葉が怒濤のごとく、小竹の口をついて出た。
まさしく飛翔刀だった。
快剣斬水よりも速い飛翔刀が出現した時、空の色は、一瞬にして失った。
胸の傷は更に裂け、そこから溢れる、ぞっとするような夥しい鮮血が、純白の雪を汚した。
紛れもない、小竹の血。
複雑な眼差しで小竹は銀竜を見つめ、また銀竜も小竹を見つめていた。
「う……っ」
そっと視線を変えた。
唖然としてこちらを見る犬夜叉に、小竹はわずかな笑みを見せ――ついに力尽きた。
「小竹――――っ!!!」
犬夜叉は思わず鉄砕牙を手放し、無我夢中に小竹のそばに走ってその体を抱き上げた。
その姿を、銀竜はただ呆然と見つめる。
犬夜叉は小竹の名前を何度も呼んだ。
小竹は薄く目を開け、犬夜叉の目を見ると、風のような声で小竹は言った。
「私が間違っていた……あなたに刃を向けるべきではなかった……」
「――――」
「故郷へ帰って、昔のように、あなたは歌い、私は踊る。
刀を棄てて、風と花の日々送りたかった……銀竜大侠(インロンターシア)……」
小竹の目には、犬夜叉の姿は銀竜として映っていた。
銀竜は一度も小竹の傍には来ない。俯き、飛雪にふきつけられる。
小竹は答えを待っているように、じっと犬夜叉を見つめる。
そんな小竹に犬夜叉は強く抱きしめ、飛雪と同じくらいの微かな声で小竹に答えた。
「連れて行くよ。一緒に帰ろう」
蒼白の小竹の顔にまた笑顔が浮かんだ。
まもなく銀竜はその場を去った。
立ち止まることも振り返ることもなく、飛雪に吹きつられ、
時に分厚い雪に足をからめ倒れながら――。
壮絶な闘いが終わって直後、
見守り続けたかごめ達はその傷の痛みを堪えながら犬夜叉の傍へ疾く走った。
だが、絶望に暮れる犬夜叉の目の前は真っ暗になった。
体は氷のように冷たくなり、次第に力が失せ、ゆらゆらと雪の上に倒れた。
竜舌蘭一門は滅亡した。
それは確実に進行はしていたが、決定付けたのはあの飛雪の一戦だった。
一門だけにあらず二百年来ともにしてきた剣も、仕える精鋭も、
何より唯一の恋人を失った劉銀竜は、もはやその勢力を挽回することは不可能であった。
――昏睡から目を覚ました時、俺はいつの間にか武蔵野にある村に戻り、楓の家の中にいた。
長く眠り続けたらしい。まだ体がゆらゆらして、まともではなかった。
「犬夜叉様。ようやく、お目を覚まされましたか」
かすかに耳元で冥加がいった。
「流麗様は不幸でございましたが、このたびは見事なご功績です」
「――――」
「近々西国から、あなた様へ賞金が出されますぞ」
俺はうめいた。体を動かすことができない。
じっと天井を見つめて、何かしらの躊躇いを感じつつ、冥加に銀竜の事を訊ねた。
そのことに冥加は、
「劉銀竜は、死にました」
小さく、静かにそう言った。
更に冥加は、あの後の銀竜のことを詳しく語ってくれた。
俺は俺にとって最高の姉を亡くし、俺を守る為に小竹は命を擲った。
それらを追うように銀竜は自ら命を落としたと聞くと、俺はひとしきりの失望に沈んだ。
涙まで溢れ、あの闘いにとても後悔を感じた。
もう三年になる。
俺も仲間も、風ように自由気ままな毎日を送っている。
あの旅も、あの血なまぐさい四日間の日々も忘れかけていたとき、俺はある話を聞いた。
「璋小竹の妹が唐国で生きている」
それを聞いてすぐに、俺は唐へ向った。
話は本当だった。唐の山岳地帯に、小竹の妹の馮美琳(フェン・メイリン)はいた。
馮美琳もまた半妖であるが、全くそうとは思えなかった。
小竹と同じくどこにでもいる、ごく普通の女性だった。
美琳は母方の一族とともに捕吏に襲われ、殺されたと聞いている。
本題を話す前に、俺はその事について美琳に訊ねた。
すると美琳はすんなりと答えた。
璋小竹が見たものは、間違いではない。
三百年前あの日、姉妹と母方の一族は県の捕吏に襲われた。
美琳は致命傷を負って意識を失ったが一命はとりとめ、
再び目を覚ますと、一族は死に、姉の姿もなかった。
既に姉も最悪な事態に見舞われていると絶望していたが、
まさか天下一の大妖怪の恋人ということも、倭にいたということは知らなかった。
姉妹の微妙な食い違いに、美琳は苦笑していた。
そして、俺は三年前のあの四日の内を美琳に明かした。
片言の華語で美琳と話していくうち、俺は小竹の本名と身の上を知った。
璋小竹の本名は馮麗玉。
彼女の父親の馮丹華は混じりもない、人間の男。武芸人だった。
母親は妖怪で、踊り子であった。
昔、武芸人の馮丹華はたった一つの刀法・飛翔刀を武器に、
平気に人を強制し、騙し、殺しを続けていた。
自分の手を一切汚さず、人を殺していたのだ。
馮丹華は、人であって人ではない。
いつしかそんな丹華の力に魅了した武芸人が集まりはじめた。
やがて千の武芸人と刀が集まった時、
丹華を頭目に残忍な刀の一門――巨大な千刀隊(チェンダオドゥイ)を建てた。
丹華が千刀隊の頭目になった時、その姿は一切みせない。
集った仲間や娘達を使って人を殺し、
千刀隊の仲間が一度でも裏切りなどみせると、丹華は娘達に殺すよう命じた。
姉妹は丹華に逆らえない。
丹華が死ぬまで、麗玉と美琳は丹華の奴隷でしかなかった。
だが丹華は誰よりも二人の娘だけに飛翔刀の技を伝え、その真意を語った。
たとえ殺戮を命じても、丹華は、娘達を心から愛していたことには違いない。
若くして丹華が死の病を患った時、彼は漸くその飛翔刀の最高的奥義を悟った。
迫る死と共に悟った、飛翔刀の最高奥義とは――
飛翔刀を含めあらゆる刀剣は人を殺すだけや、人を守る為だけのものでもない。
結局、何も生まれはしないということ。
刀剣とは持つべきに非ず、ゆえに飛翔刀(フェイシアンダオ)すなわち、非翔刀(フェイシアンダオ)なのだ。
馮丹華は人を扱い、唆し、殺し、感情と弱点を巧妙に利用したことによって、
畢生の修練で編み出した飛翔刀の最高的奥義を悟ったと、美琳は言った。
俺は頷いた。それからも更に美琳は言う。
馮丹華の死後、千刀隊は滅亡し、麗玉と美琳は刀を棄てた。
だがそのまもなく、母方の一族は捕吏の手によって滅び、それがきっかけに麗玉は再び刀を持った。
以後、父親と同じ道を歩み、形見の飛翔刀を用いて、
敵や恋人の銀竜の命を狙い、そして最後は飛翔刀によって自分を殺した。
大妖怪であった劉銀竜は、半妖の麗玉だけを一途に愛した。
麗玉も銀竜が好きだった。
二人の愛と情は、とても純白なもの。
それを通り超えた為に、二人は互いに不殺にはいれず、闘い合った。
「ふん……」
思わず俺は苦笑した――まるで俺も、二人と同じだ。
対する美琳はしんと黙る。
仲のいい姉と過ごしたわずかな思い出と、三年にしてやっと姉の死を悟った美琳はとても複雑だった。
だがそれは一瞬なもので、彼女は冷静に言った。
――闘いに参戦したものは全て、互いに生死の契りを交わした。
心は、永久に離れることはない。
今はもう、俺の手に刀はない。たとえ五十年経っても二度と刀は持たないと、そう決めている。
五十年後――刀のない風流な毎日を送り、毎日きっと仲間と酒宴をしている。
その宴の時には必ず、五十年間の人生を語り合っているに違いない。
俺が語るなら奈落を追い求める旅よりも、あの四日間を語る。
出始めは、まず姓と名だ。
流麗から始まって、劉銀竜、馮麗玉と続き、
それぞれの身分と過去を語って――最後はあの四日を語る。
野の花に清らかな風が吹くように、実際に見て、聞いた真実を俺は長々と語るのだ。
きっと涙もろくなった仲間の衣の袖はぐっしょりと濡れて重くなり、
その泪を拭いながら仲間と口を合わせてこう言うはずだ。
「五十年来、なんて夢や幻、泡影のように儚い人生なのだろう」、と……。
そういえば、流麗はあの天楼館で同じ曲を二度も吹いていた。
夢幻泡影という、得意の一曲。
秘曲の魂之舞とならんで、まさに人生の儚さを感ずる曲だった。
誰かが言っていた。
流麗の笑顔は春の野にそそぐ暖かな光のようで、誰にでも、たとえ人間もその魅力に惹かれる。
多くの妖や人間達の交わりを好み、酒も好んだ。
一族の弔いに毎夜の管を奏で、歌や詩を詠い――まるで、太陽のような女性だと。
だが精鋭一族の姫君である流麗は、現れる敵と、闘わずにはいられない。
一族や夫と生き別れた後、確信的に自分の幸福な結末など有りはしないと感ずいていた。
きっと、何よりの全てだった夫と出会う以前から、有り余る力で天下泰平を為し、
末期は英雄になると心に決めていたのだ。
だがその二つの定義の結論を、流麗は最後の闘いのさなかにきっとこう悟った。
武器はなく、英雄がいない世界こそが、本当の平和だと!
星が空の海に浮かぶこの晩、その下で俺は一人いる。
あの日と同じ夜――
耳をすませば、あの笛の音が聴こえてきそうな、そんな感じの夜だ。
いつもとは違う、神秘的な夜空の下で、俺は歌を作った。
死を恐れず、勇敢に闘い続けた英雄たちを悼む歌だ。
あれから三年が過ぎて、ようやく贈ることができた。
歌とか詩とか楽には、全く興味はない。ただ感情さえ伝わればそれでいいと思っている。
流麗もきっとそう思って、毎晩に一族に弔いの笛を捧げていたはずだ。
感情というものは、瞬間的に生まれるもの。
その時その気持ちは、紛れもない真実なのだ。
――必ず届け。
そう願って、俺は夜空の下で勇敢に闘い続けた英雄達に歌を捧げた。
倭 と 唐 に 英 雄 あ り
両 者 英 雄 比 類 な き 絶 世 す
戦 士 と い う 宿 命 を 負 い な が ら
表 の 心 は 愛 の 為 に 生 き
裏 の 心 は 憎 に 囚 わ れ る
た と え憎 に 囚 わ れ 死 し て 灰 塵 と な っ て も
英 雄 本 当 の 愛 を 棄 つ に い ら れ な い
【完】