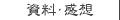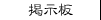「HERO-真の英雄- 壱」 優サマ
「春は何だか、とても眠くなるの。
父様とお館様に見つからないように、私が眠りに就く前に、きっと。
きっと明日、迎えに来て」
「夏を題に、久々に詩(うた)を書いた。
もしあの場所を覚えてさえいれば、砂の上に置いているから」
「秋の色は朱(あか)で、冬の色は白だ。
お前の肌は色白である故、朱も白も、どんな色も全て似合う」
「いつか、この瑠璃の小刀をお前にあげよう。
吾の大事な宝物だが、愛するお前にくれてやるとなら、何も悔いはない」
――戦国の世から五百年前。
竜舌蘭大魔王という唐の大妖怪が、一門を引き連れ、倭国を滅ぼそうとやって来た。
これまで多々異国を滅ぼし、倭も滅ぼそうとするこの一族に、勇敢に立ち向かう一人の男がいた。
日本の西国一帯を根城とする、古今無双の大妖怪一族の長だ。
当時の長は、何れこの世に在りたる、全妖と半妖の兄弟の祖父にあたる者。
だが大乱闘の内、男は致命傷を負い、竜舌蘭ら一門を唐へ送り返すことしかできなかった。
間もなく男は傷で亡くなり、男の息子が長となった事から、この英雄譚は続く。
西暦、一二八一年。
西国を根城とする大妖怪・闘牙王は一族を率い、武蔵国にいた。
闘牙王は一人、麗しい望月を瞬きもせず、ただじっと眺める。
とても感動する、神秘的な月夜だ。それ眺める闘牙王の背後に、人影が見えた。
「お館様」
女である。
年の頃なら、十七ほどか。
白銀の長い髪を頭頂部まであげて紐で括り、透き通るような黄金の目をし、片頬に二本ずつ、薄紫色の弧状を描いた線が浮かぶ。
上半身をずっしりと重い鎧で覆い、左肩から背にかけて、白くふうわりとした毛皮を垂らす。
左腰に、己の牙で鍛えた長剣を挿すこの娘の名は、流麗。
「全て、清牙王(せいがおう)や葦(あし)から聞いたようだな」
低い声で闘牙王は言った。
清牙王とは闘牙王の弟。
流麗の父親だ。
闘牙王と共に西国を治め、また闘いの内、数多危機に陥る闘牙王をよく救っている。
葦は流麗の母親で、清牙王の妻だ。
この葦の本性を知る者は、この闘牙王と清牙王と流麗だけ。
家来達には、故郷は備前であり、その国の高名な大妖怪一族の姫君、としか知らしていない。
長く艶やかな黒髪に、藍色を含んだ黒い目はまるで人間と変わらぬ姿。
何でもこの女性は、管絃をこよなく愛する。
「飛妖蛾一族を倒す事が出来ても、竜骨精との決着が、まだついてはいません。西国へ戻るには……」
「流麗、お前は、城に残る氷雪(ひせつ)共に、直に生まれる我が子が、哀れと思うか」
闘牙王の問いに、流麗は答えられない。
喉から先言葉が出ず、沈黙が続く。
「流麗」
更に闘牙王が言った。
「今にお前は従姉(あね)となるのだ。直生まれる我が子をしっかり、守ってくれ」
翌朝、一門は西国へ戻った。
その日の夜、流麗は父から外出の許可を得ると、一人、海辺へ来た。
つい二、三日前に、世間は立冬に入った。
空気は冷たく、昨日武蔵で見た月と星が、西国の空にも浮かんでいる。
砂浜に座し、冷たい空気を浴び、じっと夜空を眺めていると、闘牙王の妻・氷雪がどこかへ向っているのを見た。
流麗は何か嫌な予感がし、氷雪を呼び止めた。
「待て!」
流麗の声に、氷雪は立ち止まり、こちらを見た。
「流麗……こんな刻限に、一体何をしている?」
「それは私のセリフだ。懐妊する者が供無しで、どこに行く?まさか、また罪無き人を殺めるつもりか?」
「――罪無き人?笑止。これまで闘ってきた人や妖よりも、尚且つ罪深い者ですよ」
「――それは、何者?」
氷雪はにやりと冷笑し、答えた。
「そなたと同じ年頃の、人間の女」
「人間、だと?」
「流麗、旦那様が最近、新たな剣……鉄砕牙を持った意を知っているか?」
「――いや……」
「旦那様は十六夜という、その人間の女とつるんでいるのですよ。鉄砕牙は十六夜を守る為に、刀々斎が鍛えたもの」
「――――」
「そなたの知らぬ所で、清牙王も葦も旦那様と共に十六夜を助け、守っている。
そなたはどう思う?偉大な血筋を受け継がれた旦那様達が、人間という下等な生き物と共にするということは」
「父様も母様も、お館様も、他の妖怪や大妖怪と違って、お心が広く、優しい方。どの者にも大切に、親切にされる」
「わたくしは旦那様のそこに惚れた。哀れな身の上であるわたくしを、旦那様は何も言わず受け入れ、優しく抱いてくれた」
「――――」
「旦那様はわたくしのもの。人間などに取られてなるものか。十六夜を、邪魔者を今に殺めるぞよき!」
氷雪は本性を露にさせ、素早く走り出した。
向うところは人間の城。目的は、十六夜暗殺。
「ま、待て!」
流麗は氷雪の後を追いかける。
先回りし、氷雪の前に来ると、左手に持つ鞘から剣を抜き、刃を氷雪に向けた。
だが氷雪は特に恐れ戦く様子もなく、相変わらず冷静で流麗に言った。
「旦那様のお子を孕むわたくしに、牙を向けるという事は……殺すか?」
「殺すつもりは更々無い。けれど、どうしても行くとなら、私は容赦はせぬ!」
「ならばこちらも同じ事。邪魔するなら、そなたも我が毒爪の餌食となるまで!」
氷雪は黄緑色に光る爪を流麗に向け、そこから大妖怪も溶かす猛毒を発した。
流麗は牙の剣で毒爪を受け止めるが、その時、煙と共に異様な臭いが刃から立ち上がった。
剣が溶けているのだ。
「そなたは将来、一族の女王となる身!期待されるその身と命、おのれでも惜しいと思わぬか!」
「思わぬ!たとえ人間でも、お館様が大事にされる方を守る為なら、命など惜しまぬ!」
「愚か者!!!」
氷雪の毒に、とうとう剣は折れてしまった。
折れた剣に流麗は唖然とし、だが氷雪は怒涛の如く流麗に迫った。
「そなたも大妖怪の血を宿していながら、人間の肩を持つか!」
「――――」
「流麗、そなたはまことに妖怪の見方か!それとも、人間の見方か!?」
「私は……」
氷雪の問いに、流麗の心は何故か躊躇った。
「さあ、言え!」
「私は時に妖怪、時に人の見方だ。嘘は、言わない」
「――そう。ならば、たとえ一族でも生かすわけにはゆかぬ……死ね!」
氷雪は丸腰となった流麗に、再び爪を向けた。
冷たく厳しく、氷雪に容赦はない。
氷雪から逃げ切れず、流麗が死を覚悟したその瞬間、間に闘牙王が入り込んだ。
闘牙王は流麗を庇う為、咄嗟に左腕を伸ばし、だがその腕を氷雪は無惨にも毒爪で引き裂いてしまった。
血が飛び散り、闘牙王は右手で白く細い氷雪の腕を掴んだ。
すぐに、清牙王と葦も駆けつけた。
「父様、母様」
「無事か、流麗」
「お怪我は!?」
「――いいえ」
愛娘が無事と分かると、闘牙王と氷雪の方を眺めた。
「氷雪、こんな夜更けにどこへゆくか?」
「――――」
「どこへゆくか」
「――十六夜を、殺しにゆきます」
「何……?」
氷雪は目に涙を浮かべている。
濡れたその金色の目で闘牙王を見つめ、そして言った。
「旦那様、わたくしはあなたが愛おしい。
わたくしは……わたくしからあなたを奪おうとする十六夜が、憎くて、憎くて、たまらいのです」
「――――」
「わたくしの心を……癒して、下さいまするか……」
氷雪の頬をつたう涙を闘牙王は右手の親指でそっと拭い、そして氷雪に答えた。
「俺はお前への想いは、あの頃と全く変わってはおらん」
「――――」
「お前は子を孕んでいるのだ。闘うことは許されぬ」
「――――」
「今すぐに、城へ戻れ」
闘牙王は氷雪の腕を離し、背を向け、家路へ向った。
「兄貴、傷は平気か?」
氷雪に引き裂かれた傷から、鮮血が流れつたい、点々と地面に落ちる。
闘牙王は足を止め、首を少し横に向けて、清牙王に答えた。
「たかが擦り傷だ。帰るぞ」
翌日。
とても穏やかな日だ。
「母様、この部分がどうしても吹けません」
流麗は母の葦から竜笛の、ある曲を教わっていた。
その曲とは、秘曲・魂之舞。
葦自らが作曲した曲だ。
“清牙の妹(いも)は、鬼神も泣かす管絃の女”
管絃――つまり笛など管楽器と、琵琶など絃楽器の総称。
葦の管絃を聴く者は皆、上記の事を口あわせ、そう言っている。
やがて愛する男との間に娘が生まれ、娘にもこの秘曲を伝えようと思っていたが、
当の本人はある一部分が吹けず、次第に嫌になっていた。
「私の手と口は笛ではなく、筆と紙を持ち、歌や書を書いて、詠ずる方が合っているのです」
ついに流麗は、母から譲られた笛を、横の文机(ふづくえ)に置いた。
「私には、母様のような鬼を泣かすような楽を奏でることは、できないのですよ」
「そんな事はありません。ここ意外は完璧です」
「――――」
「さあ、もう一度吹いてごらんなさい」
葦は文机の上の竜笛を取り、流麗に手渡した。
嫌々笛を受け取り、流麗は再び、始めから魂之舞を吹いたが、やはり同じ。
行き詰る娘に、葦はふと、案を思いついた。
一方、闘牙王と清牙王は先日の武蔵へ再び足を運び、刀鍛冶の刀々斎の住処へやって来た。
「ヒドイッ!」
刀々斎が折れた流麗の剣を見た途端、わんわんと泣き出した。
それを慰めるように清牙王が言う。
「泣きたい気持ちはよう分かるぞ、刀々斎」
刀々斎、ほのわか涙を浮かべつつ、じろっと清牙王を見た。
「一体誰だ、剣をこんな目にしたのは」
清牙王は闘牙王の方へ目線をやると、当人は答えた。
「俺の妻の、毒爪だ」
「――氷雪か?おのれ氷雪……毎度無茶なことばかりしやがって」
「折れたものは、仕方あるまいさ」
清牙王は懐から、布に包んだ一本の鋭い牙を取り出した。
「昨夜、知り合いの斉資(なりすけ)という妖怪の薬師(くすし)を呼び、流麗の牙を抜いた」
牙の根には、まだ血が残っている。
刀々斎はその牙を持って、よく見た。
「ふん、悪くないな」
「刀々斎、二度目はないよう、頑丈にしてくれ」
刀々斎は早速剣の修復にとりかかり、その時に闘牙王は何よりの注文を刀々斎に告げた。
だがそれと同時に、首辺りから痛痒さを感じた。
何かと思いながら首筋に手をやり、指でつまむと、冥加だ。
「お館様。今日も変わらず美味しい血をして、冥加は――」
言い終わるまでに、闘牙王は冥加を酷くも潰した。
「お館様……何をなさいまするか……っ!」
相変わらず暢気な冥加に、闘牙王はギロリと冥加を見た。
「時折やってくる生姜に嘘をついてまで、俺はお前の姿を隠しているというのに。
お前は俺を放って、ここ数日ここにいる。この裏切り者」
「おい、冥加、今は兄貴の血を吸わぬ方が身の為だぞ」
「――はて、何故でしょう、清牙王様」
「兄貴は昨夜、氷雪に引き裂かれ、毒を受けたのだ。生憎その毒はまだ体内に残っている」
「ひ、氷雪様の毒爪を!?何ゆえ!?」
「実は昨夜、氷雪は十六夜を暗殺しようと向ったのだ。
偶々表にいた流麗が止めにかかったが、邪魔と、流麗が言った一言に氷雪は激怒し、流麗を先に殺そうとした。
間一髪兄貴が間合いに入ったら、このザマだ」
「氷雪の毒を受ければ無事にはすまねぇが、ようも平気にいられたな、大将」
「全て、流麗の摩訶不思議な力のお蔭だ」
「あの男姫か。あの姫はまっこと、存在自体摩訶不思議だ。だがそんな姫に惚れる男がいるんだよな」
「――――」
「出雲の嵩明良だったか」
刀々斎が、“嵩明良”と言った途端、闘牙王と清牙王の表情が一変険しくなった。
「あの男の名を言うな、刀々斎」
「聞いただけでも、胸くそ悪い」
どうも相変わらず嵩明良を敵として見るこの兄弟に、刀々斎は腕を止めた。
「ふん、何度でもあの男の名を呼んでやる。流麗と嵩明良は、今まであらゆる地方へ出かけ、口付けもした。
もはや、相思相愛よ。過去の事はいい加減水に流し、いい加減に嵩明良を受け入れたどうだ」
「――流麗に嵩明良は相応しくない。何れ女王の流麗の伴侶になる者は、心身共に強い者でなければならぬ」
「嵩明良は出雲の大妖怪だ。一族亡き後、嵩明良の奴はたった独りで故郷を治めている。
故に出雲国は他国よりも平穏無事と聴くぞ」
「関係あるものか。嵩明良は敵だ。敵と関れば流麗ばかりか、わが一族の命が危うくなる」
「これ以上我が娘の周りをうろつかぬよう、近々嵩明良に重い罰を処するつもりだ」
二人のこの言葉に刀々斎は言う言葉が失せ、再び剣の修復に取り掛かった。
「最近、耳にしたことがある」
暫くして闘牙王が言った。
「耳にしたこと?お館様、一体なんです?」
「――兄貴、それはもしや……竜舌蘭大魔王のことか?」
「そうだ。唐を離れ、この国の裏にでもいるのか、匂いはよく掴めぬが、近々日本に来るとも」
「父上も相当梃子摺られた相手が再び来るとなら、しかと気を引き締めねば。刀々斎よ、我が娘の剣はいつ頃に直る」
「そうさな……三日後の夜には直ろうか」
「ならば四日目の早朝に、娘を来さそう」
四日後。
剣は刀々斎の手で元に直り、流麗の手に再び戻ってきた。
「旦那様、あなたのお子でございます。さあ抱いてくださいませ」
間もなく、闘牙王と氷雪の間に息子が生まれた。
闘牙王は息子を抱く。
「名は既に、殺生丸、と決めました」
この夫婦の背後から、流麗はじっと見つめている。
氷雪が後ろを向き、にっこりと微笑み、流麗に告げた。
「流麗、ごらんなさい、そなたの従弟(おとうと)です」
「――――」
「これからはしっかりと、殺生丸をお守りするのですよ」
「既にお館様から言いつけられました。どうか、ご安心ください」
流麗が赤子を見るその目には、如何にも赤子が哀れという表情が浮かんでいた。
父様とお館様に見つからないように、私が眠りに就く前に、きっと。
きっと明日、迎えに来て」
「夏を題に、久々に詩(うた)を書いた。
もしあの場所を覚えてさえいれば、砂の上に置いているから」
「秋の色は朱(あか)で、冬の色は白だ。
お前の肌は色白である故、朱も白も、どんな色も全て似合う」
「いつか、この瑠璃の小刀をお前にあげよう。
吾の大事な宝物だが、愛するお前にくれてやるとなら、何も悔いはない」
――戦国の世から五百年前。
竜舌蘭大魔王という唐の大妖怪が、一門を引き連れ、倭国を滅ぼそうとやって来た。
これまで多々異国を滅ぼし、倭も滅ぼそうとするこの一族に、勇敢に立ち向かう一人の男がいた。
日本の西国一帯を根城とする、古今無双の大妖怪一族の長だ。
当時の長は、何れこの世に在りたる、全妖と半妖の兄弟の祖父にあたる者。
だが大乱闘の内、男は致命傷を負い、竜舌蘭ら一門を唐へ送り返すことしかできなかった。
間もなく男は傷で亡くなり、男の息子が長となった事から、この英雄譚は続く。
西暦、一二八一年。
西国を根城とする大妖怪・闘牙王は一族を率い、武蔵国にいた。
闘牙王は一人、麗しい望月を瞬きもせず、ただじっと眺める。
とても感動する、神秘的な月夜だ。それ眺める闘牙王の背後に、人影が見えた。
「お館様」
女である。
年の頃なら、十七ほどか。
白銀の長い髪を頭頂部まであげて紐で括り、透き通るような黄金の目をし、片頬に二本ずつ、薄紫色の弧状を描いた線が浮かぶ。
上半身をずっしりと重い鎧で覆い、左肩から背にかけて、白くふうわりとした毛皮を垂らす。
左腰に、己の牙で鍛えた長剣を挿すこの娘の名は、流麗。
「全て、清牙王(せいがおう)や葦(あし)から聞いたようだな」
低い声で闘牙王は言った。
清牙王とは闘牙王の弟。
流麗の父親だ。
闘牙王と共に西国を治め、また闘いの内、数多危機に陥る闘牙王をよく救っている。
葦は流麗の母親で、清牙王の妻だ。
この葦の本性を知る者は、この闘牙王と清牙王と流麗だけ。
家来達には、故郷は備前であり、その国の高名な大妖怪一族の姫君、としか知らしていない。
長く艶やかな黒髪に、藍色を含んだ黒い目はまるで人間と変わらぬ姿。
何でもこの女性は、管絃をこよなく愛する。
「飛妖蛾一族を倒す事が出来ても、竜骨精との決着が、まだついてはいません。西国へ戻るには……」
「流麗、お前は、城に残る氷雪(ひせつ)共に、直に生まれる我が子が、哀れと思うか」
闘牙王の問いに、流麗は答えられない。
喉から先言葉が出ず、沈黙が続く。
「流麗」
更に闘牙王が言った。
「今にお前は従姉(あね)となるのだ。直生まれる我が子をしっかり、守ってくれ」
翌朝、一門は西国へ戻った。
その日の夜、流麗は父から外出の許可を得ると、一人、海辺へ来た。
つい二、三日前に、世間は立冬に入った。
空気は冷たく、昨日武蔵で見た月と星が、西国の空にも浮かんでいる。
砂浜に座し、冷たい空気を浴び、じっと夜空を眺めていると、闘牙王の妻・氷雪がどこかへ向っているのを見た。
流麗は何か嫌な予感がし、氷雪を呼び止めた。
「待て!」
流麗の声に、氷雪は立ち止まり、こちらを見た。
「流麗……こんな刻限に、一体何をしている?」
「それは私のセリフだ。懐妊する者が供無しで、どこに行く?まさか、また罪無き人を殺めるつもりか?」
「――罪無き人?笑止。これまで闘ってきた人や妖よりも、尚且つ罪深い者ですよ」
「――それは、何者?」
氷雪はにやりと冷笑し、答えた。
「そなたと同じ年頃の、人間の女」
「人間、だと?」
「流麗、旦那様が最近、新たな剣……鉄砕牙を持った意を知っているか?」
「――いや……」
「旦那様は十六夜という、その人間の女とつるんでいるのですよ。鉄砕牙は十六夜を守る為に、刀々斎が鍛えたもの」
「――――」
「そなたの知らぬ所で、清牙王も葦も旦那様と共に十六夜を助け、守っている。
そなたはどう思う?偉大な血筋を受け継がれた旦那様達が、人間という下等な生き物と共にするということは」
「父様も母様も、お館様も、他の妖怪や大妖怪と違って、お心が広く、優しい方。どの者にも大切に、親切にされる」
「わたくしは旦那様のそこに惚れた。哀れな身の上であるわたくしを、旦那様は何も言わず受け入れ、優しく抱いてくれた」
「――――」
「旦那様はわたくしのもの。人間などに取られてなるものか。十六夜を、邪魔者を今に殺めるぞよき!」
氷雪は本性を露にさせ、素早く走り出した。
向うところは人間の城。目的は、十六夜暗殺。
「ま、待て!」
流麗は氷雪の後を追いかける。
先回りし、氷雪の前に来ると、左手に持つ鞘から剣を抜き、刃を氷雪に向けた。
だが氷雪は特に恐れ戦く様子もなく、相変わらず冷静で流麗に言った。
「旦那様のお子を孕むわたくしに、牙を向けるという事は……殺すか?」
「殺すつもりは更々無い。けれど、どうしても行くとなら、私は容赦はせぬ!」
「ならばこちらも同じ事。邪魔するなら、そなたも我が毒爪の餌食となるまで!」
氷雪は黄緑色に光る爪を流麗に向け、そこから大妖怪も溶かす猛毒を発した。
流麗は牙の剣で毒爪を受け止めるが、その時、煙と共に異様な臭いが刃から立ち上がった。
剣が溶けているのだ。
「そなたは将来、一族の女王となる身!期待されるその身と命、おのれでも惜しいと思わぬか!」
「思わぬ!たとえ人間でも、お館様が大事にされる方を守る為なら、命など惜しまぬ!」
「愚か者!!!」
氷雪の毒に、とうとう剣は折れてしまった。
折れた剣に流麗は唖然とし、だが氷雪は怒涛の如く流麗に迫った。
「そなたも大妖怪の血を宿していながら、人間の肩を持つか!」
「――――」
「流麗、そなたはまことに妖怪の見方か!それとも、人間の見方か!?」
「私は……」
氷雪の問いに、流麗の心は何故か躊躇った。
「さあ、言え!」
「私は時に妖怪、時に人の見方だ。嘘は、言わない」
「――そう。ならば、たとえ一族でも生かすわけにはゆかぬ……死ね!」
氷雪は丸腰となった流麗に、再び爪を向けた。
冷たく厳しく、氷雪に容赦はない。
氷雪から逃げ切れず、流麗が死を覚悟したその瞬間、間に闘牙王が入り込んだ。
闘牙王は流麗を庇う為、咄嗟に左腕を伸ばし、だがその腕を氷雪は無惨にも毒爪で引き裂いてしまった。
血が飛び散り、闘牙王は右手で白く細い氷雪の腕を掴んだ。
すぐに、清牙王と葦も駆けつけた。
「父様、母様」
「無事か、流麗」
「お怪我は!?」
「――いいえ」
愛娘が無事と分かると、闘牙王と氷雪の方を眺めた。
「氷雪、こんな夜更けにどこへゆくか?」
「――――」
「どこへゆくか」
「――十六夜を、殺しにゆきます」
「何……?」
氷雪は目に涙を浮かべている。
濡れたその金色の目で闘牙王を見つめ、そして言った。
「旦那様、わたくしはあなたが愛おしい。
わたくしは……わたくしからあなたを奪おうとする十六夜が、憎くて、憎くて、たまらいのです」
「――――」
「わたくしの心を……癒して、下さいまするか……」
氷雪の頬をつたう涙を闘牙王は右手の親指でそっと拭い、そして氷雪に答えた。
「俺はお前への想いは、あの頃と全く変わってはおらん」
「――――」
「お前は子を孕んでいるのだ。闘うことは許されぬ」
「――――」
「今すぐに、城へ戻れ」
闘牙王は氷雪の腕を離し、背を向け、家路へ向った。
「兄貴、傷は平気か?」
氷雪に引き裂かれた傷から、鮮血が流れつたい、点々と地面に落ちる。
闘牙王は足を止め、首を少し横に向けて、清牙王に答えた。
「たかが擦り傷だ。帰るぞ」
翌日。
とても穏やかな日だ。
「母様、この部分がどうしても吹けません」
流麗は母の葦から竜笛の、ある曲を教わっていた。
その曲とは、秘曲・魂之舞。
葦自らが作曲した曲だ。
“清牙の妹(いも)は、鬼神も泣かす管絃の女”
管絃――つまり笛など管楽器と、琵琶など絃楽器の総称。
葦の管絃を聴く者は皆、上記の事を口あわせ、そう言っている。
やがて愛する男との間に娘が生まれ、娘にもこの秘曲を伝えようと思っていたが、
当の本人はある一部分が吹けず、次第に嫌になっていた。
「私の手と口は笛ではなく、筆と紙を持ち、歌や書を書いて、詠ずる方が合っているのです」
ついに流麗は、母から譲られた笛を、横の文机(ふづくえ)に置いた。
「私には、母様のような鬼を泣かすような楽を奏でることは、できないのですよ」
「そんな事はありません。ここ意外は完璧です」
「――――」
「さあ、もう一度吹いてごらんなさい」
葦は文机の上の竜笛を取り、流麗に手渡した。
嫌々笛を受け取り、流麗は再び、始めから魂之舞を吹いたが、やはり同じ。
行き詰る娘に、葦はふと、案を思いついた。
一方、闘牙王と清牙王は先日の武蔵へ再び足を運び、刀鍛冶の刀々斎の住処へやって来た。
「ヒドイッ!」
刀々斎が折れた流麗の剣を見た途端、わんわんと泣き出した。
それを慰めるように清牙王が言う。
「泣きたい気持ちはよう分かるぞ、刀々斎」
刀々斎、ほのわか涙を浮かべつつ、じろっと清牙王を見た。
「一体誰だ、剣をこんな目にしたのは」
清牙王は闘牙王の方へ目線をやると、当人は答えた。
「俺の妻の、毒爪だ」
「――氷雪か?おのれ氷雪……毎度無茶なことばかりしやがって」
「折れたものは、仕方あるまいさ」
清牙王は懐から、布に包んだ一本の鋭い牙を取り出した。
「昨夜、知り合いの斉資(なりすけ)という妖怪の薬師(くすし)を呼び、流麗の牙を抜いた」
牙の根には、まだ血が残っている。
刀々斎はその牙を持って、よく見た。
「ふん、悪くないな」
「刀々斎、二度目はないよう、頑丈にしてくれ」
刀々斎は早速剣の修復にとりかかり、その時に闘牙王は何よりの注文を刀々斎に告げた。
だがそれと同時に、首辺りから痛痒さを感じた。
何かと思いながら首筋に手をやり、指でつまむと、冥加だ。
「お館様。今日も変わらず美味しい血をして、冥加は――」
言い終わるまでに、闘牙王は冥加を酷くも潰した。
「お館様……何をなさいまするか……っ!」
相変わらず暢気な冥加に、闘牙王はギロリと冥加を見た。
「時折やってくる生姜に嘘をついてまで、俺はお前の姿を隠しているというのに。
お前は俺を放って、ここ数日ここにいる。この裏切り者」
「おい、冥加、今は兄貴の血を吸わぬ方が身の為だぞ」
「――はて、何故でしょう、清牙王様」
「兄貴は昨夜、氷雪に引き裂かれ、毒を受けたのだ。生憎その毒はまだ体内に残っている」
「ひ、氷雪様の毒爪を!?何ゆえ!?」
「実は昨夜、氷雪は十六夜を暗殺しようと向ったのだ。
偶々表にいた流麗が止めにかかったが、邪魔と、流麗が言った一言に氷雪は激怒し、流麗を先に殺そうとした。
間一髪兄貴が間合いに入ったら、このザマだ」
「氷雪の毒を受ければ無事にはすまねぇが、ようも平気にいられたな、大将」
「全て、流麗の摩訶不思議な力のお蔭だ」
「あの男姫か。あの姫はまっこと、存在自体摩訶不思議だ。だがそんな姫に惚れる男がいるんだよな」
「――――」
「出雲の嵩明良だったか」
刀々斎が、“嵩明良”と言った途端、闘牙王と清牙王の表情が一変険しくなった。
「あの男の名を言うな、刀々斎」
「聞いただけでも、胸くそ悪い」
どうも相変わらず嵩明良を敵として見るこの兄弟に、刀々斎は腕を止めた。
「ふん、何度でもあの男の名を呼んでやる。流麗と嵩明良は、今まであらゆる地方へ出かけ、口付けもした。
もはや、相思相愛よ。過去の事はいい加減水に流し、いい加減に嵩明良を受け入れたどうだ」
「――流麗に嵩明良は相応しくない。何れ女王の流麗の伴侶になる者は、心身共に強い者でなければならぬ」
「嵩明良は出雲の大妖怪だ。一族亡き後、嵩明良の奴はたった独りで故郷を治めている。
故に出雲国は他国よりも平穏無事と聴くぞ」
「関係あるものか。嵩明良は敵だ。敵と関れば流麗ばかりか、わが一族の命が危うくなる」
「これ以上我が娘の周りをうろつかぬよう、近々嵩明良に重い罰を処するつもりだ」
二人のこの言葉に刀々斎は言う言葉が失せ、再び剣の修復に取り掛かった。
「最近、耳にしたことがある」
暫くして闘牙王が言った。
「耳にしたこと?お館様、一体なんです?」
「――兄貴、それはもしや……竜舌蘭大魔王のことか?」
「そうだ。唐を離れ、この国の裏にでもいるのか、匂いはよく掴めぬが、近々日本に来るとも」
「父上も相当梃子摺られた相手が再び来るとなら、しかと気を引き締めねば。刀々斎よ、我が娘の剣はいつ頃に直る」
「そうさな……三日後の夜には直ろうか」
「ならば四日目の早朝に、娘を来さそう」
四日後。
剣は刀々斎の手で元に直り、流麗の手に再び戻ってきた。
「旦那様、あなたのお子でございます。さあ抱いてくださいませ」
間もなく、闘牙王と氷雪の間に息子が生まれた。
闘牙王は息子を抱く。
「名は既に、殺生丸、と決めました」
この夫婦の背後から、流麗はじっと見つめている。
氷雪が後ろを向き、にっこりと微笑み、流麗に告げた。
「流麗、ごらんなさい、そなたの従弟(おとうと)です」
「――――」
「これからはしっかりと、殺生丸をお守りするのですよ」
「既にお館様から言いつけられました。どうか、ご安心ください」
流麗が赤子を見るその目には、如何にも赤子が哀れという表情が浮かんでいた。
「HERO-真の英雄- 弐」 優サマ
殺生丸が生まれ、既に二月が経った。
冬の寒さはより一段と深まる。
外庭で数人の侍女達が何やら、世間話をしている。
「それにしましても。殺生丸様がお生まれになってからか、穏やかな日が続きますね」
「こう穏やかな日々が続きますと、後々とても不吉な事が起こるのではないかと……」
「とても心配ですわ」
侍女のすぐ傍では、流麗が赤子の殺生丸を抱いて、あやしている。
それを眺めながら、侍女達は尚も世間話を続ける。
「思えば、姫様もご立派になられたものです」
「えぇ」
「ほんの少し前までは、殺生丸様のように、あんなに小さかったのに」
「今では旦那様達と闘いに行かれたり、何よりも近い将来、一族の女王となられる」
「時が流れるのは本当、早いものですわ」
流麗と殺生丸の姿は、城から見下ろす闘牙王と清牙王、葦にも見られていた。
「生まれてくる子は、人間であろうと妖怪であろうと同じ。見る度にそう思う」
「えぇ。ただ氷雪に、人に対する恨みを植えつけられなければよいのですが……」
庭の光景をしみじみと眺め、清牙王と葦は案ずる。
「姫姉様!」
「姫姉様!」
流麗の傍に、五人の子供達が走ってきた。
「どうしたの?」
一人の子が流麗に掌を見せた。
その掌に、息絶えた子供の鳥が乗っている。
「――これは……」
「巣から落ちていたみたいなの」
「それで今見つけたら、こんな事に……」
「まだ子供なのに、かわいそう!」
「姫姉様のお力で、生き返らせてあげて!」
「お願い!」
「お願い!」
流麗が生まれ持った摩訶不思議な力とは、生きとし生ける者の全て――
それが動物でも、治らぬ傷を跡もなく瞬時に癒したり、死者を容易に蘇らせられるという。
殺生丸を傍にいる侍女らに預けると、小鳥を左の掌に乗せ、右手で覆った。
小鳥を覆い隠したその手を口元に近づけ、ふっ、と、軽く息を吹き込む。
やがて右手を退け、子供達に小鳥を見せると、小鳥は弱弱しくも鳴声を発していた。
「生き返った!」
「生き返った!」
「やっぱり姫姉様すごーい!」
「虫でも食わせてあげたら、きっとすぐに元気になる。それは、お前達に任せようか」
流麗はそっと小鳥を子供達に預けた。
「ありがとう、姫姉様!」
「ありがとう!」
子供達は賑やかに、またどこかへ行ってしまった。
「男姫(おのこひめ)、死んだものを蘇らすのは、よくないぞ」
背後より若い、聞きなれた男の声がした。流麗が後ろを眺めると、果たしてそこに男の妖怪がそこにいた。
「嵩明良!」
正しく、出雲国を守り治める、大妖怪の嵩明良だ。
上々たる男前だが、故あってその左の頬には深い刀傷が残っている。
柵を間に、流麗は嵩明良の傍に寄る。
「よくないとは分かっているけど、あれは仕方がない」
「その摩訶不思議な力で、お館の傷も治したとな?」
「毎日したら、お館様のお怪我は早く治った。
それより嵩明良、母様の秘曲、私なりにアレンジして、全部吹けるようになった」
「まことか?」
「一番最初に嵩明良に聴かせようと、逢える日をずっと待っていた」
「――吹いてみせよ」
流麗は懐に挿す竜笛を取り出し、口元に近づけ、目を閉じながら吹いた。
夜に吹く竜笛の音は澄んだ夜気に響き、まるで透き通る。
だが昼の今も同じ。音色が辺りを響かせ、城の中までその澄んだ音が聴こえる。
――やがて一曲が吹き終えた。
笛を口元から離し、まっすぐと嵩明良を見て、訊ねた。
「嵩明良、これを聴いてどう思ったか、正直に言って」
「――葦様が吹け天国にいるようだが、お前が吹けば、やはり地獄に堕ちたようだ」
「――ばか嵩明良!もっと他に言う言葉はないのか!素敵だとか!心が和むとか!」
「正直に言ったまでだ」
「正直すぎる!ばか!バカ!馬鹿!」
怒った流麗は体のどこぞからハリセンを出し、悪口とともに嵩明良を何度も叩いた。
こんな事は最早日常茶飯事。
絶えぬハリセン攻撃と悪口を受けても、嵩明良は冷静に話を続けた。
「今日は笛を聴いたり、鳥の見物に来たのではない。今こそ、お館と清牙王様にあれを言おうと来たのだ」
嵩明良がそう言うと、流麗のハリセンはぴたりと止まった。
「――あれを?本当に?」
「嵩明良!」
頭上から清牙王の声がした。
流麗と嵩明良は上を見上げる。
見上げると、窓の向こうから清牙王が怒鳴り散らした。
「我らは貴様に話すことは無いぞ!」
「父様……」
「お願いです!どうか今日こそ吾の話を聴いてください!」
「黙れ!我らの気が変わらぬ内に、今すぐに去(いぬ)れ!」
「一分だけでもいい!話を!」
「くどい!!!」
「――――」
「嵩明良!私が十数え終えぬ内に消えねば、黄泉へと送ろうぞ!!!」
「あなた、何もそこまで……」
清牙王の暴言と、闘牙王が下を見つめるあの鋭い目に、嵩明良は、あの日の出来事よりも更に恐怖を感じた。
清牙王は家来に命じると、数を数え始めた。
命じられた家来達は、何と弓矢と投槍を持ち、先を嵩明良に向ける。
そして十を数え終え、去らぬ嵩明良に遂に矢と投槍が放たれた。
数え切れぬ矢と槍に、流麗は腰に下げる剣を抜き、嵩明良の前に立った。
「やめてっ!」
素早く飛ぶ矢と槍を流麗は剣で斬り捨て、嵩明良を守ろうとする。
一族の姫君がその前に立てば、家臣達はこれ以上の刃を放つことはできない。
矢の雨は止み、流麗は背後を見た。
見ると既に、そこに嵩明良の姿はいなかった。
「――何故あそこまで酷い事ばかりするのですか!」
その夜、流麗は昼間の事を闘牙王と清牙王に迫った。
流麗の声が、城中に響く。
「嵩明良は一分だけでもよいと……たかが一分、話を聞いてもよかったじゃありませんか!」
「流麗、お言葉を慎みなさい。お館様や、父様の前ですよ」
「母様は今は黙っていてください!」
流麗の大声に、ついに殺生丸が火が点いたように泣き出した。
その泣声を聞きつけて、氷雪が急いでその部屋に来た。
「何ですか、流麗!殺生丸の目前で、大声を出すなど!――さ、殺生丸、母様が来ましたよ」
氷雪は殺生丸を抱き、あやす。
清牙王は葦と氷雪を見、そして言った。
「行け」
低い声で言う清牙王の命令に、葦と、殺生丸を抱く氷雪はやがてそこを出て行った。
鈍い、重い扉が閉まった音がしたと同時に、そこはしんと静まり返る。
闘牙王はこの父娘に背を向け、じっと窓から外を眺めている。
「流麗」
清牙王が言った。
「嵩明良には嘗て、如月(にょげつ)という許婚がいた」
「――知っています。以前、嵩明良から聞きました」
「命を懸け、如月を守ると断言したにも関わらず、敵と起こした大乱闘の末、
嵩明良は一族も、たった一人の許婚も守れず、死なせたのだ」
「――――」
「この父がそんな男に、大事な娘を宜しく頼むと言えるとでも思うか!?」
「嵩明良の一族も、如月も、仕方がなかったのです、何も嵩明良が全て悪いわけではありません!」
「――流麗、いい加減に目を覚ますのだ。お前は既に、嵩明良に騙されているのだぞ」
「違います!私は嵩明良に、愛されているのです!!!」
「それ以上言うな!」
ずっと黙っていた闘牙王が遂に口をあけた。
いつもの優しい表情が、とても恐ろしく、闘牙王は鋭い眼差しで流麗を見た。
「流麗、今後嵩明良に逢う事、この城を出る事両方を禁じる」
「そんな……」
「命を破った時は、重く罰を処する。分かったな」
「待ってください!納得できません!」
「話は済んだ。流麗、部屋へ戻れ」
「戻りません!もう暫く、私の話を聞いてください!――父様!」
流麗が清牙王を見たら、清牙王は流麗から視線を逸らした。
流麗は今度は、闘牙王の方へ視線を送り、尚も迫る。
「――お館様!」
「――失せろ……」
「お願いです!今一度話を聞いて、考え直してください!」
「失せろ!!!」
闘牙王はついに感情的になり、流麗を暴言で押さえつけた。
――流麗が部屋を出た時、葦はずっとそこで待っていた。
「母様……」
流麗は悔しさと哀しさの両方の感情が、涙として出てきた。
葦は泣きじゃくる娘をそっと抱く。
「流麗、母はお前と嵩明良を夫婦(おとめ)にする事を、賛成していますよ」
「――――」
「流麗、嵩明良を放っておくことはなりません。明日の朝、嵩明良の許へお行きなさい」
「――――」
「流麗」
「――はい……」
「ならばさあ、お部屋へ戻り、今日はもう休みましょう」
翌日、何やら城中が騒がしい。
侍女も家臣も、手分けして流麗を探している。
剣はなく、鎧があるということは、闘いに行ったのではない。
大勢であちらやこちらを探し回っても、流麗は見つからず、清牙王は苛つきと不安が同時に募り、落ち着かず、うろうろとしている。
それを目前にする妻の葦が言った。
「あなた、どうか落ち着いて。案じずとも、きっともうすぐ流麗は帰ってきますわ」
清牙王は立ち止まって、葦を見た。
「お前は流麗の行方は知らんのか」
「知っていれば、今頃連れ戻しに行っていますよ」
流麗の行方を言ってしまえば、清牙王はすぐさまそこへ向い、きっと昨夜よりも大騒ぎになる。
葦はとにかく知らぬふりをして、清牙王にただ声をかけるだけだった。
「清牙よ、流麗姫の行方、教えてあげましょうか?」
氷雪の声がした。
扉の横で腕を組み、切れ長の目で清牙王を見つめている。
「――氷雪……流麗の行方を知っているのか!?」
「姫は出雲にいるわ。まだ陽も昇らぬ刻限に……誰かさんがそっと行かせたのね」
それだけ言うと、氷雪はまた部屋へ戻っていった。
何故氷雪がその事を知っているのか――。
聞いて清牙王は、急いで外へ出る扉へ向った。
葦は前を通る清牙王に、葦は素早く、清牙王が総身纏う白い毛皮を掴み、引き止めた。
「出雲へ行っては、なりません」
止める葦に、清牙王はギロリと葦を睨み、大声をあげた。
「何故流麗を出雲へ行かせた!!!」
「流麗と嵩明良を思ってのこと。それ以外の理由はありませぬ」
「――どういう事だ」
「流麗と嵩明良は互いに信頼し、愛し合っています。
共に生きようとする二人を引き裂くとは、決してあってはならぬこと。
昨夜の流麗は一晩中泣いてばかりで、一睡もしていません」
「兄や私が下す命は、流麗の身を守る為だ。それを背き、流麗を危険極まりないよそ者に逢わそうとは……。
母親でありながら、貴様は娘が死んでもよいというのだな!!!」
「いいえ。わたくしは、何もかも禁じ、縛り付けては、何れ流麗の心は壊れてしまうのではないかと……そちらの方が心配で……」
「――――」
「あなた、お願いです。もうお兄様と一緒に、これ以上流麗を苦しめるような事は、おやめになって……」
葦は清牙王の毛皮から手を離した。
やがて清牙王は、椅子に座り、一度大きく息を吐いてから、静かに流麗の帰りを待った。
「――流麗、やはり帰ったほうがいい」
「どうして?」
「お前が出雲へ行ったという事が知られては……」
「たとえこの事がバレても、覚悟はある。構うものか」
流麗はごろんと花畑の上に横になり、広く青い空を一杯眺めた。
「きっと――嵩明良は鳥や動物や、あの空と同じ。心は蒼くて、汚(けが)れていないのね」
「――――」
「母様だけは、私達の見方だよ。夫婦にする事を何より賛成している」
「たとえ葦様が賛成しても、お館らが賛成してくれねば……意味がない」
「――どうしたらいいかな……」
「流麗、お前はまことに、この世に英雄がいると思うか?」
「思うさ――“英雄”、とたった二文字だけだけど、もの凄く幅広い定義があるのだもの」
「例えば何だ?」
「武芸で、非力な人を敵から守り、救う。
他は――医術も。医師は我が身をけずって、他人が患った大病や怪我を、懸命になって治す」
「――――」
「ごく普通の人が、ごく些細なことを為しても、他人が見て思ったら、その人は英雄。
けれど私は嵩明良も、私の身の周りにいる者はみんな英雄ではなく、勇敢だと思っている」
「勇敢……たとえそうでも、そう思ってくれると嬉しいばかりだ」
流麗は突然に起き上がると、真顔になって嵩明良に話した。
「嵩明良、前に、お館様と父様から聞いた話……私のお爺様が唐へ返した竜舌蘭一門が、再び日本に来るらしい」
「あぁ、知っている」
「毎日海を渡って、血の臭いがここに届く」
「あぁ」
「せめて、竜舌蘭が来る前にもう一度、お館様と父様に想いを話して、今度こそ許しを得よう」
「――――」
「嵩明良、私はお前が傍にいないなんて嫌。
もし一緒になっても、なれぬままでも、敵と闘う時は絶対に、私に哀しい姿を見せないで……」
「――流麗……」
「約束を……」
「あぁ、必ず。必ずする」
流麗は嵩明良の左の頬の古傷をそっと撫でて、確かにこう言った。
「前に嵩明良は、私を愛していると言った。私も、嵩明良を心から愛している」
流麗と嵩明良は互いに、そっとその口と口を重ね合わせた。
物陰から二人の様子を見ていた闘牙王は、静かにそこを離れ、西国へ――十六夜の許へ向った。
冬の寒さはより一段と深まる。
外庭で数人の侍女達が何やら、世間話をしている。
「それにしましても。殺生丸様がお生まれになってからか、穏やかな日が続きますね」
「こう穏やかな日々が続きますと、後々とても不吉な事が起こるのではないかと……」
「とても心配ですわ」
侍女のすぐ傍では、流麗が赤子の殺生丸を抱いて、あやしている。
それを眺めながら、侍女達は尚も世間話を続ける。
「思えば、姫様もご立派になられたものです」
「えぇ」
「ほんの少し前までは、殺生丸様のように、あんなに小さかったのに」
「今では旦那様達と闘いに行かれたり、何よりも近い将来、一族の女王となられる」
「時が流れるのは本当、早いものですわ」
流麗と殺生丸の姿は、城から見下ろす闘牙王と清牙王、葦にも見られていた。
「生まれてくる子は、人間であろうと妖怪であろうと同じ。見る度にそう思う」
「えぇ。ただ氷雪に、人に対する恨みを植えつけられなければよいのですが……」
庭の光景をしみじみと眺め、清牙王と葦は案ずる。
「姫姉様!」
「姫姉様!」
流麗の傍に、五人の子供達が走ってきた。
「どうしたの?」
一人の子が流麗に掌を見せた。
その掌に、息絶えた子供の鳥が乗っている。
「――これは……」
「巣から落ちていたみたいなの」
「それで今見つけたら、こんな事に……」
「まだ子供なのに、かわいそう!」
「姫姉様のお力で、生き返らせてあげて!」
「お願い!」
「お願い!」
流麗が生まれ持った摩訶不思議な力とは、生きとし生ける者の全て――
それが動物でも、治らぬ傷を跡もなく瞬時に癒したり、死者を容易に蘇らせられるという。
殺生丸を傍にいる侍女らに預けると、小鳥を左の掌に乗せ、右手で覆った。
小鳥を覆い隠したその手を口元に近づけ、ふっ、と、軽く息を吹き込む。
やがて右手を退け、子供達に小鳥を見せると、小鳥は弱弱しくも鳴声を発していた。
「生き返った!」
「生き返った!」
「やっぱり姫姉様すごーい!」
「虫でも食わせてあげたら、きっとすぐに元気になる。それは、お前達に任せようか」
流麗はそっと小鳥を子供達に預けた。
「ありがとう、姫姉様!」
「ありがとう!」
子供達は賑やかに、またどこかへ行ってしまった。
「男姫(おのこひめ)、死んだものを蘇らすのは、よくないぞ」
背後より若い、聞きなれた男の声がした。流麗が後ろを眺めると、果たしてそこに男の妖怪がそこにいた。
「嵩明良!」
正しく、出雲国を守り治める、大妖怪の嵩明良だ。
上々たる男前だが、故あってその左の頬には深い刀傷が残っている。
柵を間に、流麗は嵩明良の傍に寄る。
「よくないとは分かっているけど、あれは仕方がない」
「その摩訶不思議な力で、お館の傷も治したとな?」
「毎日したら、お館様のお怪我は早く治った。
それより嵩明良、母様の秘曲、私なりにアレンジして、全部吹けるようになった」
「まことか?」
「一番最初に嵩明良に聴かせようと、逢える日をずっと待っていた」
「――吹いてみせよ」
流麗は懐に挿す竜笛を取り出し、口元に近づけ、目を閉じながら吹いた。
夜に吹く竜笛の音は澄んだ夜気に響き、まるで透き通る。
だが昼の今も同じ。音色が辺りを響かせ、城の中までその澄んだ音が聴こえる。
――やがて一曲が吹き終えた。
笛を口元から離し、まっすぐと嵩明良を見て、訊ねた。
「嵩明良、これを聴いてどう思ったか、正直に言って」
「――葦様が吹け天国にいるようだが、お前が吹けば、やはり地獄に堕ちたようだ」
「――ばか嵩明良!もっと他に言う言葉はないのか!素敵だとか!心が和むとか!」
「正直に言ったまでだ」
「正直すぎる!ばか!バカ!馬鹿!」
怒った流麗は体のどこぞからハリセンを出し、悪口とともに嵩明良を何度も叩いた。
こんな事は最早日常茶飯事。
絶えぬハリセン攻撃と悪口を受けても、嵩明良は冷静に話を続けた。
「今日は笛を聴いたり、鳥の見物に来たのではない。今こそ、お館と清牙王様にあれを言おうと来たのだ」
嵩明良がそう言うと、流麗のハリセンはぴたりと止まった。
「――あれを?本当に?」
「嵩明良!」
頭上から清牙王の声がした。
流麗と嵩明良は上を見上げる。
見上げると、窓の向こうから清牙王が怒鳴り散らした。
「我らは貴様に話すことは無いぞ!」
「父様……」
「お願いです!どうか今日こそ吾の話を聴いてください!」
「黙れ!我らの気が変わらぬ内に、今すぐに去(いぬ)れ!」
「一分だけでもいい!話を!」
「くどい!!!」
「――――」
「嵩明良!私が十数え終えぬ内に消えねば、黄泉へと送ろうぞ!!!」
「あなた、何もそこまで……」
清牙王の暴言と、闘牙王が下を見つめるあの鋭い目に、嵩明良は、あの日の出来事よりも更に恐怖を感じた。
清牙王は家来に命じると、数を数え始めた。
命じられた家来達は、何と弓矢と投槍を持ち、先を嵩明良に向ける。
そして十を数え終え、去らぬ嵩明良に遂に矢と投槍が放たれた。
数え切れぬ矢と槍に、流麗は腰に下げる剣を抜き、嵩明良の前に立った。
「やめてっ!」
素早く飛ぶ矢と槍を流麗は剣で斬り捨て、嵩明良を守ろうとする。
一族の姫君がその前に立てば、家臣達はこれ以上の刃を放つことはできない。
矢の雨は止み、流麗は背後を見た。
見ると既に、そこに嵩明良の姿はいなかった。
「――何故あそこまで酷い事ばかりするのですか!」
その夜、流麗は昼間の事を闘牙王と清牙王に迫った。
流麗の声が、城中に響く。
「嵩明良は一分だけでもよいと……たかが一分、話を聞いてもよかったじゃありませんか!」
「流麗、お言葉を慎みなさい。お館様や、父様の前ですよ」
「母様は今は黙っていてください!」
流麗の大声に、ついに殺生丸が火が点いたように泣き出した。
その泣声を聞きつけて、氷雪が急いでその部屋に来た。
「何ですか、流麗!殺生丸の目前で、大声を出すなど!――さ、殺生丸、母様が来ましたよ」
氷雪は殺生丸を抱き、あやす。
清牙王は葦と氷雪を見、そして言った。
「行け」
低い声で言う清牙王の命令に、葦と、殺生丸を抱く氷雪はやがてそこを出て行った。
鈍い、重い扉が閉まった音がしたと同時に、そこはしんと静まり返る。
闘牙王はこの父娘に背を向け、じっと窓から外を眺めている。
「流麗」
清牙王が言った。
「嵩明良には嘗て、如月(にょげつ)という許婚がいた」
「――知っています。以前、嵩明良から聞きました」
「命を懸け、如月を守ると断言したにも関わらず、敵と起こした大乱闘の末、
嵩明良は一族も、たった一人の許婚も守れず、死なせたのだ」
「――――」
「この父がそんな男に、大事な娘を宜しく頼むと言えるとでも思うか!?」
「嵩明良の一族も、如月も、仕方がなかったのです、何も嵩明良が全て悪いわけではありません!」
「――流麗、いい加減に目を覚ますのだ。お前は既に、嵩明良に騙されているのだぞ」
「違います!私は嵩明良に、愛されているのです!!!」
「それ以上言うな!」
ずっと黙っていた闘牙王が遂に口をあけた。
いつもの優しい表情が、とても恐ろしく、闘牙王は鋭い眼差しで流麗を見た。
「流麗、今後嵩明良に逢う事、この城を出る事両方を禁じる」
「そんな……」
「命を破った時は、重く罰を処する。分かったな」
「待ってください!納得できません!」
「話は済んだ。流麗、部屋へ戻れ」
「戻りません!もう暫く、私の話を聞いてください!――父様!」
流麗が清牙王を見たら、清牙王は流麗から視線を逸らした。
流麗は今度は、闘牙王の方へ視線を送り、尚も迫る。
「――お館様!」
「――失せろ……」
「お願いです!今一度話を聞いて、考え直してください!」
「失せろ!!!」
闘牙王はついに感情的になり、流麗を暴言で押さえつけた。
――流麗が部屋を出た時、葦はずっとそこで待っていた。
「母様……」
流麗は悔しさと哀しさの両方の感情が、涙として出てきた。
葦は泣きじゃくる娘をそっと抱く。
「流麗、母はお前と嵩明良を夫婦(おとめ)にする事を、賛成していますよ」
「――――」
「流麗、嵩明良を放っておくことはなりません。明日の朝、嵩明良の許へお行きなさい」
「――――」
「流麗」
「――はい……」
「ならばさあ、お部屋へ戻り、今日はもう休みましょう」
翌日、何やら城中が騒がしい。
侍女も家臣も、手分けして流麗を探している。
剣はなく、鎧があるということは、闘いに行ったのではない。
大勢であちらやこちらを探し回っても、流麗は見つからず、清牙王は苛つきと不安が同時に募り、落ち着かず、うろうろとしている。
それを目前にする妻の葦が言った。
「あなた、どうか落ち着いて。案じずとも、きっともうすぐ流麗は帰ってきますわ」
清牙王は立ち止まって、葦を見た。
「お前は流麗の行方は知らんのか」
「知っていれば、今頃連れ戻しに行っていますよ」
流麗の行方を言ってしまえば、清牙王はすぐさまそこへ向い、きっと昨夜よりも大騒ぎになる。
葦はとにかく知らぬふりをして、清牙王にただ声をかけるだけだった。
「清牙よ、流麗姫の行方、教えてあげましょうか?」
氷雪の声がした。
扉の横で腕を組み、切れ長の目で清牙王を見つめている。
「――氷雪……流麗の行方を知っているのか!?」
「姫は出雲にいるわ。まだ陽も昇らぬ刻限に……誰かさんがそっと行かせたのね」
それだけ言うと、氷雪はまた部屋へ戻っていった。
何故氷雪がその事を知っているのか――。
聞いて清牙王は、急いで外へ出る扉へ向った。
葦は前を通る清牙王に、葦は素早く、清牙王が総身纏う白い毛皮を掴み、引き止めた。
「出雲へ行っては、なりません」
止める葦に、清牙王はギロリと葦を睨み、大声をあげた。
「何故流麗を出雲へ行かせた!!!」
「流麗と嵩明良を思ってのこと。それ以外の理由はありませぬ」
「――どういう事だ」
「流麗と嵩明良は互いに信頼し、愛し合っています。
共に生きようとする二人を引き裂くとは、決してあってはならぬこと。
昨夜の流麗は一晩中泣いてばかりで、一睡もしていません」
「兄や私が下す命は、流麗の身を守る為だ。それを背き、流麗を危険極まりないよそ者に逢わそうとは……。
母親でありながら、貴様は娘が死んでもよいというのだな!!!」
「いいえ。わたくしは、何もかも禁じ、縛り付けては、何れ流麗の心は壊れてしまうのではないかと……そちらの方が心配で……」
「――――」
「あなた、お願いです。もうお兄様と一緒に、これ以上流麗を苦しめるような事は、おやめになって……」
葦は清牙王の毛皮から手を離した。
やがて清牙王は、椅子に座り、一度大きく息を吐いてから、静かに流麗の帰りを待った。
「――流麗、やはり帰ったほうがいい」
「どうして?」
「お前が出雲へ行ったという事が知られては……」
「たとえこの事がバレても、覚悟はある。構うものか」
流麗はごろんと花畑の上に横になり、広く青い空を一杯眺めた。
「きっと――嵩明良は鳥や動物や、あの空と同じ。心は蒼くて、汚(けが)れていないのね」
「――――」
「母様だけは、私達の見方だよ。夫婦にする事を何より賛成している」
「たとえ葦様が賛成しても、お館らが賛成してくれねば……意味がない」
「――どうしたらいいかな……」
「流麗、お前はまことに、この世に英雄がいると思うか?」
「思うさ――“英雄”、とたった二文字だけだけど、もの凄く幅広い定義があるのだもの」
「例えば何だ?」
「武芸で、非力な人を敵から守り、救う。
他は――医術も。医師は我が身をけずって、他人が患った大病や怪我を、懸命になって治す」
「――――」
「ごく普通の人が、ごく些細なことを為しても、他人が見て思ったら、その人は英雄。
けれど私は嵩明良も、私の身の周りにいる者はみんな英雄ではなく、勇敢だと思っている」
「勇敢……たとえそうでも、そう思ってくれると嬉しいばかりだ」
流麗は突然に起き上がると、真顔になって嵩明良に話した。
「嵩明良、前に、お館様と父様から聞いた話……私のお爺様が唐へ返した竜舌蘭一門が、再び日本に来るらしい」
「あぁ、知っている」
「毎日海を渡って、血の臭いがここに届く」
「あぁ」
「せめて、竜舌蘭が来る前にもう一度、お館様と父様に想いを話して、今度こそ許しを得よう」
「――――」
「嵩明良、私はお前が傍にいないなんて嫌。
もし一緒になっても、なれぬままでも、敵と闘う時は絶対に、私に哀しい姿を見せないで……」
「――流麗……」
「約束を……」
「あぁ、必ず。必ずする」
流麗は嵩明良の左の頬の古傷をそっと撫でて、確かにこう言った。
「前に嵩明良は、私を愛していると言った。私も、嵩明良を心から愛している」
流麗と嵩明良は互いに、そっとその口と口を重ね合わせた。
物陰から二人の様子を見ていた闘牙王は、静かにそこを離れ、西国へ――十六夜の許へ向った。