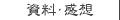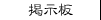「贅沢な世界の中に・・・。ぱあと6」 神久夜サマ
月と一番星が並んでいた。
「綺麗だねぇ、一番星」
「そうか?」
「あんたに感性ってもんは無いわけ」
「さぁね」
「でもさぁ、どうして一番星はあんなに輝いているんだろうね」
「さぁ」
「どうして、月はあんなに青白いんだろう」
「・・・」
「きっとね、夜の闇を照らすのに疲れてしまったんだよ、月は」
「お前は・・・」
「そして、きっと、小さいのに大きな月に立ち向かっていく一番星は神様に敬意を表されるんだね」
「俺は」
「月はね、それでも闇を照らさなくては、いけないの」
「・・・」
「何故なら、人々がとても不安になるからよ。
だって、月は人々が生まれた時から存在し、皆を照らしてくれたんだもの」
「おい」
「なあに?」
贅沢な世界の中に(ぱあと6)
「試合を始める」
劉慶が重々しく言う。
そこは、山の中とは思えない広々とした場所だった。
まるで町の家を全て焼き払ったときのような広さだ、と蛮骨は思う。
ただ、家を焼き払った時のように家の残骸はない。
この場所には何もなかった。
見物人も空から(彼らは妖怪に乗っていた)2、3人見下ろしているぐらいだ。
草も生えていない。
―ここは何があったんだ。
幼き頃、母から聞いたことがあった。
―蛮骨、知ってる?
妖怪とかね、邪悪なものがそこでとても因縁を残して死んだ場合、
その土地には100年たっても草木が生えないそうよ。
道理で。
この土地の地面の色は黒いように思える。
この山なら赤土であるはずだが。
蛮骨は、この山を歩いてここまでたどり着く中、幾度となく足をつきそうになった。
そのときに見たのだ。
赤土の色を。
赤土といっても橙の色に近い、見ていると吐き気がしてきそうな、濃厚な色。
そんな色がここの土地だけ真っ黒に近い黒という事など、有り得るだろうか?
自然界の色でここまで闇の深さがにじみ出るような黒、など。
見渡す限り、黒だった。
それなのに、周りが山に囲まれているせいで、青々と茂った緑が気に入らない。
そして、目の前で黒い戦闘服に包んだ彼女も気に入るほど気に入ったわけではなかった。
「−規則として、
武器の使用は、可とする。
相手が負けを認めた場合のみ、勝利とする。
−尚、負けを認めぬ場合、死に至る事もある。
駄目だ、と思った場合、すぐに負けを認めよ。
命までは盗らぬ。
それで、よろしいか」
劉慶の声が響き渡った。
「いいよ」
「っしゃ」
彼は互いの顔を交互に見た後、手を振り上げる。
「始めっ!」
*
彼の声の後、
風が、吹き渡った・・・ように思えた。
「はああっ!!」
暖李が飛来骨を振り被る。
最初から得意の得物で勝負する気らしい。
決着は早めに決めようということか。
「来やがれ」
彼は左手で右肩を掴み、その右手には拳が握られていた。
「飛来骨っ!!」
―ブンッ
という、音と共に以外にも早く飛来骨は飛んできた。
「ちっ」
―ガキッ
彼は右の拳で飛来骨を受け止めた。
「・・・馬鹿力だね」
暖李はにやりと笑う。
暖李にはもう、得物の飛来骨は残っていなかった。
蛮骨が、今、握っている。
「武器は、取り上げちまえばこっちのもんさ」
「それ、あんた使いこなせるのかい?」
暖李はまた、不敵に笑う。
「―使いこなせるに、決まってんだろ!」
蛮骨はその得物を振り被る。
しかし、投げたわけではなかった。
そのまま暖李に向かって走り始めたのだ。
「ちっ。
あれで打身を食らわす気か・・・!!」
暖李の顔から笑みが消える。
仕方が無い、とばかりに暖李は鎖を取り出す。
「それで、この飛来骨と対抗しようってのか!?
見るからにこっちの方が強そうだけどな!!」
蛮骨は遠慮無しに暖李に向かって飛来骨を叩きつける。
しかし、それは当たる事は無く、ブンッ!と唸り声を上げて宙を掻いた。
「・・・そんなんで対抗するわけ無いだろ、馬鹿」
暖李は蛮骨の足元を鎖で掬う。
「!おわっ!」
―ダンッ
と音を立てて蛮骨は下に叩きつけられる。
―ピシッ
鎖が蛮骨の手を叩く。
「あがっ」
とっさに飛来骨から手が離れる。
すかさず暖李は飛来骨を拾い上げた。
危ないとばかりに蛮骨はその場を離れる。
「さぁ、もういっちょやろうか」
「まぁた最初からやり直しかよ。
折角あそこまで攻めといてよぉ」
蛮骨の右手からは感覚が消えうせていた。
だが、まだ動くという事は骨折などしてないだろう。
まだ、使える・・・はずだ。
左手で右手を掴み蛮骨は渋い顔をする。
「右手は、もう使えないだろ」
蛮骨が危ぶんでいたことを暖李がさらりと言う。
「ふんっ」と蛮骨が言った所で、負け惜しみにしか聞こえなかった。
―ブンッ
と音を立てて飛来骨は宙を舞う。
それは暖李の真上に投げられた。
「何!?」
彼が飛来骨に一瞬気を奪われた。
そこをすかさず暖李は蛮骨の懐に鎖を食らわす。
「がはっ」
その鎖を腹にくらい、蛮骨は吐血をする。
しかし、それでも立っているというところが、打たれ強い、と暖李は思った。
―しかし、倒れていれば避(よ)けられたものを。
「くっそー」
蛮骨は口を拭う。
そこへ後ろから鈍い衝撃が走る。
―ドンッ
今度こそ、彼は吹っ飛ぶ。
飛来骨が後ろから襲ってきたのだ。
「がはっ」
彼は地面に吐血する。
背中からも流血し、蛮骨は地面に倒れこむ。
―くそっ!
こんな汚ねえ地面になんかへばり付きたくねぇのによ。
蛮骨はまだ感覚の残っている左手でなんとか起き上がろうとする。
そこで暖李が刀を抜いて走ってくる。
―左手を潰す気か。
「そうは、させねぇよ」
蛮骨は渾身の力で即座に立ち上がった。
それは思っていた以上に早く、その上、その左手は暖李の顔を殴りつけた。
「ちっ」
―ザザザッ
と音を立てて暖李は踏みとどまる。
ペッと口から血を吐く。
―そうか。
と蛮骨は納得する。
―ここで、何人の奴が殺されたのだろう。
『色んな、秘密があるんだ』
『名前、言いな』
―そういう事か・・・?
『いつ試験するの?』
『きゃあっ』
―何があるんだ、一体・・・!!
「飛来骨っ!」
暖李の投げた飛来骨が右腕に当たった。
しかし、それを蛮骨は払いのけるようにして叩き落す。
「くっ」
暖李がしかめっ面をする。
「おい」
「なんだ」
「此処で、何があった」
「この、土の色のことをいっているのか」
「そうだよ」
蛮骨の声には怒りが含まれているように思えた。
「別に、なんもないさ」
「この土の色はなんだ。
この土の色の意味だけでも言えよ」
はーっと暖李はため息をつく。
「ここにはね、翠子という巫女がいた。
その巫女はね、とても強くって、大概の妖怪なら全て浄化してたんだよ。
んで、その巫女を恐れた妖怪たちはね、ある人間を繋ぎに使って一体化した。
そして、翠子とその妖怪たちは何日にもわたって戦った・・・。
死んだけどね、どっちとも。
・・・。
それで、戦った主な場所が此処。
・・・うん、此処。
だからね、此処はね翠子とその妖怪たちの血を存分に吸ってるの。
黒くて当たり前。
分かった?」
此処までを言うと、
「じゃ、始めようか」
と、また構える。
「・・・違うんじゃねぇのか?」
蛮骨が尋ねる。
「違わない事は無いと思うけど?
何せ、伝説だから本当とも言わないけど」
彼は、暖李がしれっとした口調で言うのが気に食わなかった。
「だから、お前がここで修行者を殺していったんじゃねぇかって言ってんだよ!!」
「「「「「!!」」」」」
その言葉はその場にいた全てのものを緊張させた。
黙っていた劉慶が言葉を発する。
遠くにいるので声が届くように大きな声で話しているのだろうが、
それは、叫び声に聞こえた。
「言いがかりをつけるな!!
暖李はそんなことはせん!
暖李を動揺させるな!!
試験にならない!!」
それは怒りを含んでいるように蛮骨は思えた。
「・・・悪かったよ。
余計な詮索して」
そして、蛮骨は息をつき、そして、「始めようぜ」と言う。
暖李は、今度はにやりともしなかった。
*
「私の、負けだよ」
暖李は飛んだ。
宙を舞った。
地面に堕ちたところで別に外傷があったわけではないが、
堕ちた所を蛮骨に抑えられ、自分の得物の刀でのどを突きつけられた。
全身に痛みが走っていた。
だから、こういわざるを得なかった。
勿論、余力としては暖李のほうが勝っていた。
蛮骨は出血が多く、その後、貧血で倒れた。
時は、もう、夕刻だった。
「綺麗だねぇ、一番星」
「そうか?」
「あんたに感性ってもんは無いわけ」
「さぁね」
「でもさぁ、どうして一番星はあんなに輝いているんだろうね」
「さぁ」
「どうして、月はあんなに青白いんだろう」
「・・・」
「きっとね、夜の闇を照らすのに疲れてしまったんだよ、月は」
「お前は・・・」
「そして、きっと、小さいのに大きな月に立ち向かっていく一番星は神様に敬意を表されるんだね」
「俺は」
「月はね、それでも闇を照らさなくては、いけないの」
「・・・」
「何故なら、人々がとても不安になるからよ。
だって、月は人々が生まれた時から存在し、皆を照らしてくれたんだもの」
「おい」
「なあに?」
贅沢な世界の中に(ぱあと6)
「試合を始める」
劉慶が重々しく言う。
そこは、山の中とは思えない広々とした場所だった。
まるで町の家を全て焼き払ったときのような広さだ、と蛮骨は思う。
ただ、家を焼き払った時のように家の残骸はない。
この場所には何もなかった。
見物人も空から(彼らは妖怪に乗っていた)2、3人見下ろしているぐらいだ。
草も生えていない。
―ここは何があったんだ。
幼き頃、母から聞いたことがあった。
―蛮骨、知ってる?
妖怪とかね、邪悪なものがそこでとても因縁を残して死んだ場合、
その土地には100年たっても草木が生えないそうよ。
道理で。
この土地の地面の色は黒いように思える。
この山なら赤土であるはずだが。
蛮骨は、この山を歩いてここまでたどり着く中、幾度となく足をつきそうになった。
そのときに見たのだ。
赤土の色を。
赤土といっても橙の色に近い、見ていると吐き気がしてきそうな、濃厚な色。
そんな色がここの土地だけ真っ黒に近い黒という事など、有り得るだろうか?
自然界の色でここまで闇の深さがにじみ出るような黒、など。
見渡す限り、黒だった。
それなのに、周りが山に囲まれているせいで、青々と茂った緑が気に入らない。
そして、目の前で黒い戦闘服に包んだ彼女も気に入るほど気に入ったわけではなかった。
「−規則として、
武器の使用は、可とする。
相手が負けを認めた場合のみ、勝利とする。
−尚、負けを認めぬ場合、死に至る事もある。
駄目だ、と思った場合、すぐに負けを認めよ。
命までは盗らぬ。
それで、よろしいか」
劉慶の声が響き渡った。
「いいよ」
「っしゃ」
彼は互いの顔を交互に見た後、手を振り上げる。
「始めっ!」
*
彼の声の後、
風が、吹き渡った・・・ように思えた。
「はああっ!!」
暖李が飛来骨を振り被る。
最初から得意の得物で勝負する気らしい。
決着は早めに決めようということか。
「来やがれ」
彼は左手で右肩を掴み、その右手には拳が握られていた。
「飛来骨っ!!」
―ブンッ
という、音と共に以外にも早く飛来骨は飛んできた。
「ちっ」
―ガキッ
彼は右の拳で飛来骨を受け止めた。
「・・・馬鹿力だね」
暖李はにやりと笑う。
暖李にはもう、得物の飛来骨は残っていなかった。
蛮骨が、今、握っている。
「武器は、取り上げちまえばこっちのもんさ」
「それ、あんた使いこなせるのかい?」
暖李はまた、不敵に笑う。
「―使いこなせるに、決まってんだろ!」
蛮骨はその得物を振り被る。
しかし、投げたわけではなかった。
そのまま暖李に向かって走り始めたのだ。
「ちっ。
あれで打身を食らわす気か・・・!!」
暖李の顔から笑みが消える。
仕方が無い、とばかりに暖李は鎖を取り出す。
「それで、この飛来骨と対抗しようってのか!?
見るからにこっちの方が強そうだけどな!!」
蛮骨は遠慮無しに暖李に向かって飛来骨を叩きつける。
しかし、それは当たる事は無く、ブンッ!と唸り声を上げて宙を掻いた。
「・・・そんなんで対抗するわけ無いだろ、馬鹿」
暖李は蛮骨の足元を鎖で掬う。
「!おわっ!」
―ダンッ
と音を立てて蛮骨は下に叩きつけられる。
―ピシッ
鎖が蛮骨の手を叩く。
「あがっ」
とっさに飛来骨から手が離れる。
すかさず暖李は飛来骨を拾い上げた。
危ないとばかりに蛮骨はその場を離れる。
「さぁ、もういっちょやろうか」
「まぁた最初からやり直しかよ。
折角あそこまで攻めといてよぉ」
蛮骨の右手からは感覚が消えうせていた。
だが、まだ動くという事は骨折などしてないだろう。
まだ、使える・・・はずだ。
左手で右手を掴み蛮骨は渋い顔をする。
「右手は、もう使えないだろ」
蛮骨が危ぶんでいたことを暖李がさらりと言う。
「ふんっ」と蛮骨が言った所で、負け惜しみにしか聞こえなかった。
―ブンッ
と音を立てて飛来骨は宙を舞う。
それは暖李の真上に投げられた。
「何!?」
彼が飛来骨に一瞬気を奪われた。
そこをすかさず暖李は蛮骨の懐に鎖を食らわす。
「がはっ」
その鎖を腹にくらい、蛮骨は吐血をする。
しかし、それでも立っているというところが、打たれ強い、と暖李は思った。
―しかし、倒れていれば避(よ)けられたものを。
「くっそー」
蛮骨は口を拭う。
そこへ後ろから鈍い衝撃が走る。
―ドンッ
今度こそ、彼は吹っ飛ぶ。
飛来骨が後ろから襲ってきたのだ。
「がはっ」
彼は地面に吐血する。
背中からも流血し、蛮骨は地面に倒れこむ。
―くそっ!
こんな汚ねえ地面になんかへばり付きたくねぇのによ。
蛮骨はまだ感覚の残っている左手でなんとか起き上がろうとする。
そこで暖李が刀を抜いて走ってくる。
―左手を潰す気か。
「そうは、させねぇよ」
蛮骨は渾身の力で即座に立ち上がった。
それは思っていた以上に早く、その上、その左手は暖李の顔を殴りつけた。
「ちっ」
―ザザザッ
と音を立てて暖李は踏みとどまる。
ペッと口から血を吐く。
―そうか。
と蛮骨は納得する。
―ここで、何人の奴が殺されたのだろう。
『色んな、秘密があるんだ』
『名前、言いな』
―そういう事か・・・?
『いつ試験するの?』
『きゃあっ』
―何があるんだ、一体・・・!!
「飛来骨っ!」
暖李の投げた飛来骨が右腕に当たった。
しかし、それを蛮骨は払いのけるようにして叩き落す。
「くっ」
暖李がしかめっ面をする。
「おい」
「なんだ」
「此処で、何があった」
「この、土の色のことをいっているのか」
「そうだよ」
蛮骨の声には怒りが含まれているように思えた。
「別に、なんもないさ」
「この土の色はなんだ。
この土の色の意味だけでも言えよ」
はーっと暖李はため息をつく。
「ここにはね、翠子という巫女がいた。
その巫女はね、とても強くって、大概の妖怪なら全て浄化してたんだよ。
んで、その巫女を恐れた妖怪たちはね、ある人間を繋ぎに使って一体化した。
そして、翠子とその妖怪たちは何日にもわたって戦った・・・。
死んだけどね、どっちとも。
・・・。
それで、戦った主な場所が此処。
・・・うん、此処。
だからね、此処はね翠子とその妖怪たちの血を存分に吸ってるの。
黒くて当たり前。
分かった?」
此処までを言うと、
「じゃ、始めようか」
と、また構える。
「・・・違うんじゃねぇのか?」
蛮骨が尋ねる。
「違わない事は無いと思うけど?
何せ、伝説だから本当とも言わないけど」
彼は、暖李がしれっとした口調で言うのが気に食わなかった。
「だから、お前がここで修行者を殺していったんじゃねぇかって言ってんだよ!!」
「「「「「!!」」」」」
その言葉はその場にいた全てのものを緊張させた。
黙っていた劉慶が言葉を発する。
遠くにいるので声が届くように大きな声で話しているのだろうが、
それは、叫び声に聞こえた。
「言いがかりをつけるな!!
暖李はそんなことはせん!
暖李を動揺させるな!!
試験にならない!!」
それは怒りを含んでいるように蛮骨は思えた。
「・・・悪かったよ。
余計な詮索して」
そして、蛮骨は息をつき、そして、「始めようぜ」と言う。
暖李は、今度はにやりともしなかった。
*
「私の、負けだよ」
暖李は飛んだ。
宙を舞った。
地面に堕ちたところで別に外傷があったわけではないが、
堕ちた所を蛮骨に抑えられ、自分の得物の刀でのどを突きつけられた。
全身に痛みが走っていた。
だから、こういわざるを得なかった。
勿論、余力としては暖李のほうが勝っていた。
蛮骨は出血が多く、その後、貧血で倒れた。
時は、もう、夕刻だった。
「贅沢な世界の中に・・・。ぱあと7」 神久夜サマ
「蛮骨、人が生きていることに何の意味があるだろう」
「どういう意味だ」
「人は死ぬんだ」
蛮骨は答えなかった。
「死ねば、何も意味を持たないんじゃないのか」
「歴史に残れば良いんじゃねぇのか」
「そうかな。死んだ後、歴史に残ってもてはやされて嬉しいだろうか。
そもそも、永遠でない人類の歴史に残って何が楽しいだろう」
「・・・お前は何が言いたいんだ」
蛮骨は眉をひそめる。
「私は、何故自分がここに存在しているのか、分からない」
蛮骨は、黙っていた。
がさっと音がする。
陽気に声をあげたのは蛇骨だった。
「あれぇ?兄貴、なんでこんなとこにいるんだよ?」
「お前こそ、何しに来たんだ」
「別に。兄貴を探しにきただけ。
・・・何話してたんだ?」
暖李は笑みをこぼす。
それが自嘲の笑みなのか、蛇骨の無邪気さ故かは分からない。
「人は、何故存在するんだろう。生きるんだろう。
きっと死ぬのに」
少し黙って、蛇骨は答える。
「生きていることを楽しむことに意味があるんじゃねぇのか。
だから、人は苦しくなれば死にたがるし、逆に幸せを求めて闘う」
「・・・そう、そう・・・かな」
贅沢な世界の中に・・・。(ぱあと7)
ぴしゃん、という水滴が滴る音がして蛮骨は目を覚ます。
洞窟の奥にいるような気がした。
それでも、目を開けてみると、上にはただの天井しかない。
少し、期待が外れたような気がして蛮骨は寝返りをうつ。
そして、気付く。
俺は、確か広々として、何も無い場所にいたんじゃないのか。
がばっと起き上がると、後ろから声が聞こえた。
素っ頓狂な声だった。
「起きたのか!?」
目を丸くして此方を見る少女を見る。
「・・・俺、どうしたんだ」
別に。とだけ言って少女はまた手ぬぐいを洗い出す。
丁寧に絞り畳んだかと思うと、蛮骨の額にぴしゃとつける。
「てっ」
「寝てな。まだ起きていいような体の状態じゃない」
暖李はそのまま押さえつけるようにして蛮骨を寝かせる。
「俺、どうしたんだよ」
蛮骨は二度目の質問を発す。
「・・・貧血で倒れたんだ。
あれだけの出血をしたのに、よく之だけの時間で起きられたね」
今度は答えた。
どうやらはぐらかす気もなかったらしい。
そして、そんなに昏睡していたわけでもなさそうだ。
「・・・よく、死ななかったね」
それは、褒美を上げる母親の顔に似ていた。
「・・・他の奴は、死んだのか」
蛮骨がことの内容を理解していることを暖李は承知していた。
だから頷いた。
「なんで」
一拍間を空けて暖李が口を開く。
「此処に来る奴が、全て修行をしに来ると思う?」
「・・・違うのか」
「違うね。此処は、伝説の土地なんだ。
此処の奴ら全員で闘えば一国なんて滅ぼせるんだよ」
暖李は冷酷な笑みを浮かべる。
「だから、どこの大名も税を取らない。
此処は、領地じゃない。
・・・そしたらさ、まわしものがくるんだよ。
中から壊そうって魂胆かね」
蛮骨は、少し考える風をしてから言う。
「だから、試験・・・か」
「そういうこと。試験で、殺すんだ。
一人ずつね。
でも、あんたはそういう風じゃなかった。
じゃあ、連れも同じだろ?
・・・本当に修行をしに来たやつらなんだな」
先ほどの冷酷な顔とは打って変わって懐かしそうな笑みをこぼす。
「何年ぶりかな」
懐かしそうな笑みをこぼす暖李にこんなことは聞きたくなかったが、
意を決して蛮骨は尋ねる。
「なんで、殺すんだよ」
「・・・殺そうとも、思ってないよ。
ただ、私は血に酔うんだ。
殺された人には悪いけどね」
暖李は苦笑してみせる。
その苦笑が長年の鍛錬の賜物だと蛮骨は思った。
それほど、上手い。
だが、蛮骨は違うと思った。
「殺さなくて、いいんじゃねぇのか。
脅して帰せば良いんじゃねぇのか」
ふぅとため息をついて暖李はうつむく。
「本当はね。一国なんて滅ぼせるなんて、嘘だ。
そんなの一族かかっても無理なんだよ。
勿論、小国なら勝てるだろうが、大国なら無理だ。
だけど、あっちはこっちの規模を知らない。
・・・そして、村のある場所もね。
結界が張ってあるんだ。村の、巫女が張ってるんだけどね。
たまに、緩む。
そしたら、たまに入ってこれるやつがいるんだよ。
ホント、たまにね。
そしたら、場所が分かってしまうだろ?
のろしでもあげられたら、この村は終わりだ。
結界っていっても霊力の強い奴がいるわけじゃない。
敵国に霊力の強い巫女なんかいてみろ。
すぐに結界はとかれる。
攻め込まれる、だ」
「それで、殺していくのか」
「村を、守るためだ」
悲しそうに笑った顔が本音だと、蛮骨は思った。
*
「兄貴!」
それからいくらもたたず、ばんっと戸の開く音がした。
「大丈夫かよ〜」
今にも泣きそうな顔をしてよってくる蛇骨を見ると、
微笑がこぼれる。
「大丈夫だって」
顔を覗きこんだ蛇骨の頭をぽんと叩く。
「おい!暖李!
てめぇ、兄貴に何しやがった!!」
蛮骨の傍らにいた女に蛇骨はにらみを利かせる。
それを流すように笑ってから、暖李は答える。
「別に。ただ、試験をしただけ。
・・・少し、珍しい、ね」
うつむいたその顔に影がかかっているにも関わらず、
開いた口は少ししかあいていなかったにも関わらず、
蛇骨はその微笑が最高の喜びを意味すると思った。
「どういう意味だ」
「人は死ぬんだ」
蛮骨は答えなかった。
「死ねば、何も意味を持たないんじゃないのか」
「歴史に残れば良いんじゃねぇのか」
「そうかな。死んだ後、歴史に残ってもてはやされて嬉しいだろうか。
そもそも、永遠でない人類の歴史に残って何が楽しいだろう」
「・・・お前は何が言いたいんだ」
蛮骨は眉をひそめる。
「私は、何故自分がここに存在しているのか、分からない」
蛮骨は、黙っていた。
がさっと音がする。
陽気に声をあげたのは蛇骨だった。
「あれぇ?兄貴、なんでこんなとこにいるんだよ?」
「お前こそ、何しに来たんだ」
「別に。兄貴を探しにきただけ。
・・・何話してたんだ?」
暖李は笑みをこぼす。
それが自嘲の笑みなのか、蛇骨の無邪気さ故かは分からない。
「人は、何故存在するんだろう。生きるんだろう。
きっと死ぬのに」
少し黙って、蛇骨は答える。
「生きていることを楽しむことに意味があるんじゃねぇのか。
だから、人は苦しくなれば死にたがるし、逆に幸せを求めて闘う」
「・・・そう、そう・・・かな」
贅沢な世界の中に・・・。(ぱあと7)
ぴしゃん、という水滴が滴る音がして蛮骨は目を覚ます。
洞窟の奥にいるような気がした。
それでも、目を開けてみると、上にはただの天井しかない。
少し、期待が外れたような気がして蛮骨は寝返りをうつ。
そして、気付く。
俺は、確か広々として、何も無い場所にいたんじゃないのか。
がばっと起き上がると、後ろから声が聞こえた。
素っ頓狂な声だった。
「起きたのか!?」
目を丸くして此方を見る少女を見る。
「・・・俺、どうしたんだ」
別に。とだけ言って少女はまた手ぬぐいを洗い出す。
丁寧に絞り畳んだかと思うと、蛮骨の額にぴしゃとつける。
「てっ」
「寝てな。まだ起きていいような体の状態じゃない」
暖李はそのまま押さえつけるようにして蛮骨を寝かせる。
「俺、どうしたんだよ」
蛮骨は二度目の質問を発す。
「・・・貧血で倒れたんだ。
あれだけの出血をしたのに、よく之だけの時間で起きられたね」
今度は答えた。
どうやらはぐらかす気もなかったらしい。
そして、そんなに昏睡していたわけでもなさそうだ。
「・・・よく、死ななかったね」
それは、褒美を上げる母親の顔に似ていた。
「・・・他の奴は、死んだのか」
蛮骨がことの内容を理解していることを暖李は承知していた。
だから頷いた。
「なんで」
一拍間を空けて暖李が口を開く。
「此処に来る奴が、全て修行をしに来ると思う?」
「・・・違うのか」
「違うね。此処は、伝説の土地なんだ。
此処の奴ら全員で闘えば一国なんて滅ぼせるんだよ」
暖李は冷酷な笑みを浮かべる。
「だから、どこの大名も税を取らない。
此処は、領地じゃない。
・・・そしたらさ、まわしものがくるんだよ。
中から壊そうって魂胆かね」
蛮骨は、少し考える風をしてから言う。
「だから、試験・・・か」
「そういうこと。試験で、殺すんだ。
一人ずつね。
でも、あんたはそういう風じゃなかった。
じゃあ、連れも同じだろ?
・・・本当に修行をしに来たやつらなんだな」
先ほどの冷酷な顔とは打って変わって懐かしそうな笑みをこぼす。
「何年ぶりかな」
懐かしそうな笑みをこぼす暖李にこんなことは聞きたくなかったが、
意を決して蛮骨は尋ねる。
「なんで、殺すんだよ」
「・・・殺そうとも、思ってないよ。
ただ、私は血に酔うんだ。
殺された人には悪いけどね」
暖李は苦笑してみせる。
その苦笑が長年の鍛錬の賜物だと蛮骨は思った。
それほど、上手い。
だが、蛮骨は違うと思った。
「殺さなくて、いいんじゃねぇのか。
脅して帰せば良いんじゃねぇのか」
ふぅとため息をついて暖李はうつむく。
「本当はね。一国なんて滅ぼせるなんて、嘘だ。
そんなの一族かかっても無理なんだよ。
勿論、小国なら勝てるだろうが、大国なら無理だ。
だけど、あっちはこっちの規模を知らない。
・・・そして、村のある場所もね。
結界が張ってあるんだ。村の、巫女が張ってるんだけどね。
たまに、緩む。
そしたら、たまに入ってこれるやつがいるんだよ。
ホント、たまにね。
そしたら、場所が分かってしまうだろ?
のろしでもあげられたら、この村は終わりだ。
結界っていっても霊力の強い奴がいるわけじゃない。
敵国に霊力の強い巫女なんかいてみろ。
すぐに結界はとかれる。
攻め込まれる、だ」
「それで、殺していくのか」
「村を、守るためだ」
悲しそうに笑った顔が本音だと、蛮骨は思った。
*
「兄貴!」
それからいくらもたたず、ばんっと戸の開く音がした。
「大丈夫かよ〜」
今にも泣きそうな顔をしてよってくる蛇骨を見ると、
微笑がこぼれる。
「大丈夫だって」
顔を覗きこんだ蛇骨の頭をぽんと叩く。
「おい!暖李!
てめぇ、兄貴に何しやがった!!」
蛮骨の傍らにいた女に蛇骨はにらみを利かせる。
それを流すように笑ってから、暖李は答える。
「別に。ただ、試験をしただけ。
・・・少し、珍しい、ね」
うつむいたその顔に影がかかっているにも関わらず、
開いた口は少ししかあいていなかったにも関わらず、
蛇骨はその微笑が最高の喜びを意味すると思った。