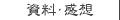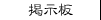「朧月夜」 神久夜サマ
「殺生丸さまっ!」
こちらに駆けて来る少女がいた。
それは、私に笑顔を教えてくれた者。
決して失ってはならぬ。
私の傍ではきっと失ってしまう。
だから―・・・。
「良いのですか?殺生丸様。」
「何がだ。」
「りんを置いていったことですが・・・。」
「なんだ、その事か。」
彼はさして気にもしていない様子でこう言った。
「恋しいのか?ならば、私の傍を離れてりんのところへ行ってくれても構わんのだぞ。」
その言葉は、一見とげが有る様だが、
実際言われてみた者は拍子抜けするほど優しさが含まれていた。
そして、彼の顔もまた微笑んでいた。
何が嬉しいのか。何が楽しいのか。
長年お供をしてきた邪見にもわからない微笑だった。
そして、目的地。
まるで、平安時代の都のように広く、そして、華やかな場所だった。
そんな場所でこちらに駆けてくる女がいた。
「殺ちゃん!!」
その女は本当に嬉しそうな顔で駆け寄ってくる。
「母上。お変わりなく、元気そうで。」
少し笑ったような表情で言う殺生丸に彼女は言う。
「いやねvv一応、危篤なのよ?余命、1年だってvv」
分かったような、分からないような理屈と、本当に他人事のように話す母親に
すっかりペースを崩されてしまった、殺生丸だった。
が、そんなことは言ってられない。
自分の母親の命だ。
「一体どうしたと言うんです?治す方法は?」
「あぁ、良いのよvv死にたいからvv」
彼は一瞬言葉を失った。
あくまで笑顔を絶やさない事にも、驚かされた。
しかし、彼女の笑顔の中にこれほどの悲しみを見たのは初めてだった。それに、彼は驚愕した。
「さ、御殿の中にお入んなさいvv」
御殿へ入ると、ぞろぞろと僕たちが降伏する。
それは、見慣れた光景であった。
が、彼はこんな僕たちを知らない。
子供の頃、見慣れた僕が、こんなにも顔が良く似ているのに、まるで別人だった。
主人の余命を知り、悲しみに打ちひしがれているとでもいうようだった。
いや、そうなのだ。
「母上・・・。」
「でねvv」
殺生丸の言葉を彼女はさえぎった。
「もうそろそろ、殺ちゃんにも結婚して欲しいのvv」
「は?」
何を言い出すのかと思いきや、こんな時にこんな話を持ち出すとは。
殺生丸は頭が痛くなる思いだった。
「それは、ようございますvv」
「わたくし達、殺生丸様のご幼少の頃からそれをずっと待っていたんでございますのvv」
「殺生丸様の花嫁様となれば、美人に相違ありませんわvv」
「そんな方にお仕え出来るなんてvv」
「わたくし達、果報者ですわね〜vv」
・・・話が勝手に進んでいく・・・。彼はそう思った。
この僕5人組は母が小さい頃から母に付きっ切りで、母も気に入って近くに置くものだから
一層ハイテンションになっていく、そんな者達だった。
年が近いせいか、仕えているというよりは友達感覚であった。
しかし、殺生丸は気付いた。気付いていた。
彼女達の明るい雰囲気の裏にまた、限りない悲しみが潜んでいるという事に。
「ふふっ。それは良かったわね。」
彼女は穏やかな調子で笑う。
しかし、殺生丸にとって、これほど不安な事はなかった。
母は、一度たりとも僕の心の迷いに気が付かないときはなかった。
それが、殺生丸が気が付いているのに彼女が気が付かないなんて事があろうか。
まさか、気が付いて見ぬ振りをしているのではと色々考えをめぐらせていたとき。
「殺ちゃん、何考えているの?」
「え。」
殺生丸は顔を上げた。
考えていて、今更ながらに気が付いた。
母は、自分の考えている事を読めなかった事はない。
いつも考え事をしているとその考えをぴたりと当てるのだ。
「何故?」と聞くと、「だって、殺ちゃんの母様だもの。」と思い切り微笑んで迷いを消してくれた。
だから、知られたくない悩みがあるとき、母の前は危険地帯だった。
そんな母が、「ヨメナイ?」
・・・どうしたというのだろう。
「あのね、殺ちゃん。」
「はい。」
「『りん』っていう子と結婚する?」
「は?」
「連れてるんでしょ?人間の女の子。聞いたわよ刀刀斎にvv」
あの老いぼれ・・・。余計な事を・・・。
どうせ、犬夜叉か誰かに聞いたか、そうでなければ上空から覗き見でもしたのだろう。
「し、しかし、人間を一番忌み嫌っておられたのは母上でしょう?」
焦った風に殺生丸は話す。人間や妖怪等関係なく、結婚することがいやだったのだ。
しかし、彼女の反応は、思い通りに行かなかった。
「じゃ、殺ちゃんは、許嫁の楼蘭ちゃんと結婚するのね?」
「は?」
楼蘭というのは、彼の幼馴染だった。
だが、それだけの関係で、許嫁になっていたとは、彼は、知らなかった。
「な、何故、楼蘭が許嫁なのです?」
「あのね。殺ちゃんが生まれる前に、もし、両者に特別な想いが無ければ、
この二人は結婚させよう。ってことになってたのよvv」
「それは、父上も同意なされた事ですか?」
「そうよ。楼蘭ちゃんのご両親が私達の僕の中で一番強かったのは知ってるわよね?」
「は。」
「だからよ。魏炎も、あの二人は信用してたから、もし良ければって思ってたんでしょうね。
そしたら、魏炎の妖力は受け継がれるわけだし?」
「・・・分かりました。」
あら、あっさり。でも、まぁ、殺ちゃんがそう言うんなら・・・。
そういって彼女はパンパンと手を叩く。
「入ってらっしゃい、楼蘭。」
そして、入ってきたのは誠に美しい美女だった。
凛としたその目に、藍の色の着物は良く映えていた。
さらさらという音を立てて彼女はそこに座る。
流れるような黒く、長い髪を束ねて金の簪が光った。
その姿は、かの光源氏の愛人、朧月夜に良く似ている。
―照りもせず
曇りも果てぬ春の夜の
朧月夜に似るものぞなき・・・。
くすと彼女は笑い、こう言った。
「殺生丸。それで良いの?」
とたんに殺生丸の脳裏にあの者の笑顔が、姿が横切った。
いけない。私の傍では失ってしまう。
「殺生丸。真に貴方が欲しているものを教えてあげましょうか。」
彼女は何かを、殺生丸の中の何かを覗き込むようにして、殺生丸を見た。
「貴方は、自分が何を欲しているか分かる?」
殺生丸の顔に不安の色が浮かび上がる。
「教えてあげましょうか?」
もう一度楼蘭がたずねた。
「いい。分かった。」
殺生丸は言った。
「私は、力を欲している。そうだろう?まだ私に足りないものがあるとでもお前は言うのだろう。」
くすり。また、彼女は笑った。
「私を誤魔化すつもり?無駄な事よ。だって、私、生留様から能力を受け継いだんだもの。」
「何?」
「いいから。聞きなさい。貴方は、彼女を欲している。」
「・・・。」
「今、戻ってあげないと、彼女は死ぬかもしれない。
分かってるんでしょう。彼女の血の臭いが数分前からしていること。」
「ふん。くだらん。私は帰る。」
くるりと背をむけ彼はそこを去った。
行くは彼女の場所かもしれない。違うかもしれない。
「これで良いんですか?」
「ありがとv」
そのすぐ後、生留は永遠の眠りに就く。
―私はね、最後に殺ちゃんの心を知りたくなかった。
だって、もしかしたら、殺ちゃんも人間を心から愛しているかもしれないでしょ?
貴方が見たら、私には分からない。
だから、貴方に私の能力を授けたの。
・・・人間なんて・・・。
私の愛した人を全て奪っていく、泥棒よ・・・。
嗚呼、嫌い。人間なんて・・・。
ああ、こんな事を言うつもりじゃなかったのに・・・。
楼蘭。
貴方にこんな思いはしてほしくない。
この能力を使って、いい男性を選んでね・・・?
嗚呼、魏炎・・・。
迎えに来て・・・よぉ・・・。
貴方は、もう、私の事なんてどうでもいいの・・・?
そうなのね・・・。
「生・・・留様・・・。遅いですよ・・・。
愛した後にこんな能力を授けられても・・・。」
ふ、と彼女は嘲笑う。
それは、自分に対してなのかもしれなかったし、畏れ多くも生留に対するものなのかも知れなかった。
でも、愛して、貴方は幸せだったのではないのですか・・・?
本当に私達女というものは・・・。
そして、殺生丸はというと、臭いのあるほうへ駆けていた。
無論、邪見は置いてきぼりだ。
「りん!!」
息を切らして森を突っ切ると湖があった。
そこに、りんの姿と神楽の姿。
「ふん。」
神楽はそこを退散した。
再びりんに目を向けると腕に切り傷があった。
「殺生丸様・・・。」
置いて行った自分に責める顔もせず、彼女は少し驚いたような顔で自分の名を呼んだ。
「大丈夫か?」
「はいっ!勿論です!」
しかし、笑顔とは裏腹に額には脂汗が浮いていたし、かなりの出血量だった。
「ふん。嘘をつけ・・・。」
そう言うと、彼はペロと彼女の傷口を舐めた。
「せ、殺生丸様!?」
あまりに急な出来事にりんは目を点にした。
頬に血が上るのが分かった。
「ふん。」
そういう殺生丸は少し微笑んでいるように見えた。
「行くぞ。りん。」
そう、彼は言った。
しかし、何故神楽がりんを襲ったのかは謎のままだった。
あれは、奈落が命令したものではないようだった。
もしかすると、それは、女なら誰でも持つ、「嫉妬」という物だったのかも知れなかった。
―女は、常に男の後ろで、男に命令されて生きる生き物でした。
それでも、かの源氏物語に出てくる朧月夜だけは違いました。
彼女は、朧な形であっても、最後まで自分を貫き通しました。
私も、そんな生き方がしたかった・・・。
―俺は、お前をそんな風に扱ったかよ?
―・・・魏炎・・・。
迎えに来て・・・くれたの・・・?
こちらに駆けて来る少女がいた。
それは、私に笑顔を教えてくれた者。
決して失ってはならぬ。
私の傍ではきっと失ってしまう。
だから―・・・。
「良いのですか?殺生丸様。」
「何がだ。」
「りんを置いていったことですが・・・。」
「なんだ、その事か。」
彼はさして気にもしていない様子でこう言った。
「恋しいのか?ならば、私の傍を離れてりんのところへ行ってくれても構わんのだぞ。」
その言葉は、一見とげが有る様だが、
実際言われてみた者は拍子抜けするほど優しさが含まれていた。
そして、彼の顔もまた微笑んでいた。
何が嬉しいのか。何が楽しいのか。
長年お供をしてきた邪見にもわからない微笑だった。
そして、目的地。
まるで、平安時代の都のように広く、そして、華やかな場所だった。
そんな場所でこちらに駆けてくる女がいた。
「殺ちゃん!!」
その女は本当に嬉しそうな顔で駆け寄ってくる。
「母上。お変わりなく、元気そうで。」
少し笑ったような表情で言う殺生丸に彼女は言う。
「いやねvv一応、危篤なのよ?余命、1年だってvv」
分かったような、分からないような理屈と、本当に他人事のように話す母親に
すっかりペースを崩されてしまった、殺生丸だった。
が、そんなことは言ってられない。
自分の母親の命だ。
「一体どうしたと言うんです?治す方法は?」
「あぁ、良いのよvv死にたいからvv」
彼は一瞬言葉を失った。
あくまで笑顔を絶やさない事にも、驚かされた。
しかし、彼女の笑顔の中にこれほどの悲しみを見たのは初めてだった。それに、彼は驚愕した。
「さ、御殿の中にお入んなさいvv」
御殿へ入ると、ぞろぞろと僕たちが降伏する。
それは、見慣れた光景であった。
が、彼はこんな僕たちを知らない。
子供の頃、見慣れた僕が、こんなにも顔が良く似ているのに、まるで別人だった。
主人の余命を知り、悲しみに打ちひしがれているとでもいうようだった。
いや、そうなのだ。
「母上・・・。」
「でねvv」
殺生丸の言葉を彼女はさえぎった。
「もうそろそろ、殺ちゃんにも結婚して欲しいのvv」
「は?」
何を言い出すのかと思いきや、こんな時にこんな話を持ち出すとは。
殺生丸は頭が痛くなる思いだった。
「それは、ようございますvv」
「わたくし達、殺生丸様のご幼少の頃からそれをずっと待っていたんでございますのvv」
「殺生丸様の花嫁様となれば、美人に相違ありませんわvv」
「そんな方にお仕え出来るなんてvv」
「わたくし達、果報者ですわね〜vv」
・・・話が勝手に進んでいく・・・。彼はそう思った。
この僕5人組は母が小さい頃から母に付きっ切りで、母も気に入って近くに置くものだから
一層ハイテンションになっていく、そんな者達だった。
年が近いせいか、仕えているというよりは友達感覚であった。
しかし、殺生丸は気付いた。気付いていた。
彼女達の明るい雰囲気の裏にまた、限りない悲しみが潜んでいるという事に。
「ふふっ。それは良かったわね。」
彼女は穏やかな調子で笑う。
しかし、殺生丸にとって、これほど不安な事はなかった。
母は、一度たりとも僕の心の迷いに気が付かないときはなかった。
それが、殺生丸が気が付いているのに彼女が気が付かないなんて事があろうか。
まさか、気が付いて見ぬ振りをしているのではと色々考えをめぐらせていたとき。
「殺ちゃん、何考えているの?」
「え。」
殺生丸は顔を上げた。
考えていて、今更ながらに気が付いた。
母は、自分の考えている事を読めなかった事はない。
いつも考え事をしているとその考えをぴたりと当てるのだ。
「何故?」と聞くと、「だって、殺ちゃんの母様だもの。」と思い切り微笑んで迷いを消してくれた。
だから、知られたくない悩みがあるとき、母の前は危険地帯だった。
そんな母が、「ヨメナイ?」
・・・どうしたというのだろう。
「あのね、殺ちゃん。」
「はい。」
「『りん』っていう子と結婚する?」
「は?」
「連れてるんでしょ?人間の女の子。聞いたわよ刀刀斎にvv」
あの老いぼれ・・・。余計な事を・・・。
どうせ、犬夜叉か誰かに聞いたか、そうでなければ上空から覗き見でもしたのだろう。
「し、しかし、人間を一番忌み嫌っておられたのは母上でしょう?」
焦った風に殺生丸は話す。人間や妖怪等関係なく、結婚することがいやだったのだ。
しかし、彼女の反応は、思い通りに行かなかった。
「じゃ、殺ちゃんは、許嫁の楼蘭ちゃんと結婚するのね?」
「は?」
楼蘭というのは、彼の幼馴染だった。
だが、それだけの関係で、許嫁になっていたとは、彼は、知らなかった。
「な、何故、楼蘭が許嫁なのです?」
「あのね。殺ちゃんが生まれる前に、もし、両者に特別な想いが無ければ、
この二人は結婚させよう。ってことになってたのよvv」
「それは、父上も同意なされた事ですか?」
「そうよ。楼蘭ちゃんのご両親が私達の僕の中で一番強かったのは知ってるわよね?」
「は。」
「だからよ。魏炎も、あの二人は信用してたから、もし良ければって思ってたんでしょうね。
そしたら、魏炎の妖力は受け継がれるわけだし?」
「・・・分かりました。」
あら、あっさり。でも、まぁ、殺ちゃんがそう言うんなら・・・。
そういって彼女はパンパンと手を叩く。
「入ってらっしゃい、楼蘭。」
そして、入ってきたのは誠に美しい美女だった。
凛としたその目に、藍の色の着物は良く映えていた。
さらさらという音を立てて彼女はそこに座る。
流れるような黒く、長い髪を束ねて金の簪が光った。
その姿は、かの光源氏の愛人、朧月夜に良く似ている。
―照りもせず
曇りも果てぬ春の夜の
朧月夜に似るものぞなき・・・。
くすと彼女は笑い、こう言った。
「殺生丸。それで良いの?」
とたんに殺生丸の脳裏にあの者の笑顔が、姿が横切った。
いけない。私の傍では失ってしまう。
「殺生丸。真に貴方が欲しているものを教えてあげましょうか。」
彼女は何かを、殺生丸の中の何かを覗き込むようにして、殺生丸を見た。
「貴方は、自分が何を欲しているか分かる?」
殺生丸の顔に不安の色が浮かび上がる。
「教えてあげましょうか?」
もう一度楼蘭がたずねた。
「いい。分かった。」
殺生丸は言った。
「私は、力を欲している。そうだろう?まだ私に足りないものがあるとでもお前は言うのだろう。」
くすり。また、彼女は笑った。
「私を誤魔化すつもり?無駄な事よ。だって、私、生留様から能力を受け継いだんだもの。」
「何?」
「いいから。聞きなさい。貴方は、彼女を欲している。」
「・・・。」
「今、戻ってあげないと、彼女は死ぬかもしれない。
分かってるんでしょう。彼女の血の臭いが数分前からしていること。」
「ふん。くだらん。私は帰る。」
くるりと背をむけ彼はそこを去った。
行くは彼女の場所かもしれない。違うかもしれない。
「これで良いんですか?」
「ありがとv」
そのすぐ後、生留は永遠の眠りに就く。
―私はね、最後に殺ちゃんの心を知りたくなかった。
だって、もしかしたら、殺ちゃんも人間を心から愛しているかもしれないでしょ?
貴方が見たら、私には分からない。
だから、貴方に私の能力を授けたの。
・・・人間なんて・・・。
私の愛した人を全て奪っていく、泥棒よ・・・。
嗚呼、嫌い。人間なんて・・・。
ああ、こんな事を言うつもりじゃなかったのに・・・。
楼蘭。
貴方にこんな思いはしてほしくない。
この能力を使って、いい男性を選んでね・・・?
嗚呼、魏炎・・・。
迎えに来て・・・よぉ・・・。
貴方は、もう、私の事なんてどうでもいいの・・・?
そうなのね・・・。
「生・・・留様・・・。遅いですよ・・・。
愛した後にこんな能力を授けられても・・・。」
ふ、と彼女は嘲笑う。
それは、自分に対してなのかもしれなかったし、畏れ多くも生留に対するものなのかも知れなかった。
でも、愛して、貴方は幸せだったのではないのですか・・・?
本当に私達女というものは・・・。
そして、殺生丸はというと、臭いのあるほうへ駆けていた。
無論、邪見は置いてきぼりだ。
「りん!!」
息を切らして森を突っ切ると湖があった。
そこに、りんの姿と神楽の姿。
「ふん。」
神楽はそこを退散した。
再びりんに目を向けると腕に切り傷があった。
「殺生丸様・・・。」
置いて行った自分に責める顔もせず、彼女は少し驚いたような顔で自分の名を呼んだ。
「大丈夫か?」
「はいっ!勿論です!」
しかし、笑顔とは裏腹に額には脂汗が浮いていたし、かなりの出血量だった。
「ふん。嘘をつけ・・・。」
そう言うと、彼はペロと彼女の傷口を舐めた。
「せ、殺生丸様!?」
あまりに急な出来事にりんは目を点にした。
頬に血が上るのが分かった。
「ふん。」
そういう殺生丸は少し微笑んでいるように見えた。
「行くぞ。りん。」
そう、彼は言った。
しかし、何故神楽がりんを襲ったのかは謎のままだった。
あれは、奈落が命令したものではないようだった。
もしかすると、それは、女なら誰でも持つ、「嫉妬」という物だったのかも知れなかった。
―女は、常に男の後ろで、男に命令されて生きる生き物でした。
それでも、かの源氏物語に出てくる朧月夜だけは違いました。
彼女は、朧な形であっても、最後まで自分を貫き通しました。
私も、そんな生き方がしたかった・・・。
―俺は、お前をそんな風に扱ったかよ?
―・・・魏炎・・・。
迎えに来て・・・くれたの・・・?